画像や動画、テキストの生成に活用されることの多い生成AIですが、どのように導入すればよいのかについて知らない方も多いのではないでしょうか。生成AIの導入にあたっては、自社にとって適した生成AIは何かについて追究することが大切です。
この記事では、生成AIの導入手順をはじめ、大手企業による導入事例、失敗例について解説します。生成AIの活用を視野に導入を検討される方は、本記事を参考にしながら導入・活用を図りましょう。
生成AIとは?
生成AIとは、モノやアイデアを新たに生み出すことに対応した人工知能のことです。指定されたデータに基づき、業務や作業の自動化を実現する従来のAIとは異なり、収集した情報やデータから規則性を見つけ、その上で新たなデータを生み出せる特徴があります。
現在多くの企業で活用されることの多いOpenAI社の「ChatGPT」やMicrosoft社の「Copilot」、Google社による「Gemini」などは生成AIの代名詞でもあり、テキストの生成をはじめ近年では画像や動画の生成などにも対応しています。
生成AIにはできることが多く存在する一方で、できないこともいくつかあります。それぞれについては以下の記事でまとめていますので、興味のある方はこちらもぜひご覧ください。
関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介
生成AIの導入手順
生成AIを社内に導入するためには、いくつかの手順に沿って行う必要があります。具体的には下記の通りです。
- 目的の明確化
- 業務の選定
- 体制構築
- 生成AIの選定・導入
- マニュアル作成・運用
- 評価分析・改善
ここでは、生成AIを導入する際の手順について詳しく解説します。
目的の明確化
まずは、生成AIを導入してどのようなことを成し遂げたいのかを明確にしましょう。目的を明確にしておくことで、どのデータを準備すべきかが判断しやすくなります。また従業員をはじめとしたステークホルダーとの意見の調節も、導入目的が明確にまとめられているからこそ説得力のある説明が行えるでしょう。
例えば、日々の問い合わせ業務に対応する従業員の作業負担を軽減させたい、問い合わせ対応を自動化させ深刻なトラブルなどに限って対応できるようにしたいなどです。
生成AIは画像や動画をはじめ、テキストやプログラミングコードの生成などできることが多岐にわたります。だからこそ生成AIの特徴と自社が実現させたい理想像を照らし合わせ、適切なものを選べるよう目標を定めておきましょう。
業務の選定
生成AIを導入する目的を決めた後は、代替させたい業務を具体的に選定しましょう。どのような業務に生成AIを導入するかによって選ぶべきAIツールが判断しやすくなるためです。仮に社内外からの問い合わせ対応を自動化・効率化させたいときは、AIチャットボットが適しています。企業PR用の画像を作成したいのであれば、画像生成AIを選ぶとよいでしょう。
「生成AIを導入したものの、イメージしていた結果とは違っていた」など導入のミスマッチを防ぐためにも、代替させたい業務は具体的に洗い出し、その上で適切なAIツールを選ぶことが大切です。
なお、BUSINESS HACKではAIをはじめとしたITツールを導入した企業の成功事例についてまとめた記事も公開中です。業務の選定にお悩みの方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
関連記事:業務効率化に成功した10社の企業事例|メリットや成功させるコツとは
体制構築
業務の選定が終わった後は、全社で対応できるよう体制構築を図りましょう。例えば、生成AIを運用するためのガバナンスの策定によって、経営層やDX推進部門を中心に企業全体の共通認識が深まり、適切な運用・活用が実現します。
しかし、生成AIの運用・活用にあたっては、さまざまなリスクと隣り合わせであることも念頭に置かなければなりません。特にサイバー攻撃は早急な対策が必要な問題のひとつで、2025年2月の産経新聞では、日本に対するサイバー攻撃関連の通信数が平成27年で632億回だったのに対し、令和5年には約6197億回とおよそ10倍にまで増加したと報じています。
これらのことから、インターネットを介する生成AIを活用する場合にはセキュリティポリシーに沿ったセキュリティソフトの導入や、二段階認証を活用、役職や部署、業務に応じた権限を付与するなど、適切な対策を講じる姿勢が求められます。
関連記事:生成AIの対策まとめ|技術的・法的リスクを避ける術を紹介
参考:産経ニュース|日本へのサイバー攻撃関連通信数、8年で10倍に 「14秒に1回」 各国で安全保障強化
生成AIの選定・導入
導入目的の明確化、具体的な業務の選定、全社での体制構築が終わった後は、自社に適した生成AIを選び、導入へと進みます。繰り返しになりますが、生成AIは機能が多岐にわたることから、自動化や効率化させたい業務に適したAIツールを選ぶよう心がけましょう。
なお、導入の際はスモールスタートで試すことをおすすめします。最初から全社に導入させた場合、仮に効果が得られなかったときに社内の体制構築が無駄に終わる恐れがあるためです。スモールスタートではじめ、予想通りの効果が得られたときは、部署や業務などで分け、徐々に浸透させていきましょう。
デジタルツールに関する知識・技術を有する従業員が在籍し、開発リソースも十分確保できるのであれば、自社開発を選ぶのも方法のひとつです。
マニュアル作成・運用
生成AIを使用し十分な効果が得られると判断できたときは、全社での運用・活用を見据え、マニュアルを作成し全従業員へ共有しましょう。マニュアルには操作方法はもちろん、最初に取り決めた目標や導入後の企業の未来像などを盛り込むことで共通認識のなかで実用化を目指すことができます。
また、生成AIによる業務上のメリットも簡単に記載することで、従業員も「自分ごと」と捉えることができ、積極的な活用につながるでしょう。
評価分析・改善
生成AIを導入後は、一定期間が経過したタイミングで評価分析を実施しましょう。1か月や3か月間隔で生成AIによる効果について部署・業務ごとにヒアリングやアンケート調査を行うことで、当初決めていた目標が実現できているかについて評価できるほか、改善点や課題を洗い出すことができます。
仮に改善点や課題が多く届いたときは、内容を1つひとつをメモし、段階的に対処していくことで今以上の利便性につなげられるでしょう。なお生成AIの活用におけるメリットについては以下の記事でまとめていますのでこちらもご覧ください。
関連記事:生成AIのメリット・デメリットとは?活用シーンや注意点を解説!
生成AIの導入事例
生成AIはさまざまな企業で導入が進んでいます。ここでは、大手企業による導入事例について解説します。
日本コカ・コーラ株式会社
日本コカ・コーラ株式会社では、消費者の身近な場所に生成AIを取り入れ、関係性強化に成功しています。2023年12月には同社とOpenAI社などで立ち上げた生成AIプラットフォーム「Create Real Magic」を活用し、オリジナルのクリスマスカードが作成できるWebサイトを一般公開しました。
さらに2024年5月には同社の主力コーヒー飲料「ジョージア」と生成AIを使った占いもスタートさせており、消費者との関係性強化に向けた積極的な取り組みが進められています。
参考:ライブドアニュース|コカ・コーラの「Create Real Magic」でオリジナルのクリスマスカードを作ろう
参考:日本経済新聞|日本コカ・コーラ、生成AIで占い ジョージア施策第3弾
江崎グリコ株式会社
江崎グリコ株式会社では、Allganize Japan株式会社によるAIチャットボット「Alli」でバックオフィス業務の効率化を図っています。業務効率化の実現に向けて全社で業務の可視化を実施したところ、バックオフィス部門では問い合わせ対応が上位を占め、管理部門や情報システム部門では社内問い合わせ対応によって本来の業務に支障が出ていました。
AIチャットボットを導入したところ、問い合わせ対応件数が毎月30%以上削減できたほか、非システム部門でもタイムリーにFAQを更新したことで業務効率化につながりました。
参考:PR Tims|Glicoグループのバックオフィス効率化をAIチャットボット「Alli」で支援 | Allganize Japan株式会社のプレスリリース
パナソニック コネクト株式会社
パナソニック コネクト株式会社では、生成AIによる業務生産性と従業員のAIスキルの向上、シャドーAI利用リスクの軽減などを目的に、2023年、全社を対象としたAIアシスタントサービス「ConnectAI(旧称ConnectGPT)」を導入しました。
同AIツールの試験運用の結果を受け、今後はカスタマーサポートセンターのデータを活かした社内業務の改善と業務効率化を目指しています。
参考:パナソニックホールディングス株式会社|パナソニック コネクトのAIアシスタントサービス「ConnectAI」を自社特化AIへと深化 | 技術・研究開発
ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸株式会社では、およそ6,500拠点において数か月先の業務量を予測するAIとして「荷物量予測システム」を開発し、拠点で働く従業員・車両の適正な配置に成功しています。
Amazonや楽天市場などのECサイトの普及により、毎日膨大な量の荷物を顧客に届ける同社ですが、各拠点で取り扱う荷物の地域差や営業における繁閑差が問題視されていたことを受け、適正な従業員のシフトや車両手配を実現するためにAIシステムが導入されました。
人手不足が叫ばれる物流業界にとっては同社のAI導入は画期的であり、また多様なシーンでの業務効率化につながるきっかけとなっています。
参考:ヤマトホールディングス株式会社|ビッグデータ・AIを活用した配送業務量予測および適正配車のシステム導入について― アルフレッサとヤマト運輸によるヘルスケア商品の共同配送スキーム構築の第一弾 ―
住友化学株式会社
住友化学株式会社では、生成AIツールのひとつである「ChatSCC」の運用を始め、研究開発の効率化と生産性の向上に成功しています。自社事業に向けて改良されたツールは、およそ6,500名の全従業員が使用しており、将来的には独自データの有効活用による既存事業の競争力確保、新規ビジネスモデルの創出を図るとしています。
参考:住友化学株式会社|社内向け生成AIサービス「ChatSCC」の運用を開始~飛躍的生産性向上と独自データの有効活用を目指す~
生成AI導入における企業の失敗事例
生成AIを導入したものの、結果的に失敗に終わった事例も存在します。ここでは、企業の失敗事例について解説します。
ソフトバンク株式会社
世界的にも有名で、自社の独自製品でもあるロボット「Pepper」を誕生させたソフトバンク株式会社でも生成AIによる失敗事例があります。そのひとつとして、生成AIに対する従業員の意見を聞かず、オーバーヘッド部隊の事業戦略部門が現場をイメージして学習データを構築した結果、理想的な業務効率化の実現に至らなかったケースです。
このトラブルをきっかけに、生成AIの活用は「机上の理論」であってはいけないこと、従業員の声を聞かずしてよいツールはできないことを学び、トライアンドエラーを繰り返しながら運用と実用につなげています。
参考:ITmedia エンタープライズ|ソフトバンクもAI導入で失敗していた――「3+1の壁」を突破した今だからこそ言えること(要約):SoftBank World 2017 –
マクドナルド
マクドナルドでは、モバイルオーダーやセルフレジなどにDXを取り入れ、顧客体験を大きく変化させた経験を持つ企業です。
しかしその一方で、ドライブスルーにおける音声AIの活用では、顧客のイントネーションやアクセントに対応しきれず注文とは異なる商品が登録されたり、自動化によって従業員のダブルチェックが必要となったりするなど、効率化とはほど遠い結果に着地した経験があります。
こうした課題を通じて、マクドナルドは「テクノロジー導入=即効性」ではなく、「人との連携を前提としたDX」の重要性にいち早く気づいた企業でもあるため、今後の進化に期待が集まります。
参考:Joint Statement from McDonald’s and IBM
参考:YouTube|McDonald’s is removing its Ai Drive-Thru Voice-Ordering System After Viral Mishaps –
エア・カナダ
エア・カナダでは、顧客からの問い合わせに対応するべく、2019年に生成AI技術を活用したチャットボット開発に成功しました。チャットボットの活用を通じてフライト予約や問い合わせなどさまざまな対応を効率化させ、顧客満足度の向上を図っています。
しかし、ある顧客にチャットボットによる誤案内が届いたことで事態は一変します。情報を信じた顧客が同社に利用申請を行ったところ、実際の規定とは異なることを理由に拒否され、顧客による訴訟問題へと発展しました。裁判所は「チャットボットの誤案内も公式Webサイトの一部」とみなし、同社から顧客に対して賠償命令が下りました。
この出来事をきっかけに、エア・カナダではAI活用の透明性や説明責任がより一層重視されるようになり、顧客対応の信頼性を高める新たな方針づくりへと踏み出しています。
参考:Air Canada ordered to pay customer who was misled by airline’s chatbot | Canada | The Guardian
サムスン電子
サムスン電子では、社内業務の効率化や生産性の向上を目的に2023年にChatGPTを試験導入しました。しかし、導入初期にエンジニアが学習データのひとつとして社内の機密ソースコードをChatGPTに入力し、外部に漏洩するリスクが判明しました。
リスクを最小限に減らすため、2023年5月にはChatGPTを含む生成AIツールの社内利用を全面的に禁止し、従業員たちによる業務効率化への期待が打ち破られた事例があります。
この事例を受けてサムスンは、生成AIの業務利用を一時的に禁止するだけでなく、個人端末での利用においても社内データの取り扱いを厳格に制限し、違反時には解雇も辞さない方針を打ち出しました。リスク管理と技術活用のバランスを模索する姿勢は、今後の企業のAI活用における重要な指針となりそうです。
参考:Samsung Bans ChatGPT, Google Bard, Other Generative AI Use by Staff After Leak – Bloomberg
まとめ
生成AIの導入にあたっては、導入によってどのような効果を得たいのかなど、具体的な目標を明確にした上でAIツールを選ぶことが大切です。そのためには、従業員の意見を取り入れながらDX推進を実行できるよう、DX推進部門の設置が推奨されます。
DX推進部門の存在によって従業員の意見を取り入れた上でAIツールが選べることに加えて、DXに対する経営層の理解を深めるきっかけとなり、円滑なDX推進が行えるでしょう。
PeacefulMorning社では、貴社のDXプロジェクトに最適な人材を即日ご提案するサービス「DX Boost」を提供しています。DX推進部門の立ち上げに伴い、社内従業員だとリソースが不足している際はぜひお気軽にご相談ください。高い技術とコミュニケーション力を有するエンジニアを厳選してご紹介いたします。

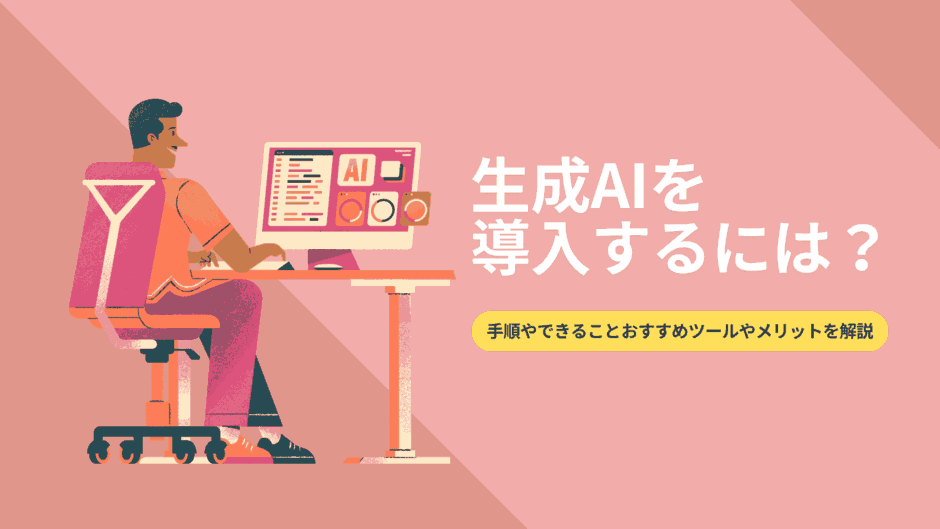



コメントを残す