生成AIは、分析したデータによって画像や動画、テキストなどを新たに作り出すことができる人工知能です。特別な技術や知識を習得しなくても、業界・業種にちなんだモノ・アイデアを生み出せることから、日本でもDX推進と共に生成AIの活用が増えています。
この記事では、生成AIにおけるメリットをはじめ、デメリットと対策、具体的な活用シーンについて解説します。
生成AIとは?
生成AIとは、テキスト、画像、音声といったさまざまなデータを取り込み、深層学習を通じてAI自らが学習を重ねることで、オリジナルの文章、画像、音楽など、新たなデータを作り出すことができる人工知能を指します。生成系AIやジェネレーティブAIなどと呼ばれることもあり、一般的なAIとは異なり、データの収集・分析を通じて新たなモノ・アイデアを生み出すことができる特徴を持ちます。
また、生成AIは多様なシーンで活用できますが、できないことも存在します。生成AIの概要をはじめ、できることとできないことについては以下の記事をご覧ください。
関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介
生成AIのメリット
生成AIには多くのメリットがありますが、代表的なものは下記の通りです。
- 作業効率・生産性の向上
- 人員不足・業務負担の軽減
- コスト削減
- アイデア幅の拡大
- リアルタイムでのデータ分析
- 24時間365日でのサービス提供
- 品質維持
ここでは詳細について解説します。
作業効率・生産性の向上
生成AIの活用によって作業効率や生産性の向上につながります。例えば人間の力では多くの時間や労力を必要とする制作作業の場合、生成AIに必要なデータの収集・分析によって効率よく進められます。ブログ記事やWebコンテンツの制作であれば、細かなプロンプトを入力することで瞬時に1つの記事が抽出され、記事制作の効率化につなげられます。
この場合「〇〇というキーワードの上位記事を網羅し、3,000文字以上のコラム記事を生成してください」のように詳細なプロンプトを提示することで、質の高いコンテンツが抽出されやすくなります。
プロンプトの内容によって高品質なコンテンツ制作も実現可能であることから、生産性向上に寄与する点もメリットです。
人員不足・業務負担の軽減
生成AIによって人員不足をリカバリーすることも可能です。例えば企業のサポートセンターに生成AIを活用したチャットボットや自動応答システムを導入することで、軽微な問い合わせであれば生成AIで完結できます。
そもそもAIは反復的かつ定型的な業務を得意としています。生成AIはその一歩先を進み、深層学習によってAI自らが学習を重ね、新たなコンテンツを生み出すことができる人工知能なので、人的資源を要する業務をデータ化し、生成AIに分析させれば人員不足はもちろん、業務負担の軽減も実現できます。
コスト削減
コスト削減にも生成AIは有効です。従来であればクリエイターやデザイナーに外注していた企業のロゴ制作なども、生成AIに必要なプロンプトを入力することで理想に近いデータを抽出してくれます。より理想に近づけたいときもプロンプトの精度を上げるだけでよいので、デザイナーなどとのミーティングも不要です。
外部業者に依頼していた業務を生成AIに代替できれば、コストを大幅にカットできるので、人材育成の強化や福利厚生の拡充など企業の内部に費用を充てることができます。
アイデア幅の拡大
生成AIにプロンプトを入力すると、制作物に対するアイデアのヒントを得ることもできます。一般的に、制作物におけるアイデアの創出は多くの時間が掛かりますが、業種に適したデータを生成AIに分析させることで瞬時にさまざまなアイデアを抽出します。
生成AIは多様なデータを分析・パターン化して新たなデータを生み出すので、抽出されたデータに既視感を覚えることもあります。しかし抽出されたデータと人間の創意工夫によっては想像もしなかったまったく新しいモノを生み出せる可能性もあります。人工知能と人間の掛け合わせによって大きな相乗効果に期待できる点はメリットといえるでしょう。
リアルタイムでのデータ分析
生成AIは最先端のAIであるため、ビッグデータも瞬時に収集・分析します。どれだけ多くのデータもリアルタイムで解析し必要なデータを抽出でき、作業速度の向上が見込まれ迅速な意思決定につながります。
例えば労力や時間を要するマーケティング戦略の策定であれば、生成AIの活用によってユーザーニーズを捉えたデータを迅速かつ効率的に手に入れることができるでしょう。余った時間は新たなサービスの考案に充てることもできます。
従業員の業務に対する時間的リソースを削減し、1人1人の時間を確保しやすくなるため、成長機会につながれば企業力強化も実現可能です。
24時間365日でのサービス提供
生成AIは年中無休で働くことができます。活用シーンによっては24時間365日いつでも適切なサービスを提供できることがメリットです。例えば企業のサポートセンターにおける自動対応などが該当します。
また、生成AIの利用は基本的にクラウド型であるため、アイデアのヒントを得たいときやコンテンツ・Webメディアの方向性を洗い出したいときなども時間を気にせず質問でき、次のステップの決断に活かすことができます。
品質維持
必要なデータを分析することで、常に一定品質を保ったデータを抽出できるのもメリットです。作業フェーズをデータ化したものを生成AIに読み込ませれば、品質を保った状態での生産が実現します。精度の高いプロンプトによっては従業員のニーズを捉えた業務も代替できるため、従業員の体調やモチベーションに左右されることなく生産可能です。
生成AIのデメリットと対策
生成AIには多くのメリットがある一方で、下記のようなデメリットも存在します。
- 権利侵害リスク
- フェイク情報
- 品質維持の難しさ
- セキュリティリスク
- サイバー攻撃
- 法整備
- コンテンツによっては生成不可
ここではデメリットの詳細と具体的な対策方法について解説します。生成AIの活用・導入する際は事前に把握しておきましょう。
権利侵害リスク
生成AIが生み出す情報・コンテンツにおいては権利侵害に関するリスクがある点に注意しなければなりません。多くのデータを収集・分析する際は、すでにWeb上で公開されたデータがベースになっているため、抽出データはそのまま使用せず、人の手を加える、内容を確認するといった工夫・対策が欠かせません。
2024年には生成AIによる声優の声の無断利用が報道されました。多くの声優陣は”声における著作権保護”を目的とした啓発キャンペーンも始めています。
生成AIは進化によって人間に多くの利便性を提供する一方、人間の権利を脅かす可能性がある点には注意が必要です。
参考: NHK|“AIで声の無断利用やめて”声優などの業界団体が声明
フェイク情報
生成AIが生み出すデータは日に日に精度を増しており、正しい利用によってはクリエイティブ業界において幅広い活躍が期待できます。しかしその一方で、悪用されやすい点も改めて認識しておく必要があります。
例えばX(旧Twitter)では、2016年の熊本地震の際、動物園からライオンが放たれたと投稿されました。一緒に投稿された画像はまさに投稿内容を信じたくなるものであり、投稿はたちまち拡散され、人々の不安を煽る形となりました。
生成AIの高品質な画像・動画が生み出せる特徴を悪用したことで、デマや不確かな情報がSNSに溢れやすくなりました。生成AIを利活用する際は抽出データはそのまま使用せず、専門家によるファクトチェックを求めることが大切です。
参考:朝日新聞|「ライオン放たれた」ほかネット偽情報135件 熊本地震で警察記録
品質維持の難しさ
生成AIの利活用によって品質維持に期待できる一方、不正確な情報が採用されることも多いです。必ずしも品質維持に寄与するといった認識は避け、常に情報の整合性を確かめる姿勢を心がける必要があることも念頭に置きましょう。
セキュリティリスク
大量のデータを要する特徴から、活用シーンによっては個人情報や機密情報の漏洩が懸念されます。大切な情報を取り扱うのであれば少人数のチームを設け、限られた範囲で取り扱う、現システムに対応したセキュリティツールを導入するなどの対策を心がけましょう。
1つひとつの取り組みによって社内整備がなされることから、情報漏洩をはじめ不正アクセスなどのリスクも最小限に抑えられるでしょう。
サイバー攻撃
ネットワーク環境を介して行われる、スマートフォンなどでの不正操作、いわゆるサイバー攻撃によって、金銭や個人情報が盗まれたり企業システムの停止が余儀なくされたりすることもあります。生成AIに限ったことではないものの、インターネットを介して利活用する特徴から、サイバー攻撃に対する懸念も無視できない項目のひとつです。
サイバー攻撃を防ぐためにも、社内のセキュリティ対策を万全に整えることが大切です。またIT技術に精通した従業員の育成・確保を実施し、万が一のトラブルの際も迅速に対応できるよう準備する必要もあるでしょう。
法整備
生成AIをはじめとしたAIの進化と法整備にズレが生じている点も挙げられます。データの著作権や生成AIそのものの法的な位置づけは、まだまだ整っていないのが現状です。声優の声の問題においても著作権法の改正に向けた声は高まっているものの、AIの利活用を直接律する制定はなく問題は波紋を広げたままです。
生成AIを中心にAIの利活用は精度とともに増加する予想もあることから、常に国の動きは注視し、改正されれば迅速に取り入れる姿勢が欠かせないでしょう。
コンテンツによっては生成不可
生成AIはさまざまなシーンでの利活用が可能ですが、すべてのコンテンツを生み出せるわけではありません。人間の感情を理解し表現すること、さらには専門性を要する業界・分野だと生成が難しいことがあります。
例えば「笑顔の女性」の画像は生み出せても「春の訪れを喜ぶ女性」の画像を忠実に再現することは難しいです。生成AIから抽出されるデータの再現度を高めるためには、生成AIが理解できるプロンプトを構成する必要があります。
関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介
生成AIの活用シーン
生成AIの特徴は多様なシーンで活用できます。代表的な6つのシーンは下記の通りです。なお、AIをビジネスで活用したい方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:AIをビジネスで活用するには?活用する上での目的や事例、成功のコツを解説
1. 文章作成
さまざまなデータを収集・分析できる能力から、文章作成に活用できます。提示する資料やプロンプトによっては、ニーズを捉えたコンテンツが作成できるでしょう。ただし、一文が長くなっていたりファクトチェックが必要になったりすることもあるため、抽出されたデータは必ず整合性を確認し、必要に応じて正しい情報に手直しすることをおすすめします。
2. 音声の文字起こし・要約
会議やオンラインミーティングで録音したデータを文字に起こすことはもちろん、内容を要約することも可能です。文字起こしや資料の予約にはある程度の時間を要しますが、生成AIに代替すればわずかな時間で1つの資料にまとめることができます。なお、整合性を確認するためにも、同僚や上司に提出する際は資料の最終チェックを忘れずに実施しましょう。
3. 画像・動画の生成
生成AIは、企業におけるイメージ画像や人材採用におけるPR動画の作成にも活用されています。新たなモノを生み出せる特徴から、外部クリエイターに依頼している企業にとっては魅力的な活用方法といえるでしょう。
外注に依頼した場合、制作費用が掛かることからコストが気になる部分も、生成AIに適切な資料・プロンプトを提示することで、理想的な画像・動画を手にすることができるでしょう。
4. アイデアの参考
Webサイトやコンテンツの方向性、企画やキャッチコピーなども生成AIに任せることができます。適切な資料とプロンプトを提示すればさまざまな案を提示してくれます。生成AIが抽出したデータをヒントにすることで、これまでは思いつかなかったアイデアへとつながる可能性があります。また、アイデアや思考の整理、抽象的な案の具体化にも活用できます。
5. プログラミング補助
生成AIはプログラミングに対応したツールも多く展開されています。コードの作成・編集にあたってはプログラミングコードを覚える必要がありますが、適切なプロンプトを入力することで状況に応じたコードを取得できます。軽微なシステムエラーであれば、生成AIが抽出したコードでリカバリーすることも可能です。
ただし、生成AIのデータは整合性が確保できていない場合もあるため、そのまま使用することは避け、自社に在籍するプログラマーにチェックを通すことをおすすめします。
6. Web上での顧客対応
近年、大手企業を中心にサポートセンターにおける自動応答が増加しています。自動応答も生成AIが対応しており、サポートセンターにおける人員削減や労力負担の軽減につなげています。
なお、問い合わせシステムに生成AIを導入する場合、あらかじめ頻繁に届く問い合わせ内容とその答えをFAQにまとめる必要があります。生成AIで問い合わせ業務の効率化を図るときは、事前資料を作成しておくことでスムーズな導入を実現できます。
まとめ
生成AIのメリットには、専門的な技術・知識を持たない人でも、高品質な画像・動画・コンテンツを作り出せることにあります。しかし、高品質なデータを抽出できるからこそ事実とは異なるデータも生まれやすいことから、抽出データの使用にあたっては、ファクトチェックが欠かせないといえるでしょう。
生成AIは主にクラウド型であるため、インターネットを介して必要なデータを送信し、分析させる必要があります。情報の種類によっては漏洩やサイバー攻撃の懸念もあることから、頻繁に利活用するのであれば、自社で生成AIを構築することが望ましいです。
PeacefulMorning社では、RPAやAIの開発経験豊富なプロが、社内の開発者育成を月額10万円からサポートするサービスRobo Runnerを提供しています。画面共有を通じて分からない部分を質問できるサービスも利用できるので、スムーズに知識を養うことができます。
また、社内開発者が増加しても、手厚いサポートをそのまま使うことができるので、ツール開発の推進につなげられます。
日本をはじめ世界中でDXの導入が積極的に行われています。競合他社に乗り遅れる前に、Robo Runnerを通じて人材育成を図り、企業力強化を目指しましょう。

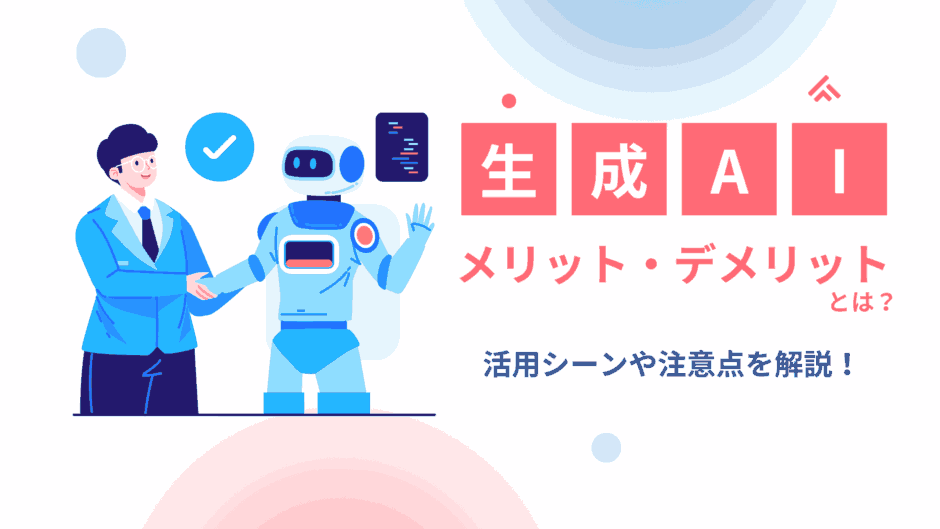


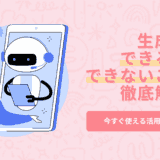
コメントを残す