ChatGPTのような対話型AIを使い、日常生活における疑問について多くの方が質問した経験があるのではないでしょうか。しかし、具体的にどのようなことができ、どのようなことを不得意とするのか知らない方も多いでしょう。この記事では生成AIにできること・できないこと、生成AIを活用するメリットについて解説します。
生成AIとは?
生成AIとは、さまざまなモノ・アイデアを生み出すことに対応した人工知能のことです。あらかじめ指定されたデータに基づき自動化できる従来のAIとは違い、学習データからパターン・関係性を見つけ、テキストや画像などを新たに生成することができます。
多様な業界・シーンで活用される理由の多くは、特別な知識・技術を持っていない方でも新たなモノを簡単に作り出せる点にあります。例えばWebライターのライティング業務も、ChatGPTのような対話型AIにプロンプトと呼ばれる指示を入力することで、Googleなどの上位記事を踏まえたコラム記事を迅速に生成することが可能です。
本来のライティング業務では、上位記事の傾向を分析し1つの記事に仕上げるまでに多くの時間が掛かります。生成AIの技術は日々進化し正確性を高めている背景から、近年では生成AIが制作したコラムを校正する業務がWebライター市場に普及し始めています。
生成AIにできること
AIそのものの進化によって、生成AIもめまぐるしく進化を遂げています。そのため、最近ではさまざまなことに対応できるようになっています。
テキストの生成
生成AIにプロンプトと呼ばれる指示文を提示することで、指示文に沿った文章を生成できます。OpenAIのChatGPTを筆頭にGoogleのGeminiやMicrosoftのCopilotが該当します。テキスト作成を生成AIに任せることで、SNSに投稿する簡単な文章作成やアイデアの創出など幅広い業務で応用できます。
なお、プロンプトの精度によって生成される内容が大きく変わります。そのため、品質の良さやユーザーの潜在ニーズを満たすテキストを生成したいときは、いい文章を生成するためのプロンプトを構成することがポイントになります。
画像・動画生成
生成AIのなかには画像生成に対応したタイプもあり、テキスト入力によってオリジナル画像を生成することができます。Stability AIのStable Diffusionや、Midjourney社による同名の生成AIなどが挙げられ、画像や動画を生成する際も高精度なプロンプトによって品質の高い画像・動画が生成できます。
なお、現在の生成AIで作成できる動画の尺度は短いものに留まっています。しかし、AIの進化速度はめまぐるしいことから、将来的には長尺の動画生成も実現する可能性が高いと予想されています。
音声生成
音声生成に対応した生成AIもあります。具体的には、音声やテキストを入力することで新しい音声を生成できるものです。例えば、同一人物の音声データを大量に学習させることで違和感なく自由に話せるようになるなどです。
1度音声データを学習するとさまざまなシーンで応用できる特徴から、動画のナレーションや自動ガイダンスの音声、多言語通訳などで実際に活用されています。
ソースコード生成
生成AIの活用によってプログラミングに必要なソースコードも生成できます。ソースコードの習得には専門用語の理解が必要になり、独学で学ぶ場合、多くの時間と労力が伴います。しかし、どのシーンで使うソースコードなのかをプロンプトに落とし込み生成AIに提示することで、迅速に必要なコードを生成できます。
ソースコードを生成する上では、あらかじめビッグデータと呼ばれる大量のデータを読み込ませる必要があります。人間では膨大な時間を要する情報の読み込み・抽出も、AIであれば瞬時に分析しパターン化できるので、本格的なソースコードも簡単に生成することができます。
データの要約・翻訳
Webサイト上のコラムやリサーチ結果を取り込むことで、内容を要約することも可能です。10,000文字以上のコラム記事も、内容をかいつまんで把握することができます。
また、英文などで届いたメールを全文コピーし、生成AIに貼り付け、翻訳を依頼することで、多言語での翻訳もできます。海外の言葉に精通した従業員がいなくても、生成AIによってスムーズなやり取りが実現します。
生成AIにできないこと
さまざまなことに対応できる生成AIですが、なかにはできないこともあります。例えばAI自身が自発的に考え新たなモノを創りあげるなどです。具体的にどのようなことなのかを解説します。
自発的な創造
生成AIは、大量のデータをベースに新たなモノを作り出すことに長けています。しかし、データがAIのベースだからこそ自発的に考えてモノを作り出すことには対応できていません。
人間でいう「自分で考えて自分なりの判断で何かを生み出すこと」ができないので、新たなモノを作り出せたとしても、どこか既視感がある、何かに似ているなど、何らかをベースにしたようなモノができあがることがあります。
既視感があるモノが生成されるのは、取り込んだデータを組み合わせて生成しているためです。そのため、人間のようにゼロから何かを作り出せないのが現状です。
感情の理解
生成AIは、取り込んだデータから学習し、パターン化したり分析したりすることを得意としています。あくまで取り込んだデータを基準としているため、人間の感情を理解することができません。
例えば生成AIに「悲しい顔をした女性」の画像を大量に読み込ませたとしましょう。この場合「悲しい顔」と「女性」というキーワードとあわせて数多くの表情を取り込み学習することから、悲しい顔をした女性の画像を抽出・生成することは可能です。
しかしあくまで取り込んだデータを基準としているため、悲しい顔の女性について認識・理解はできても、喜怒哀楽すべての感情の把握や表情の具体的背景などは読み取ることができません。
柔軟な判断
生成AIに柔軟な判断はできません。例えば人間でいう臨機応変に対応することや、倫理的な行動とは何かを理解し実践することなどです。臨機応変や倫理的な行動に関するデータを取り込むことで言葉の意味について理解することはできますが、これらを実行することには対応していません。
学習範囲外の生成
生成AIは学習範囲外の生成にも不向きです。大量のデータを取り込み、分析・判断・パターン化を得意とするAIの特徴が理由です。例えば、2024年までの出来事をデータとして取り込んだ場合、2025年以降の出来事に対する説明はできないなどです。
生成AIにおけるできないことをいくつか挙げましたが、視点を変えれば取り込むデータがジャンルを問わず多ければ多いほど学習機会が増え、精度は上がるといえます。生成AIには思考がないため、現状では自発的に考えることができません。しかし、必要とするデータを多く取り込み学習させることで、人間と無理なく共存できる存在になると考えられるでしょう。
生成AIのメリット
生成AIにはさまざまなメリットがありますが、ここでは代表的なメリットについて解説します。以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
関連記事:生成AIのメリット・デメリットとは?活用シーンや注意点を解説!
生産性向上
生成AIの活用によって生産性向上に期待できます。例えばこれまでは新しいアイデアを生み出すためにさまざまなデータを人間が収集し分析していたことも、生成AIに代替すれば迅速に進められたデータの収集・分析により、アイデアにまつわるヒントを得ることができます。
データ収集や分析に掛かる時間や労力を減らしながら新たな発想につなげられるため、特に経営戦略やマーケティング戦略を要する部署やクリエイティブ業界では生産性の向上が見込めるでしょう。
品質向上
大量のデータを取り込み生成AIに学習させることで、品質の高いデータ生成も可能です。使うツールによっては人間の技術や思考では辿り着かないようなリアルな画像を生成することもできます。
生成AIの活用によって品質向上はもちろん、クライアントに対する豊かな発想・視点によるアプローチも可能になるでしょう。
カスタマイズ向上
取り込んだデータをもとに新たなデータを生成する特徴を活かせば、目的に合わせてカスタマイズしたデータ生成も可能です。例えば、企業のイメージカラーやデザインを元に新たなロゴを作成したい場合です。このようなときは企業のイメージカラーや希望するデザイン画像などを生成AIに学習させることで、希望に近い画像を生成できます。
従来はロゴ作成にクリエイターやイラストレーターへ外注していたとしても、生成AIの活用によって社内で発案・検討・制作がすべて完結します。経費削減はもちろん、クリエイターへの情報提供の手間や、提供した情報漏洩の不安もなくなるなど、多方面でのメリットに期待できるでしょう。
クリエイティブ分野における新たな創造
生成AIが生成したデータは、取り込んだデータをもとに生成するため、どこかで見聞きしたことのあるデータも生まれやすいです。しかし、人間による工夫を加えることで、まったく新しいモノを生み出すことができる可能性も秘めています。
その結果、クリエイティブ分野で活躍する方1人ひとりの可能性が大きく広がる点もメリットといえるでしょう。
生成AIの活用シーン
生成AIは多くのシーンで活用できる特徴があります。代表的なものとしては以下6つです。
- プレゼン資料における企画作成
- メールなどの自動返信テンプレート作成
- 会議などの文字起こし・議事録作成
- 文章の要約
- ニーズ分析
- 翻訳
ここでは生成AIをどのように活用できるのか、その詳細について解説します。
関連記事:AIをビジネスで活用するには?活用する上での目的や事例、成功のコツを解説
プレゼン資料における企画作成
生成AIに目的やターゲットなど詳細な情報をデータとして学習させることで、その情報を捉えたデータを生成できます。そのため、会議や製品・サービスの提案には欠かせないプレゼン資料も生成AIに任せることができます。
ただし、提案書の生成にあたっては対象とするユーザー情報を細分化して盛り込んだペルソナを作り、データ化する必要があります。提案するユーザーの年代や製品・サービスの目的だけを盛り込んだデータでは、対象が抽象的過ぎてしまい、1人のターゲットに響く提案につながりません。
対象とするユーザーの年齢や抱えがちな悩み・課題などを盛り込んだペルソナを作り、その情報をデータ化し生成AIに学習させることで、具体性があり納得につなげやすい提案書を生成できます。
メールなどの自動返信テンプレート作成
生成AIにデータを学習させることでさまざまなシーンで応用可能です。その一例がメールなどの自動返信です。冒頭から文末までを手入力で済ませると数分掛かるメールなどの返信も、普段の返信内容をあらかじめ生成AIに学習させることで、定型文を生成することができます。
生成された定型文を普段のメールアプリなどに登録することで、返信における時間や労力を減らすことができます。また、どのように返信していいか迷う内容も、生成AIに読み込ませることで返信文の提案を受けることもできます。
ただし、生成AIの能力は完璧ではないため、生成された返信文や提案文の内容については、届いたメールとの齟齬や違和感がないかを確認してから送信しましょう。
会議などの文字起こし・議事録作成
会議の録音データも生成AIに読み込ませることで、文字起こしを経た議事録の生成が可能です。近年ではオンライン会議に参加させることでリアルタイムで文字起こしを行うAIツールもあります。重要な会議ほど録音データの取り扱いや議事録の作成に労力・時間を要します。生成AIを活用すれば、対面・非対面を問わずいつでも正確な記録を残せます。
文章の要約
Webサイトに掲載されたコラムやPDF化した資料の要約も可能です。論文作成などにおいては一次資料が必要になることも多く、内容を理解するまでに時間が掛かります。そのようなときも、生成AIに読み込ませることで、対象データにどのようなことが書かれているのかを分析できます。
論文作成をはじめ、Webサイトに掲載するコラムの作成、マーケティング資料の作成なども、あらゆる資料を使い生成AIに学習させることで、効率化を図りながら取り組むことができます。
ニーズ分析
アンケート結果を生成AIに分析させることで、企業に沿ったニーズ分析が実現します。対象とするデータは多ければ多いほど顧客の潜在ニーズを抽出することができるので、企業戦略の策定や商品開発につなげられます。
アンケート結果以外にも、サポートセンターに届いた苦情も生成AIに読み込ませれば、多角的な視点での企業の改善点が発見でき、サービスの改善にも役立ちます。このような方法を慣例化させれば、顧客満足度の向上につなげることもできるでしょう。
翻訳
グローバル化が進む企業では、多言語対応を要することもあるでしょう。例えば海外企業の担当者とメールやチャットでやり取りを行う機会があるときは、生成AIに届いたメール・チャットの内容を読み込ませることで翻訳できます。さらに必要に応じて、届いた内容に適した返信文を質問すれば文章の提案を受けることもできます。
多言語対応するためには、英語や中国語など先進国の言葉を筆頭に1から学ぶ必要がありますが、生成AIの活用によって、多くの国とのコミュニケーションがアップデートできるでしょう。
まとめ
AIの進化によって、近年ではさまざまなモノ・アイデアを生み出す生成AIの存在も注目されています。ITやWebエンジニアの業務に従事する人の9割が生成AIを活用していると回答したニュースもあることから、今後はさらに生成AIの活用が進み、進化を遂げると考えられます。
すでにさまざまな生成AIツールが展開されていますが、その多くはクラウド型であるため、使用にあたっては情報漏洩リスクを懸念する方もいるでしょう。そのようなときは、自社に適したAIツールを作成してみてはいかがでしょうか。
PeacefulMorning社が提供するRobo Runnerは、RPAやAI開発経験豊富なプロが、開発者育成を月額10万円からサポートするサービスです。オンラインサポートがあるので、わからない部分はプロと画面を共有しながら質問し、解決することができます。
開発におけるハウツーについてもプロに直接聞くことができるので、AI技術に精通した人材育成の幅を広げたいときにも有効です。
AIの進化によってさまざまな企業が積極的にDX化に向けて動いています。市場競争に乗り遅れないためにも、この機会にRobo Runnerで自社競争力向上を図りましょう。

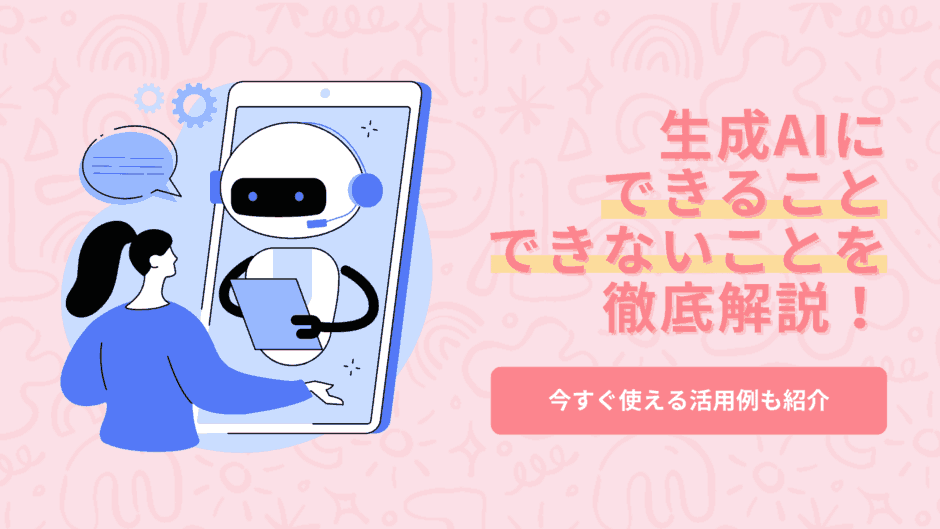



コメントを残す