バックオフィス業務は、企業の利益には直結しないためにシステム導入や改善が後回しにされやすい一方で、従業員が適切に取り組んでいなければ組織全体が機能しなくなるなど、重要な業務としても位置付けられます。
そのような背景があるなか、近年では世界各国のDX推進に伴いバックオフィス業務の効率化が注目を集めており、優先的に改善しようとする企業が増えています。
本記事ではさまざまな企業にならってバックオフィス業務の改善を図ろうとする担当者・責任者の方へ、バックオフィスの概要をはじめ、業務課題や効率化するメリット、方法などについて解説します。
バックオフィスとは
バックオフィスとは、営業やマーケティングといったフロントオフィスをサポートする役割を担う以下の部署・業務のことです。
- 一般事務
- 経理
- 財務
- 人事
- 総務
- 法務
- 労務
バックオフィスでは組織の後方から企業全体の活動を支えるために必要な手続きを行い、間接的に利益に貢献する立場に位置します。
バックオフィスにあたる業務の種類
バックオフィスにあたる業務には一般事務を含め、7つの部署に該当します。具体的な業務は下表の通りです。
|
部署・業務 |
概要 |
|
一般事務 |
・全従業員の業務をサポート ・データ入力・書類のファイリング ・来客・電話対応 ・郵便物・荷物などの仕分け・発送・受け取り ・他部門での書類作成・資料のまとめ |
|
経理 |
・企業経営にまつわる金銭の流れを管理する ・帳簿の記帳・管理、帳簿を基準とした財務諸表の作成 ・請求書・領収書などの発行・管理・手続きの対応 ・月次決算・年次決算の作業・管理 ・法人税を含む各税金および保険料などの計算・手続き |
|
財務 |
・経理部で作成した帳簿・財務諸表を基準に企業の資金繰りにまつわる業務を担う ・銀行融資における交渉・手続きをはじめ株式発行や資金調達 ・予算・資金の管理 ・余剰資金を使用した場合に必要となる新たな投資、事業売買の検討 ・財務戦略の企画立案 |
|
人事・労務 |
・企業における人材・働き方を管理 ・採用活動全般の総括・管理 ・従業員の労働時間・出退勤の管理 ・従業員の異動・転勤などを含む配置 ・従業員の評価・教育 |
|
総務 |
・企業全体に関する管理・その他の支援のうち、どの部門にも該当しない仕事を担う ・消耗品・資産関係の管理 ・機器・設備・オフィスの管理・業務補助 ・社内イベントの企画・主催 ・社内ルールの規定・改定・コンプライアンス関連の処理 |
|
法務 |
・法律にまつわる部分を担う ・契約書をはじめとした書類のリーガルチェック ・著作権・商標権をはじめとする知的財産権の管理 ・外部企業などによる訴訟・障害権侵害などに関する法的トラブルの対応 ・全社向けの法律に関する相談受付 |
このようにバックオフィスと一口にいってもさまざまな部署が該当し、それぞれで担当する業務が異なります。そのため、バックオフィス業務の改善を図るためには具体的な部署・業務について洗い出すことが大切です。
関連記事:経理業務の効率化方法5選|メリットや注意点、成功事例を徹底解説
関連記事:採用業務の効率化方法6選|採用時の課題や自動化に役立つツールを紹介
バックオフィス業務における課題
一般事務をはじめ、総務や人事・労務などを含むバックオフィス業務ですが、以下のような課題を抱えている場合が多いです。
業務のブラックボックス化
バックオフィス担当者を対象としたアンケートでは、約3割の担当者が「仕事の属人化」を自社課題または不満と回答したと報じています。業務の多くはマルチタスクでイレギュラーな対応も珍しくありません。そのため、どの業務にどの程度の時間を充てているのかについて周囲が把握しにくいブラックボックス化が起きています。
また、取引先やその担当者によって対応すべきルールが異なるケースも多く、業務に従事する場合、経験や熟年の勘が求められることがあります。その結果、ブラックボックス化しやすい業務であると考えられ、改善に向けた取り組みが求められています。
参考:約3割のバックオフィス業務担当者が業務のアウトソーシングサービスを利用していると回答!
定型化した業務によるモチベーションの低下
バックオフィス業務はフロントオフィス業務とは違い定型化されている業務が多いです。そのため、忙しいのにやりがいが持てないといった状態を招きやすく、モチベーションを維持することが難しい業務でもあります。
また、数字を使うことの多い業務でもあるため、少しのミスも許されず、神経疲れする従業員も少なくありません。
やり取りや承認が伴う作業が多い
書類を用いた手続き・管理が多い特徴から、やり取りや承認を要することも多いです。特に組織の中枢を担う部署に位置する経理部や法務部では、意思決定にいくつかのステップを踏む場合が多いです。リマインドや進捗確認といった細かなやり取りに時間が割かれ、結果、本来の業務がストップするといったことも珍しくありません。
コミュニケーションコストに時間や労力が割かれてしまうと、従業員のモチベーションや集中力の低下を招き、生産性が落ちることもあります。
ミスが生じやすい
人の作業にはヒューマンエラーがつきものです。どれだけ注意していてもミスは起きるものですが、バックオフィスでのミスは大きな損失に発展しかねません。決算期や新人採用、給与計算ごろになれば、忙しい分だけミスも生じやすいです。
「ミスがあってはならない」「忙しすぎてミスが増えている」といった状況が、従業員のプレッシャーになると、さらにミスを生み、大きなトラブルにつながる可能性もあります。
デジタル化が停滞しやすい
バックオフィス業務のデジタル化が停滞しやすい点も課題のひとつです。バックオフィス業務で使用しているシステムが古くから使用しているものだった場合、デジタル化に踏み切れないことがあります。
既存システムがブラックボックス化している場合は、新システム導入の前にシステムの課題解決を優先しなければなりません。課題をみつけ、その上で対処していく流れに対して複雑さや面倒さを感じ、後回しにされてしまうためです。
DXの推進に向けて、経済産業省は外部パートナーとの連携を推奨しています。既存システムのブラックボックス化などさまざまな理由によってデジタル化が停滞していると感じるときは、外部パートナーを使用し、適切な対処を取り入れながらDX推進を図ると安心です。
参考:経済産業省|デジタル トランスフォーメーション DX銘柄2024
バックオフィス業務を効率化するメリット
ITツールなどの利用を通じてバックオフィス業務を効率化することには、下記のようなメリットがあります。
業務プロセス・フローの見直しにつながる
バックオフィス業務の効率化によって業務プロセスやフローの見直しにつながります。従来では気付けなかった業務・作業を把握できるので、属人化していた業務まで把握することができるので、業務の標準化も実現します。
ITツールを導入し効率化を図る場合、全社に広がる業務や作業を1つひとつ洗い出す必要があります。プロセスやフローを見直し、不要・非効率とする部分を省きながら効率化を図れるため、古くから使われていた業務体制を新たに構築できるのはメリットといえるでしょう。
生産性の向上が期待できる
手作業を中心とするバックオフィス業務を効率化することで生産性の向上に期待できます。RPAツールをはじめとしたツールに定型化・反復化した作業を任せられれば、マネジメントや管理体制強化といった、人力でなければ対応できない業務に人的リソースや時間的リソースを充てられます。
労働負担の軽減につながる
ITツールなどを使用し効率化を図ることで従業員の労働負担も軽減されます。データ入力や給与計算といった数字を頻繁に使う作業が多いバックオフィス業務では、集中力が求められ、精神的負担を感じやすい側面があります。
このような作業にはRPAツールを使用することで、人間の何倍もの速度で正確に入力作業が進み、従業員の労働負担を減らしながら生産性の向上にもつながります。
人為的ミスの削減が期待できる
データの入力・集計・照合といった業務が中心のバックオフィス業務は、数字の入力ミスや計算ミスなどさまざまなミスが生じやすい業務でもあります。しかし、不要・非効率な作業を省くなどの工夫によって、人為的ミスの削減にもつながります。
データ管理が容易になる
バックオフィス業務の効率化によってデータ管理が容易に行える点もメリットのひとつです。例えばクラウドベースのシステムを導入した場合、業務に使用するデータの管理がスムーズにでき、リアルタイムでの共有・アクセス・編集が可能になります。
紙媒体で資料を管理していた場合も、データ化することで部署間での共有が素早く行えるので、コミュニケーションや資材コストの削減にも期待できます。
バックオフィス業務を効率化する方法
さまざまな方法を用いることで意外にもスムーズに進めやすいバックオフィス業務の効率化ですが、具体的にどのような方法があるのでしょうか。ここではいくつかピックアップして解説します。
外部パートナーを活用する
バックオフィス業務の効率化には、外部パートナーの活用が有効です。誰でも対応できる定型的な作業は外部に委託することで、社内メンバーが本来注力すべき業務に時間を割けるようになります。
電話・メール対応やデータ入力など、反復的な業務が多い場合は外部委託を検討してみましょう。
クラウドソーシングを活用する
外部パートナーに頼るのではなく自社で業務を遂行したいときは、クラウドソーシングを活用する方法も有効です。請求書や発注書の発行、勤怠管理や帳票管理などは、クラウドソーシングでもデジタル化できます。外部パートナーへの依頼費用が気になるときは、クラウドソーシングも検討してみるとよいでしょう。
なお、弊社のグループ会社であるCrowdWorks Agentでは、670万人以上の登録データベースから、最適なフリーランス人材を最短3日でご提案します。人材のご提案から契約・参画後のフォローまで一気通貫でサポートするため、即戦力人材の活用に、お役立てください。
社内用チャットボットを導入する
社内の問い合わせ業務に時間が割かれているのであれば、社内用チャットボットを導入する方法もあります。問い合わせ対応に時間を割かずに済むため、本来の業務に集中することができ、生産性の向上やモチベーションの維持につながるでしょう。
業務マニュアルを作成・共有する
各部署からの問い合わせ対応に時間を取られるのであれば、業務マニュアルを作成し、全社に共有する方法もおすすめです。マニュアルを共有することで従業員自らで問題を解決できるので、問い合わせ対応が減少するだけでなく、調べてもわからない問題のみバックオフィスに問い合わせるといった環境を構築でき、バックオフィスの業務の効率化につながります。
RPAツールを活用する
定型・反復的な業務にRPAツールを導入すると、業務の効率化を実現できます。代替したい業務プロセスやフローをロボットに設定することで、設定したプログラム通りに作業が進みます。モチベーションや体調に左右されることがないため、正確かつ一定の品質を維持しながら生産性を上げることができます。
関連記事:RPAとは?わかりやすく仕組みや期待できる効果を事例とともに解説
ペーパーレス化を図る
請求書や発注書、契約書や会議資料などはPDFでの管理に切り替え、ペーパーレス化を図るのも効果的です。紙ベースからデータベースに変えることで、各部署との資料共有や編集も容易に行えます。ほしい資料を素早く開き確認できるため、業務の効率化を目指したい企業には特におすすめです。
バックオフィス業務を効率化する3つの手順
バックオフィス業務を効率化する場合は、これから解説する3つの手順に沿って実践してみましょう。
業務の可視化と課題の分析をする
バックオフィス業務を効率化するには、まず業務の可視化と課題の分析からはじめましょう。課題を特定することで、優先順位をつけながら解決に結びつけることができます。
課題解決につなげるためのツール選定にも有効なので、まずは業務の可視化・課題分析から取り組んでみましょう。
課題解決に導くツールや施策を検討する
バックオフィス業務の可視化によって特定された課題に優先順位をつけたら、次に課題解決に導くツールや施策について検討しましょう。業務の効率化につながるツールやシステムはさまざまなものが展開されていますが、自社課題を必ずしも解決できるとは限りません。
課題を洗い出し、不要・非効率と判断した業務フローは省く、データ入力にはショートカットキーを活用する、便利なショートカットキーであれば全社に共有するといった施策でも解決できる場合があるので試してみましょう。
関連記事:【シーン別】事務職の小さな改善事例|手順やポイント、注意点も解説
実際の業務に反映しモニタリングする
業務の効率化に向けてツールや施策を実施した後は、モニタリングを行い効果測定を実施しましょう。ツールや施策を実施する前に業務に掛かる時間を計測しておくと、導入前後でどの程度の効果があったのかを測定することができます。
まとめ
バックオフィス業務は、企業の後方支援を担い、従業員を支える重要な役割を果たしています。事務処理など定型的・反復的な作業が多い上、社内外からの問い合わせ対応も求められるため、集中力やモチベーションを保ちながら本来の業務を遂行するのが難しい場面も少なくありません。
こうした業務に対する従業員の不満や負担感を軽減したい場合は、本記事で紹介した業務効率化の方法をぜひ参考にしてください。
また、社内人材の育成によって効率化を検討されている方は、Peaceful Morningが提供する「Robo Runner」がおすすめです。AIやRPAをはじめとした効率化ツールの導入から開発、組織への定着まで一気通貫でご支援します。
ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。

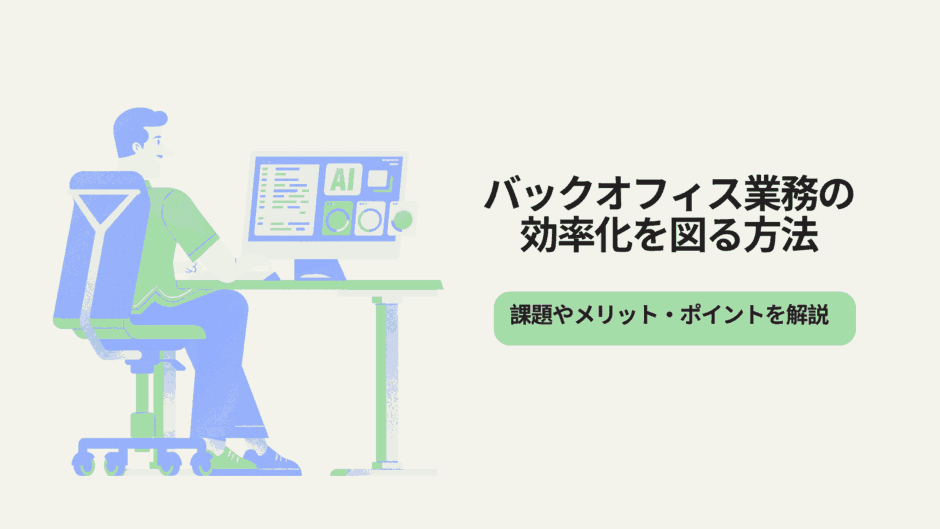



コメントを残す