AI技術の進化によって誕生した生成AIでは、さまざまなデータを抽出できる特徴から、今では多くのシーンで活用されています。ビジネスシーンも例外ではなく、例えばAIチャットボットを導入し社内外の問い合わせ業務を自動化するなど、活用が広まっています。
AIチャットボットを用いた問い合わせ業務の自動化は、従業員の対応時間を削減し、本来の業務に集中できる環境を整えるための施策として注目されています。本記事ではこのような事例を含め、効率化できる業務の一例や取り組み方、有効なツールについて解説します。
生成AIで効率化できる業務例
生成AIで効率化できる業務は、大きく分けて以下の7つあります。
- 文書の自動生成
- 問い合わせ業務の自動化
- スケジュール管理
- クリエイティブ関連の制作
- プログラミング
- プロジェクトの管理
- 市場などの調査・分析
ここでは、さまざまな生成AIツールを紹介しながら業務でどのように使うことができるかについて解説します。
関連記事:AIによる業務効率化とは?おすすめのツールや選び方を徹底解説!
文書の自動生成
生成AIにできることとして文書の自動生成があります。この特徴を応用すると、ビジネスシーンのなかでも取引先とのメール・チャット文章や自社メディア用コラム、SNS投稿文などで業務の効率化を実現できます。使い方は、OpenAIの「ChatGPT」などに作成してほしい文書に関する指示文(プロンプト)を提示するだけです。
生成AIに伝わるようなプロンプトを心がけることで、理想的な文書データが抽出できるほか、比較的毎日行う業務であれば作業にかける時間も短縮できます。文書の自動生成は生成AIのメイン機能といっても過言ではないため、費用を抑えたいときは先述した生成AIを使うとよいでしょう。
問い合わせ業務の自動化
AIチャットボットの活用によって問い合わせ業務の自動化も可能です。生成AIとは回答する仕組みに違いがあり、生成AIはさまざまな質問に対応できる一方、AIチャットボットは事前に登録した回答を提示できる特徴を持ちます。
自社から問い合わせの多い質問と適切な回答をあらかじめ登録しておけば、類似する質問にAIが自動で対応してくれるため、業務の効率化を図ることができます。本来の業務の手を止める機会を減らすことができるので、集中力やモチベーション、生産性を維持することにもつながります。
なお、AIチャットボットは社内システムに導入するものが多いため、ある程度の費用が掛かることは念頭に置きましょう。
スケジュール管理
生成AIツールのなかには、AIが自動でユーザーのタスクを分類し、優先順位を自動で設定しながらスケジュール管理をしてくれるツールもあります。「Googleカレンダー」をはじめとしたカレンダーアプリと連携できるツールを選べば、スケジュールを自身で管理する時間を省略できます。「DolaAI」や「Backlog」などがあるので、気になる方は詳細を確認してみるとよいでしょう。
クリエイティブ関連の制作
画像や動画など、クリエイティブな制作も生成AIに任せることができます。最近ではGoogleの「Gemini」でも、無料で画像作成が行えるようになっています。抽出した画像や動画を示すプロンプトを提示することで、画像編集、動画編集のスキルがなくても簡単に作成できます。
製品・サービスに関するキャラクターやロゴなどのデザインが決まらず時間だけが過ぎていくといったときは、生成AIに相談することで理想に近いデザインができ、業務効率化を後押ししてくれるかもしれません。
プログラミング
生成AIを活用することで、プログラミングコードの自動生成やバグの検出、リファクタリングなどの作業を効率化できます。プロンプトに記載された要件に基づいたデータを収集する特徴から、プログラミングに慣れている方であれば、アプリケーションの開発・修正などの業務を効率化できるでしょう。
プロジェクトの管理
プロジェクトにおける計画立案や進捗管理、リソースの最適化といった細かな業務も、生成AIを使い効率化できます。生成AIの多くは、無料・有料を問わずユーザーが提示した資料の分析・要約・必要箇所の抽出にも対応しています。例えば時間の掛かる計画立案に生成AIを活用すれば大幅な時間削減につながります。
進捗管理やリソースの最適化も生成AIに任せられるため、使い慣れたころに一連の流れを生成AIに任せてみるとよいでしょう。
市場などの調査・分析
ユーザーが提示した資料の分析にも対応していることから、マーケティング分野に欠かせない市場分析にも活用できます。膨大なデータを取り扱う必要性から人間の能力では限界がありますが、生成AIの活用によって素早く精度の高い市場調査および分析が実現できます。
インターネット上で公開された調査票や報告書などもデータ収集や分析に使用していることから、使用したいデータによっては政府が発行した資料を交えた情報も抽出可能です。
生成AIを活用して業務の効率化を図る手順
生成AIを活用して業務の効率化を図る場合は下記の手順を意識してみましょう。なお、手順については文書の作成を軸に解説します。
改善したい業務を洗い出す
まずは自身の日常業務のなかでも改善したい業務の洗い出しからはじめましょう。生成AIにできることは、以下の通りです。
- テキストの生成
- 画像・動画生成
- 音声生成
- ソースコード生成
- データの要約・翻訳
上記の項目と自身が改善したい業務が対応可能であるかを確認しておくと作業をスムーズに進められます。生成AIにできること・できないことについては以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介
細かな目標値を設定する
次に生成AIを使ってどのようなゴールを達成したいのか目標値を設定しましょう。スタートラインとゴールを目標値にするのではなく、中間目標を設定するとどの程度改善しているのかが判断しやすくなります。例えば生成AIを使い自社ホームページに掲載するコラム記事を生成し、CV数を20%増加したい場合は以下のような目標値を設定しましょう。
- 文章作成時間を従来の30%削減する
- 抽出されたデータの修正およびファクトチェックも合わせて従来の作業時間から50%削減する
- 生成AI使用前よりも自社ホームページのCV数が20%増加している
普段の業務時間と自社ホームページの通常のCV数を洗い出しておくと効果測定の際にどの程度効果が出ているのか判断しやすくなります。
適切なツールを選定
改善したい業務と目標値を設定した後は、次にツール選定を実施します。コストを掛けたくないのであれば無料で使用できる「ChatGPT」や「Gemini」を、文章の編集・添削業務を効率化したいのであれば「SAKBUN」や「Grammarly」などを利用するとよいでしょう。
また、日常的にMicrosoft Officeソフトを使用しているのであれば「Copilot」が内蔵されているので使用感を試してみるのもおすすめです。
テスト導入する
改善したい業務に対して適切なツールが選定できたら、次は実際に使い、使用感について調べてみましょう。簡単なキーワードを使い、どのような文書データが抽出されるのかを把握することで、自身の業務内容に対応できるかを判断することができます。
また、容易な操作感であればあるほど業務の効率化につながるので、操作手順やわかりやすさを含めたデザイン設計などもチェックしてみましょう。
資料やデータを準備する
使用感に問題がなさそうであれば、生成AIに抽出してほしい内容に関する資料・データを準備しましょう。インターネット上で調べられる情報であれば、適切なキーワードを盛り込んだプロンプトを作成します。マーケティング部門などで活用するのであれば、自社の経営データや市場分析に使用したデータを用意しておくと作業がスムーズに進みます。
トレーニングを実施する
次に生成AIのトレーニングを実施します。トレーニングでは生成AIのパフォーマンスについて確認し、必要に応じてチューニングを行います。トレーニングやチューニングは、生成AIから抽出したデータに違和感や不足項目があった際に、あらかじめ用意した資料・データを読み込ませ、抽出データの精度を高める目的があります。
データの精度はプロンプトの内容で改善されるケースも多いですが、インターネット上で検索しても閲覧できないデータについてはユーザー側で読み込ませる必要があります。抽出した文書データに必要情報が抜けているときは、データの精度を高めるため、トレーニングやチューニングを実施し改善を図りましょう。
テストの実施・評価
トレーニングやチューニングを実施した後は、使用感や効果を検証するためのテストを行い、改善点を特定しましょう。自社ホームページに使用することを前提とした文章を生成し、従来の業務プロセスと比較します。作業フローや時間が短縮されていなければ、チューニングを通して改善を図りましょう。
マニュアルを作成・共有する
業務でも使用できるよう生成AIの調整が終わった後は、実際の業務で使用できるようマニュアルを作成し、必要に応じて他従業員に共有します。自社コンテンツ部などチームや部署全体で使用するのであれば、マニュアルを作成・共有することで作業の均質化を図ることができます。
本格的に導入し、効果測定と改善を繰り返す
生成AIの選定やトレーニング・チューニングやマニュアルの作成などが一通り終わったら、本格的に導入し、業務に活用していきましょう。業務プロセスやフローなどに変更があれば、必要に応じて生成AIにも変更を加えるためのチューニングを実施し調整します。
1~3か月ほど使用した後は効果測定を行い、当初定めていた目標値を達成しているかを分析します。目標の達成・未達成にかかわらず、効果測定は定期的に行い、必要に応じて改善を図りながらPDCAサイクルを回すことをおすすめします。生成AIの運用における改善点を特定するためには、実際に使用している従業員からフィードバックを集めることが効果的です。
生成AIを活用した企業の成功事例
ここからは、生成AIを活用した企業5つの成功事例について解説します。
パナソニック コネクト株式会社
パナソニックコネクト株式会社では、生成AIによる従業員のAIスキルや生産性の向上を目的に、OpenAIの「ChatGPT」をもとにした自社向けAIアシスタントサービス「ConnnectAI」を開発・活用しています。AIアシスタントを他従業員に聞くほどではない質問や戦略立案に活用する従業員が増えたことで、わずか1年間で18.6万時間の労働時間を削減しました。
参考:パナソニックホールディングス株式会社|パナソニックコネクト 生成AI導入1年の実績と今後の活用構想 | 技術・研究開発
株式会社ベネッセホールディングス
株式会社ベネッセホールディングスでは、自由研究のテーマ決めを手助けする目的から、小学生の親子を対象にChatGPTを用いたプロダクトを提供しています。リリース前後にはいくつかの課題を乗り越える必要がありましたが、実際に使用した多くの親子からは自由研究に役立ったという評価を受けました。
参考:株式会社ベネッセホールディングス|生成AIの活用事例のご紹介
株式会社パルコ
株式会社パルコでは、人物・背景・映像・音楽・ナレーションまでをすべて画像生成AIで創りあげたファッション広告を発表しました。またたく間に多くの注目を集め、デジタルメディア協会が主催、総務省が後援する「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’23」にて年間コンテンツ賞の優秀賞を受賞しました。
参考:株式会社パルコ|「HAPPY HOLIDAYS広告」が、AMDアワードで「優秀賞」を受賞 | パルコグループブログ
株式会社メルカリ
株式会社メルカリでは、フリマアプリの利用にあたって、商品の出品・購入や問題解決といった幅広いサポートを目的に、生成AIをはじめとしたAIアシスタント機能の提供をスタートしました。なかでも注目を集めたのが、一定期間売れ残っている出品商品をユーザーの目に届きやすく購入してもらいやすくなるようAIアシスタントから改善案が届く仕組みです。
メルカリAIアシスタントは優秀かつ頼もしい機能でしたが残念ながら2024年8月に終了し、現在は出品をサポートするAIがリリースされ、多くのユーザーが利用しています。
参考:株式会社メルカリ|メルカリ生成AI/LLM 専任チームの取り組み [2023.12]
参考:株式会社メルカリ|メルカリAIアシスト – メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ
参考:株式会社メルカリ|メルカリ、「AI出品サポート」の提供を開始。出品体験をさらに簡単にアップデート
株式会社七十七銀行
株式会社七十七銀行では、DX推進をはじめ銀行業務の効率化・高度化を目的に2025年3月から業務に生成AIを活用しています。文書作成・情報収集・データ集計といった日常業務に生成AIを使用し、本部の55以上の業務で年間約32,000時間の効率化が期待されています。
参考:株式会社七十七銀行|News Release 2024年11月8日 生成AIを活用した生産性向上の取組みについて もっと、ずっと、地域と
生成AIを導入する際のポイント
生成AIを導入する上では、下記のポイントを押さえておくことをおすすめします。
関連記事:生成AIを導入するには?手順やできること、おすすめツールやメリットを解説
業務課題は必ず洗い出す
生成AIの使用を通じて業務の効率化を図るためには、業務課題は必ず洗い出すことを意識しましょう。業務プロセスやフローを細かく分析し、不要や非効率を感じる部分を特定することで、適切な生成AIが選定しやすくなります。日常業務のなかでも「この作業はなくても正常に機能する」といったフローがあれば、業務課題としてメモを取っておきましょう。
業務課題に優先順位を付ける
業務の課題を洗い出した後は、どの課題から改善すべきか優先順位を付けましょう。改善点が多いほど1度に取り組みたくなりますが、1つひとつクリアしていくことで選んだ生成AIが適切なものであるかが判断できることに加えて、チーム・部署での混乱を最小限に抑えることができます。
社内整備を実施する
生成AIを導入するのであれば、あらかじめ社内整備を実施することも大切です。社内あるいはチーム・部署で活用することを決めていても、どのような手順で行われ、どのような業務に使用できるのかについて共有していないと、業務の効率化につなげられません。
デジタル技術に苦手意識を抱く従業員も一定数いることを考慮し、社内研修やマニュアルの作成・共有、各種問い合わせに対応できるチームの設置などを行いながら、導入における社内の混乱を最小限に抑えましょう。
他ツールの使用も視野に入れる
生成AIツールは種類が多く、特徴が大きく異なります。業務の効率化を図る上では、従事する業務に最適な生成AIツールであるかを常に考えながら使用しましょう。生成AIツールによっては、アップデートや有料プランへの登録によって機能やメリットが増えるケースも多いです。
1度選んだ生成AIツールが自社にとっての最適解と決めるのではなく、定期的に他ツールの特徴や機能をチェックし、現状の業務にとって最適なツール選びにつなげましょう。
まとめ
日常業務と生成AIの特徴がマッチしていれば、使い方次第で大幅に効率化させることができます。しかし、生成AIツールの種類は多岐に渡り、どれを選べばよいのか判断に迷う方もいるでしょう。そのようなときは、本記事で解説した業務例を参考にしながら、どの程度効率的に進むのか試してみることをおすすめします。
「自社に本当に合うツールがどれか分からない」と迷う場面もあるかもしれません。そのようなときは、AIやデジタル技術に精通したプロに相談してみるのも有効です。Peaceful Morningでは、RPAやAI開発経験の多いプロに最適なツール選びやツール導入後の使い方などをパソコンの画面共有を通じて相談できる「RoboRunner」を提供しています。
また、業務改善などを目的としたDX推進部門の設置にあたって社内リソースの確保が難しいときは、専任のエージェントが貴社に最適なDX人材を最短即日でご提案する「DX Boost」も提供しています。
いずれも貴社の改善点を解決へと導くサービスです。生成AIをはじめ、業務の効率化や改善、ツールの使用方法などについてお悩みの企業担当者様は、この機会にお気軽にご相談ください。



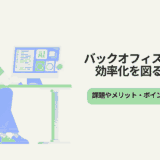

コメントを残す