業務効率を向上させたいものの、どこから手をつけるべきか分からないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。無計画に改善を試みても、根本的な課題を解決できず、効果が得られないケースも少なくありません。
本記事では、業務改善が必要な状況や、業務効率化に役立つフレームワーク12選、さらには実践方法について解説します。業務の生産性向上を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
業務効率化の改善・フレームワークとは?
業務改善とは、企業や組織が抱える課題を解決し、業務の流れを最適化する取り組みです。不要な作業を削減し、資源を有効活用することで、業務のムリ・ムダ・ムラを排除します。
業務の効率化を進めるには、まず現状の課題を明確にし、適切な改善策を講じることが重要です。しかし、どこから手をつけるべきか分からない場合も多いため、フレームワークを活用すると効果的でしょう。フレームワークを使うことで、課題の整理・抽出が容易になり、業務の改善点を具体的に把握できます。
また、業務の効率化は、単にコスト削減を目的とするだけではなく、企業の競争力を高め、持続的な成長を促す手段のひとつです。適切なフレームワークを活用し、業務の生産性を向上させることが求められます。
業務効率化の改善が必要な状況
業務効率化の改善が必要な状況はさまざまですが、ここでは主な3つの状況について解説します。
任されている業務が多すぎる場合
業務量が過剰になると、従業員の負担が大きくなり、生産性の低下やミスの発生につながります。また、常に業務に追われる状態が続くと、従業員の疲労が蓄積し、精神的な負担も増加します。これにより、ミスの発生率が上がるだけでなく、職場の雰囲気やチームの連携にも悪影響を及ぼすかもしれません。
無駄な業務が多い場合
業務の中には、実際には必要性が低く、時間を浪費している作業が含まれていることがあります。たとえば、決裁のために紙の資料を用意し、上司に回覧して押印をもらう必要がある場合、不在時には業務が滞ることになります。
また、会議の際に資料を人数分印刷し、机の上に並べることが習慣になっている場合も、作業の負担が増えていると言えるでしょう。これらの業務は、本来の目的達成に必要不可欠ではないものの、慣習として続いていることが多いです。
業務や作業時間にバラツキがある場合
同じ業務でも、担当者や状況によって作業時間や品質に差が出ることがあります。検品作業において、ベテランの担当者は短時間で正確に作業を終えられる一方で、経験の浅い担当者は時間がかかり、ミスの発生率も高くなるかもしれません。
また、時期によって業務量や対応スピードが変わる場合も、バラツキの一因となります。繁忙期には作業が遅れやすく、閑散期には業務量が減るため、一定の作業ペースを維持することが難しくなるでしょう。
業務効率化を実現するフレームワーク12選
業務効率化を実現するフレームワークを12個紹介します。
- ECRS
- BPMN
- KPT
- ロジックツリー
- バリューチェーン分析
- PDCAサイクル
- 5W2H
- QCD
- 4象限マトリクス
- フィッシュボーンチャート(特性要因図)
- マンダラート
- シックスシグマ
それぞれの特徴を理解した上で、自社に最適なものを選び実行してみましょう。
ECRS
ECRSは、業務改善を効率よく進めるためのフレームワークです。Eliminate(排除)、Combine(統合)、Rearrange(再配置)、Simplify(簡素化)の4つの視点で業務を見直し、業務の最適化を図ります。
最初にムダな業務や不要なルールを排除し(Eliminate)、類似する業務を統合(Combine)することで作業の効率化を進めます。その後、業務の流れを整理し(Rearrange)、より単純で分かりやすい形に整える(Simplify)ことで、業務の生産性を向上させるのが特徴です。
関連記事:ECRSとは?業務改善に不可欠なフレームワークを解説します
BPMN
BPMN(Business Process Modeling Notation)は、業務プロセスの可視化を目的としたフレームワークです。業務の流れをフローチャート形式で整理することで、プロセスの課題を発見しやすくなります。
例えば、業務の手順が複雑化している場合でも、BPMNを活用することで、誰がどの工程を担当しているのかを明確にできるでしょう。また、業務のボトルネックを特定し、改善策を検討する際にも役立ちます。業務の流れを見直し、ムダを削減するだけでなく、新たなシステム導入の判断材料にもなるため、幅広い業界で活用されています。
KPT
KPTは、業務の振り返りを行うためのフレームワークです。Keep(継続すること)、Problem(課題)、Try(挑戦すること)の3つの視点から、業務の改善点を整理できます。
もともとシステム開発の分野で用いられていましたが、短いスパンで業務を振り返り、改善を繰り返せるため、さまざまな業務に応用されています。特に、継続すべき良い点を明確にしながら、課題を洗い出し、次の改善策を立てる流れが特徴です。
ロジックツリー
ロジックツリーは、課題を樹形図状に細分化し、分析するためのフレームワークです。「なぜ?」を繰り返し掘り下げることで、課題の本質を明らかにできます。
例えば、「売上が低迷している」という課題を設定した場合、「顧客数が減っている」「単価が下がっている」などの要因に分類し、それぞれの根本原因を探ることが可能です。このように、複雑な問題を整理しながら、解決策を見つけやすくするのが特徴です。
関連記事:【5分で掴める】業務改善や問題解決に活かせる思考方法、ロジックツリーとは?
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、製品やサービスが生産・販売される過程で、どのように付加価値を生み出しているかを分析するフレームワークです。この付加価値とは、企業独自の強みや競争優位性を生み出す要素を指します。
バリューチェーンは「主活動」と「支援活動」に分かれ、主活動は生産・物流・販売など、直接的に価値を生むプロセス、支援活動は技術開発や人事など、間接的に価値を支える要素です。これらを細かく分析することで、競争力を高めるための改善点を見つけられます。製品やサービスの価値を向上させるために、バリューチェーン分析を活用することが有効でしょう。
PDCAサイクル
PDCAサイクルは、Plan(計画) Do(実行) Check(評価) Action(改善)の流れを繰り返し、継続的に業務改善を進めるフレームワークです。計画を立てた後に実行し、その結果を評価することで、問題点を洗い出せます。
さらに、評価を基に改善策を実施し、次のサイクルにつなげることで、業務の精度を高められるでしょう。PDCAは業務プロセスを最適化し、同じミスを繰り返さないための手法として、幅広い業界で活用されています。継続的な改善が求められる業務において、有効な手段のひとつつです。
5W2H
5W2Hは、業務のタスク管理や計画を効率よく整理するためのフレームワークです。以下の7つの視点から、業務の詳細を明確にできます。
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(誰が)
- What(何を)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
- How Much / How Many(いくら・いくつ)
業務の効率化を図るうえで、5W2Hを用いることで、課題を分かりやすく整理し、スムーズな業務進行を実現できます。
QCD
QCDとは、Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の3要素を重視し、業務の生産性を向上させるフレームワークです。もともとは製造業の生産管理に活用されていましたが、現在では多くの業界で導入されています。
- Quality(品質):高品質な製品・サービスを提供することで、顧客満足度を向上させ、企業の信頼を高める要素。品質管理を徹底することで、競争力のある製品を生み出せます。
- Cost(コスト):無駄な支出を抑え、利益を最大化するために、適切なコスト管理が求められます。ただし、過度なコスト削減は品質の低下につながる可能性があるため、バランスが重要です。
- Delivery(納期):顧客に製品やサービスを適切なタイミングで提供することが求められます。納期を守ることで、顧客の信頼を維持し、ビジネスの継続性を確保できます。
QCDを適切に管理することで、業務の効率化だけでなく、企業の競争力強化にもつながるでしょう。
関連記事:QCDとは?優先順位の付け方や派生語のフレームワークも紹介
4象限マトリクス
4象限マトリクスは、タスクの優先順位を整理するためのフレームワークです。「重要度」と「緊急度」の2軸で業務を分類し、どのタスクから取り組むべきかを明確にします。
4象限マトリクスでは、タスクを以下の4つのカテゴリに分類します。
- 緊急&重要:すぐに対応すべき最優先の業務
- 緊急ではないが重要:計画的に取り組むべき業務
- 重要ではないが緊急:他者に委任できる業務
- 緊急でも重要でもない:優先度が低く、削減できる業務
業務の取捨選択を行い、優先順位を明確にすることで、限られた時間の中で効率よく業務を進められるでしょう。
フィッシュボーンチャート(特性要因図)
フィッシュボーンチャートは、結果(特性)が発生した要因を整理するためのフレームワークです。魚の骨のような形をしていることから、フィッシュボーンチャートと呼ばれています。フィッシュボーンチャートでは、問題の原因を分類し、視覚的に整理することで、根本的な課題を特定しやすくなり、代表的な分類として以下の「4M」があります。
- Man(人):人的要因(スキル不足・人員配置の問題など)
- Machine(機械):設備やツールの影響(故障・老朽化など)
- Method(方法):作業プロセスの問題(マニュアルの不備・手順ミスなど)
- Material(材料):資材や情報の品質(不良品・データ不足など)
業務のボトルネックを特定し、具体的な改善策を検討する際に役立つフレームワークです。
マンダラート
マンダラートは大谷翔平選手が学生時代に活用していたことで有名ですが、アイデアを整理し、思考を深めるためのフレームワークとなります。中心のキーワードを基に関連する項目を放射状に展開し、思考の幅を広げます。基本的なマンダラートの構成は、3×3の9マスを使います。
- 中央のマスにテーマやキーワードを記入
- 周囲の8マスに関連する要素を記入
- さらに、周囲の8マスを中心にした新しい9マスを作成し、アイデアを深掘り
この方法を繰り返すことで、合計81マスのアイデアが広がり、思考の整理や新しい発想を生み出しやすくなります。ビジネス戦略や目標設定にも活用できるフレームワークです。
シックスシグマ
シックスシグマは、業務の品質を向上させ、エラーを最小限に抑えるためのフレームワークです。特に「DMAIC」と呼ばれる5つのステップを繰り返すことで、業務の改善を継続的に進められます。
- Define(定義):顧客満足に直結する課題を特定
- Measure(測定):データを収集し、現状を数値化
- Analyze(分析):課題の原因を分析し、影響を評価
- Improve(改善):具体的な改善策を策定し、実施
- Control(管理):改善策の効果を検証し、継続的に管理
シックスシグマは、業務の精度向上が求められる製造業や、品質管理が重要な業界で多く活用されています。プロセスを可視化しながら改善を繰り返すことで、業務の安定化を図ることができるでしょう。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
業務効率化を実現する6ステップ
業務効率化を実現するには、以下の6つのステップを踏みましょう。
- ステップ1:現状の業務の流れを把握する
- ステップ2:課題や改善点を全て洗い出す
- ステップ3:課題の根源を突き止める
- ステップ4:解決策を探る
- ステップ5:実行・測定・効果を測定する
- ステップ6:測定した結果をもとに継続や修正を繰り返す
それぞれ解説します。
ステップ1:現状の業務の流れを把握する
業務効率化を進めるには、まず現在の業務の流れを正確に把握することが重要です。業務の全体像が分からなければ、どこに問題があるのか判断できません。そのため、業務プロセスを細かく分解し、どのような手順で作業が進んでいるのかを可視化しましょう。
フローチャートや業務マニュアルを活用すると、業務の流れを整理しやすくなります。また、業務を担当する社員からヒアリングを行うことで、実際の業務の流れと課題を正確に把握できるでしょう。
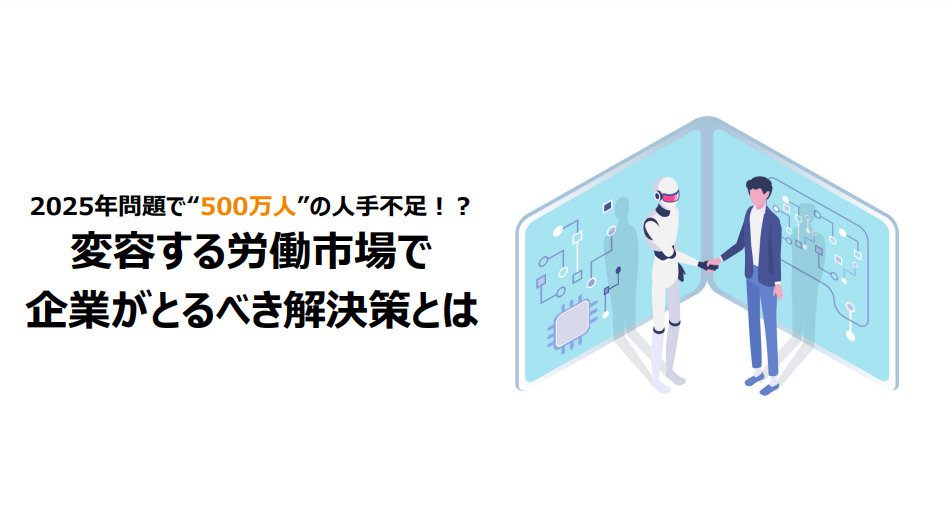
\ 業務可視化の方法を解説 /
ステップ2:課題や改善点を全て洗い出す
業務の流れを整理したら、次に課題や改善点を明確にする必要があります。現場で実際に業務を行っている社員の意見を聞くことで、見えにくい問題点を発見しやすくなります。
たとえば「作業に時間がかかる」「確認作業が多くミスが減らない」といった問題があるかもしれません。課題をリストアップする際は、「時間がかかる」「コストが高い」「手順が複雑」といった観点で分類すると、優先的に解決すべきポイントが分かりやすくなるでしょう。
ステップ3:課題の根源を突き止める
洗い出した課題に対して、その原因を特定することが求められます。単に「業務に時間がかかる」といった表面的な課題ではなく、「なぜ時間がかかるのか」を深掘りすることが重要です。
「マニュアルが分かりにくい」「承認フローが複雑」「システムが古い」といった要因が考えられます。根本的な原因を明確にするには、「なぜ」を繰り返して原因を追究する「なぜなぜ分析」などのフレームワークを活用するとよいでしょう。
ステップ4:解決策を探る
課題の根本原因が分かったら、具体的な解決策を考えます。この際、改善効果が高く、実行しやすい方法を選ぶことが大切です。「システムの自動化」「業務の標準化」「マニュアルの整備」といった対策が考えられます。
また、すぐに取り組める施策と時間がかかる施策を分類し、優先順位を決めるとスムーズに進められるでしょう。業務効率化のフレームワークを活用すると、より効果的な解決策を見つけやすくなります。
ステップ5|実行・測定・効果を測定する
解決策を決定したら、実行に移します。しかし、実行するだけでは業務効率化が成功したとは言えません。施策が期待通りの効果を発揮しているかを測定する必要があります。
たとえば、「処理時間が短縮されたか」「ミスが減ったか」など、具体的な指標を設定し、定期的にチェックしましょう。業務の効率が向上していれば、その方法を標準化し、継続的に運用することが重要です。
ステップ6|測定した結果をもとに継続や修正を繰り返す
最後に、測定結果をもとに施策の継続や修正を行います。業務環境は日々変化するため、一度の改善で終わらせるのではなく、定期的に見直すことが求められます。
もし期待通りの効果が得られなかった場合は、原因を再分析し、新たな対策を考えましょう。PDCAサイクルを回すことで、業務効率を長期的に維持しやすくなります。継続的な改善を行うことで、組織全体の生産性向上につながるでしょう。
フレームワークの効果的な活用方法とコツ
フレームワークを効果的に活用するには、やみくもに使うのではなく、いくつかのポイントを意識することが大切です。目的の明確化、QCDの視点、そして現場の声をどう取り入れるかによって、改善の成果が大きく変わります。
フレームワークを活用する前に「目標・課題」を明確にする
フレームワークを効果的に活用するには、事前に目標と課題を明確にすることが大切です。目的が不明確なまま進めると、適切なフレームワークを選べず、効果を発揮しにくくなります。そのため、業務改善を目指す際は「どの業務をどの程度改善したいのか」を具体的に設定しましょう。
関連記事:【個人向け】業務効率化の目標例とは|具体的な設定手順やポイントを解説
QCDを意識する
業務効率化を図る際は、QCD(品質・コスト・納期)を意識することが重要です。品質を維持しながらコストを抑え、納期を守ることが、事業の成功につながります。業務のスピードを重視しすぎると品質が低下し、逆に品質を優先しすぎるとコストが増加する可能性があります。そのため、バランスを考慮しながら業務を見直すことが求められます。
上層部や担当者は現場の意見に耳を傾けて改善策を構築する
業務効率化を進めるには、上層部や担当者が現場の意見を十分に取り入れることが欠かせません。現場の社員は日々の業務を通じて、実際の課題や非効率な部分を把握しています。
たとえば「手作業が多く時間がかかる」「情報共有がスムーズにできない」といった具体的な問題点をヒアリングすることができます。これらの声を反映しながら改善策を構築すると、実用的な解決策を導きやすくなります。現場と経営層が連携し、継続的に業務改善を行うことが重要です。
まとめ
本記事では、業務効率化を実現するフレームワークや改善の進め方について解説しました。業務のムダを削減し、生産性を向上させるためには、適切なフレームワークを活用し、課題を明確にすることが成功の手助けとなるでしょう。また、継続的な見直しと現場の意見を反映することで、より効果的な業務改善が実現できます。
フレームワークを活用するだけでなく、業務全体を俯瞰して把握することも、改善の第一歩です。Peaceful Morningでは、Robo Runnerを活用した業務可視化コンサルティングを提供しています。 現在の業務を“見える化”し、次のアクションに繋げたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中

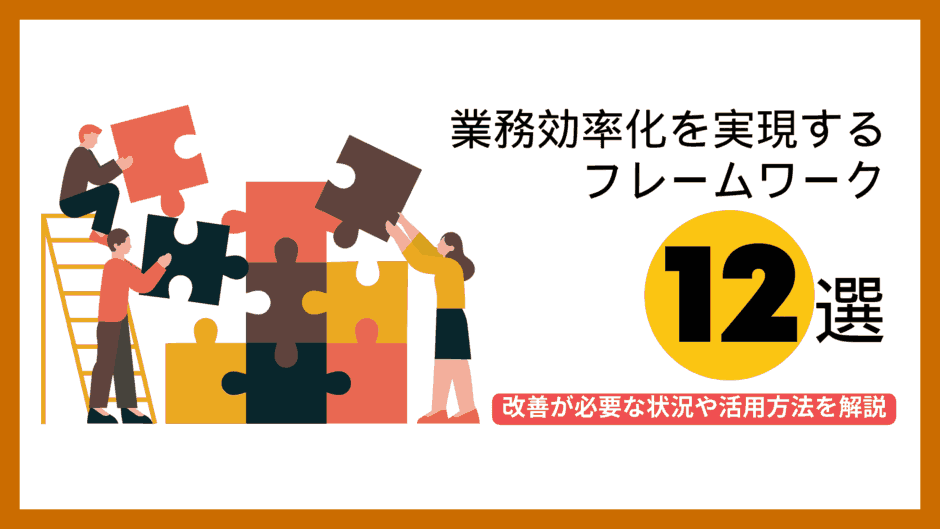
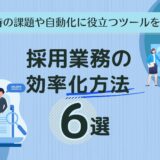
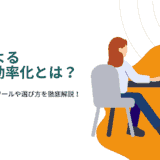
コメントを残す