DXを推進する際、企業でボトルネックになりやすい項目のひとつに、レガシーシステムがあります。レガシーシステムとは、企業内で長期間使われている古いコンピューターシステムの総称で、新たなテクノロジーの登場により相対的に陳腐化していく性質があります。
この記事では、レガシーシステムの詳細とDXの関係性、要因やビジネスへの影響について解説します。自社システムがレガシーシステムに該当するのか、該当していた場合どのような影響があるのかを押さえ、DX推進に潜む自社課題を特定し、解決策を検討しましょう。
レガシーシステムとは
レガシーシステムは、長年の運用で更新・機能追加・拡張が繰り返されてきた結果、古い技術や構成が残ったシステムを指します。
既存システムを外部ベンダーに任せている場合、ベンダーロックインが生じ、契約更新を余儀なくされることがあります。仮に一部の従業員に任せていた場合、依存度が高いほど、属人化や退職に伴う知識・技術の喪失につながります。
既存システムがレガシー化していると、急速に発展するデジタル技術に対応しきれない可能性があり、企業のボトルネックになることもあります。
関連記事:ベンダーロックインに陥る要因とは?脱却するポイントを解説
DXとの関係性
経済産業省が公表した「DXレポート」によると、レガシーシステムはDX推進の足かせになっていると指摘しています。DXの目的はデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、市場の競争優位性を確立することです。レガシーシステムを抱えていれば新たなデジタル技術に対応できず、DXを推進する競合他社に後れを取ってしまいます。
レガシーシステムは保守運用コストの高騰やセキュリティリスクの増加といった懸念を招きますが、いずれも組織の変革を目指すためです。大がかりな取り組みであるからこそ、DXに踏み切るうえではレガシーシステムの課題を早期解決させることが大切です。
2025年の崖との関係性
経済産業省の資料では、DXにおける課題として「2025年の崖」について警鐘を鳴らしています。「2025年の崖」は、レガシーシステムの刷新が進まない場合、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じる可能性を指摘するものです。DXにおいてはIT人材の確保や育成も伴いますが、これらが適切に進まない限り、日本経済は大きな損失を招き、経済破綻に陥る可能性もあります。
DXは企業にとって大きな取り組みではありますが、迅速に取り組む必要があることが理解できるでしょう。
関連記事:「2025年の崖」とは?起こりうる問題や対応策を解説!
レガシーシステムの要因
レガシーシステムを刷新しない限り、日本経済に大きな損失をもたらす可能性があります。では、そもそもレガシーシステムとはどのようなことが要因で生まれてしまうのか、ここでは要因の詳細について解説します。
更新・追加開発によるシステムの複雑化
レガシーシステムに陥る要因のひとつに更新や追加開発によるシステムの複雑化が挙げられます。システムを日常的に使うからこそ利便性や効率化を図るべく繰り返されてきた更新や追加開発ですが、何年も何十年もこうした作業が繰り返されていれば、システムが複雑化するのは当然と考えられます。
システムが複雑化すれば全体像の把握が困難になり、場合によってはエラーや故障などが起きやすく、改修コストが増大する原因につながることもあります。
知識・技術の消失
システムの更新や追加開発を繰り返している場合、システムに大きな仕様の変化が伴います。この部分を社内のIT人材に任せてばかりいると、従業員が退職したり定年を迎えた場合、システムに関する知識や技術を持つ人材がいなくなるため、ブラックボックス化が進みます。
追加開発を検討しても実現が難しく、古いシステムを使い続けざるを得ない状況が生じます。
外部ベンダーへの依存
外部ベンダーにシステムの保守運用を任せていた場合もレガシーシステムに陥る要因です。ベンダーへの依存度が高いほど適切にシステムを維持できない環境、いわゆる「ベンダーロックイン」に陥るためです。
ベンダーロックインに至った場合、社内で自由にシステムの刷新・更新ができなくなってしまうため、レガシー化はますます進むと考えられます。
関連記事:ベンダーロックインに陥る要因とは?脱却するポイントを解説
レガシーシステムによるビジネスへの影響
社内システムがレガシーシステムだと判明した場合、気になる項目として挙げられるのが社内ビジネスへの影響でしょう。ここからはレガシーシステムによるビジネスへの影響について解説します。
さまざまなパフォーマンスが低下する
レガシーシステムによって社内のさまざまな業務パフォーマンスが低下します。業務の中枢を担うシステムが老朽化を迎えていれば、その分だけトラブルが起きやすくなります。トラブルが多発すれば、業務の中断が余儀なくされるだけでなく、頻繁に起こる業務中断によって従業員のモチベーション低下にもつながります。
さらに、企業に点在するデータ資産が多ければ多いほど、検索速度が低下し、従業員がシステムを円滑に使えなくなることもあります。こういった状況が続く、あるいは多発すればするほど、従業員は残業や休日出勤を余儀なくされ、人件コストなどさまざまなコストが余計に発生することにもつながります。
既存システムの保守運用コストが高額になる
レガシーシステムを使い続けた場合、部署単位での最適化や追加開発などが生じるものの、その部分さえ目をつぶれば新システムに乗り換えるよりもコストが低いと考える方も多いでしょう。しかし、追加開発など繰り返しシステムが複雑化すると保守管理そのものに多くのコストを必要とすることも多く、結果的に高額な金額になる場合があります。
例えば、システムのデータベースを維持するべくアップグレードや堅牢なセキュリティツールを別途導入する必要がある場合、それぞれにコストが掛かるだけでなく、老朽化したシステムによってトラブル発生の頻度が高ければ業務中断を余儀なくされるでしょう。
トラブルの度に外部ベンダーに修理を依頼していれば新システムを導入するよりもコストが掛かり、負のサイクルに陥る可能性も少なくありません。
保守運用が属人化しやすい
レガシーシステムは特定の分野に精通した知識や技術を要する人材でしか運用できないことが多く、属人化しやすいです。仮に従業員に保守運用を任せきりだった場合、通常の業務に加えて保守運用による業務も抱えなければならず負担は増える一方です。
例えば1990~2000年代にシステムが実装され、その当時のことをよく知る担当従業員や技術者は、2025年以降に順次定年退職を迎えます。仮に定年年齢が引き上げられても、システムに熟知する従業員や技術者はやがて定年退職を迎え、現場を離れることになります。
仮に外部ベンダーに一任していた場合も理由は同じです。こうした理由から、システム担当者が不在となった後、どのように運用していく必要があるのか熟考が迫られる点は、ビジネスに限らず企業にとって大きな課題となるでしょう。
法改正や市場変化への順応が難しい
社会の変容とともにビジネス環境も大きく変化すれば、必然的に法改正に順応できるシステムが求められます。例えば2024年に電帳法(電子帳簿保存法)が改正され、取引で発生した書類をデータ保存することが義務化となりましたが、仮にデータの電子化に対応していないレガシーシステムだった場合、法令違反を招く危険性があります。
法令違反となれば企業信用度の失墜や廃業といった最悪の事態に陥る恐れもあるため、レガシーシステムを使い続けている企業ほどビジネスシーンで遅れを取ることになるでしょう。
セキュリティリスクが増える
システムが古くなるほどシステム内に構築されたセキュリティも古くなるため、サイバー攻撃の標的になりやすいです。サポート終了を迎えたシステムを使い続けていれば、日々攻撃性が高まるセキュリティリスクに適切に対応できません。
こうした理由を総合的に考えると、レガシーシステムからの脱却は、あらゆる企業課題を解決に導くためには避けられない課題と考えられるでしょう。
DX推進が停滞する
レガシーシステムがDXの妨げになることもあります。例えばOSの古いAndroidスマートフォンに最新アプリをインストールしようとすると、OSの古いスマートフォンに最新アプリが入らないのと同様に、レガシーシステムでも新しいアプリや連携が使えない場合があります。利便性や生産性向上を目的としたアプリケーションが連携不可などを理由に使えないため、DX推進が停滞する点もレガシーシステムによる影響のひとつといえるでしょう。
レガシーシステムから脱却する方法
さまざまな影響を及ぼしかねないレガシーシステムから脱却する際は、下記の方法を試してみましょう。
マイグレーション
マイグレーションとは、ハードウェア・ソフトウェア・データなどのIT資産を新しい環境へ移行することです。例えばアプリケーションやストレージ、データベースなどの移行作業などが挙げられます。
各種移行作業
アプリケーションやストレージ、データベースなどの移行はそれぞれ下表のような特徴を持っています。
|
アプリケーションの移行 |
従来のアプリケーションと同等の機能を備えた新たなアプリに移行すること |
|
ストレージの移行 |
データを格納しているストレージを新たなものに移行すること |
|
データベースの移行 |
データベース基盤を新しい環境へ移行すること |
|
BPMの見直し |
業務プロセスの整理・分析を通じて業務効率化を目指すべく適切な行動へと移していく取り組みのこと |
なかでもBPMの移行では社内に蓄積されたデータやデータベースの移行も伴うため、アプリケーションとストレージの移行も並行して行うことが多いです。
モダナイゼーション
モダナイゼーションとは、老朽化したIT資産を最新のアーキテクチャや製品に置き換える取り組みです。詳しくは以下の記事でも解説しているため、参考にしてください。
関連記事:モダナイゼーションとは?概要やメリット、実施手順をわかりやすく解説
リプレイス
既存システムやパッケージソフトウェアを新たなものへと移行することを指します。リプレイスでは既存の業務プロセスを見直してから導入することになるため、業務効率化を実現させる上で有利な方法です。
リライト
新たな環境に合わせて現行のプログラムを最適な言語・ソフトウェアに書き換えることを指します。システムの機能や仕様に大きな変更を加えないため、スムーズに移行できるメリットがあります。
リホスト
サーバーやOSなどを新たな環境に構築し、日常的に使用するアプリケーションやデータを移行することを指します。例えばオンプレミス環境からクラウド化に切り替える方法もリホストに該当します。
クラウドサービス
レガシーシステムをクラウド上に移行する方法もあります。オンデマンドでの提供により、いつでもどこからでもアクセスできる利便性の高さが魅力です。セキュリティ対策が整備されてあることが多いため、レガシーシステムの課題を素早く解決できる点はクラウドサービスならではのメリットです。
レガシーフリー
古い部品や機器を使わず、新たな仕様を採用したシステムのことをレガシーフリーと呼びます。古い部品・機器に依存しない設計のため、保守や調達の負担を抑えやすいというメリットがあります。
DX人材の確保・育成
社内でDX人材を育てる、あるいは採用を通じて確保する方法も有効です。DX人材を確保すれば、レガシー化の原因特定と迅速な解決につなげられます。
複数のDX人材を確保・育成しておけば次のレガシーシステムを生む可能性を下げることにもつながります。さらに、ベンダーロックインやシステムのブラックボックス化など、企業課題になりやすい問題も未然に防ぐことができます。
自社課題に適したDX人材を速やかに確保したいときは、Peaceful Morningの「DX Boost」がおすすめです。グループ600万名を超える人材データベースから、貴社に最適なDX人材を即日ご提案できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。
また、DX人材を社内育成したいときは、RPA・AIの導入から開発、運用まで、プロのエンジニアが伴走型でサポートする「Robo Runner」が有効です。無制限のチャットサポートやWebミーティング、豊富なeラーニングコンテンツを通じて、主要ツールの習得から実際の業務活用まで、企業や部署のDX推進を全面的にサポートします。
生成AIを含むデジタルツールの活用により業務効率化を図りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
レガシーシステムは企業成長の妨げになるだけでなく、ビジネスにも多くの影響を与える企業課題のひとつです。要因や影響、脱却する方法などを参考にしながら、強固なビジネス基盤の構築を図りましょう。DX人材を速やかに確保したい方は、Peaceful Morningまでお気軽にご相談ください。

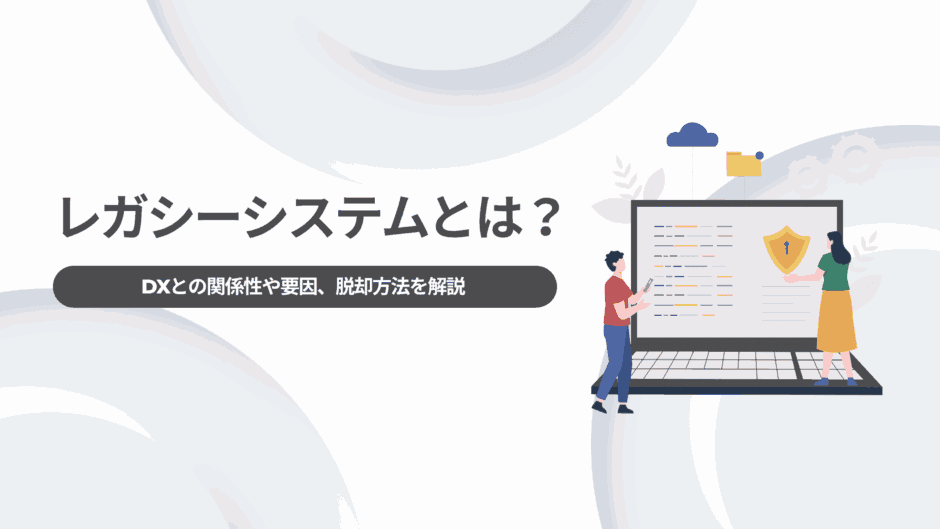




コメントを残す