顧客の購買行動が社会の変容とともに大きく変化する昨今、企業は膨大なデータを活用し、顧客1人ひとりのニーズに応える製品・サービスの提供やアプローチが求められています。このときに必要となる取り組みがデータ利活用です。この記事では、データ利活用の概要、目的・メリット、成功させるためのポイントを解説します。
関連記事:データリテラシーとは?概要やメリット、身につけ方について解説

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /
データ利活用とは
データ利活用とは、収集・蓄積・分析したデータを業務や意思決定に反映し、業務効率化・生産性向上・新たな価値創造を通じて競争力を高める取り組みです。近年はビッグデータを活用して企業課題の解決に取り組み、利益率や顧客体験の向上を実現する企業が増えています。
データ利活用の目的
データ利活用は、必要になりそうなデータを闇雲に集めるだけでは意味がありません。データ利活用は、次の目的に沿って進めることが不可欠です。
意思決定の精度向上
これまで勘や経験に左右されがちだった意思決定も、詳細なデータにより精度が高まり、根拠のある意思決定へと変えることができます。データに基づいた判断は不確実性の高い現代ビジネスにおいて効果的であるため、今後の戦略的意思決定プロセスをより強固にします。
新たな企業価値の創出
データ利活用は、既存製品・サービスのブラッシュアップにも役立ちます。例えば顧客ニーズについてまとめたデータを用意・分析すると、これまでは見えなかったより深い潜在ニーズの抽出を可能にします。ニーズを深く理解し適切な製品・サービスへと改善する取り組みは顧客体験の向上へとつなげ、企業価値を高めることにも期待できます。
データ活用との違い
データ利活用と混同しやすい言葉のひとつにデータ活用があります。データ活用は、企業に蓄積されたデータを用い、業務や意思決定に役立てることです。一見するとデータ利活用と同じように思うかもしれませんが、ある企業課題に対してどういうデータが必要かといった目的から逆算したデータ収集・分析を行っていないため、求める成果に至らない場合があります。
一方、データ利活用は、目的から逆算して必要なデータを定め、収集・分析するため、製品・サービス・ビジネスモデルなどの改善や経営戦略の立案に有効活用できるといった違いがあります。
データ利活用で得られるメリット
組織的にデータ利活用に取り組むと、以下のメリットに期待できます。
データドリブンな経営を実現
データドリブン経営とは、勘や経験だけに頼らず、データに基づいて意思決定する経営手法です。データ利活用を通じて市場動向や顧客理解など企業にあるさまざまな分野を幅広く理解することで、多角的な視点による改善とイノベーションを可能にします。
なかでもリアルタイムデータを活用すれば、社会や顧客の変化に素早く対応した意思決定も可能になり、経営に潜むリスクを最小限に抑えることができます。
新たな価値の提供
目的に応じたデータの収集・分析によって顧客の行動や思考を深く理解し、1人ひとりに焦点を充てた製品・サービスの開発にもつながります。市場ニーズに応じた製品・サービスへと改善するだけに留まらず、根拠のあるデータを活用することで、ニーズを捉えた新たな製品・サービスの開発・提供も実現できます。
新規市場開拓
社内データと行政の公開統計を組み合わせて分析すると、これまでは見えなかったユーザーの潜在ニーズを表面化することもできます。深い洞察力によっては顧客生涯価値の向上を実現する新規市場の開拓にもつなげられます。
現状把握による組織的な改善
データ利活用は、企業の現状把握に役立つだけでなく、組織的な改善点の特定にもつながります。例えば、これまでは収益率から業績低下を判断していたものを、データ利活用によって詳細な原因を特定・把握できる、などです。業績低下の原因が高精度なデータによって洗い出されれば、適切な意思決定を通じて組織的に速やかに改善することも可能です。
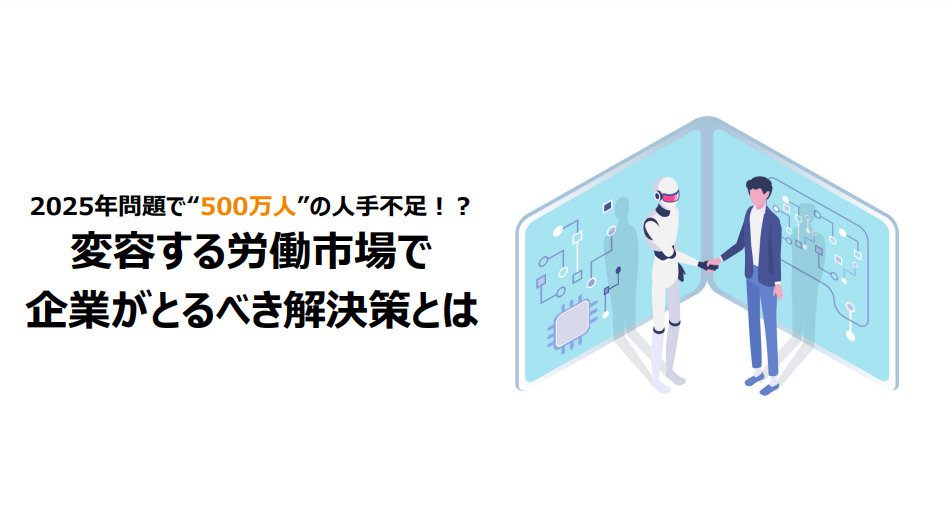
\ 業務可視化の方法を解説 /
データ利活用に適した分析手法
データ利活用にあたっては、目的に応じて適切な分析手法を選ぶことが大切です。分析手法には「何が起きたのか」を把握する手法から「今後どのようにすべきか」を判断する手法などが段階的に存在します。ここからはデータ利活用における4つの分析手法を段階に応じて解説します。
1.記述的分析
記述的分析は「何が起きたのか」を明らかにするための分析手法です。社内に点在する過去のデータの集計・可視化を通じて現状把握する際に役立ちます。例えば製品の売り上げデータをグラフ化して前年比と比べる、顧客情報を整理して傾向を把握するなどがあります。記述的分析によって現状や兆候の有無を把握できます。
2.診断的分析
診断的分析は記述的分析で明らかになった物事について「なぜ起きたのか」を把握するための分析手法です。「なぜ?」を特定することで、状況改善に有効なヒントの特定やリスク回避に効果的な方法を分析できます。
3.予測的分析
予測的分析は記述的分析と診断的分析で収集したこれまでの傾向・パターンを考慮し、「○○すれば△△を防げる見込みが高い」といった将来予測を行う手法です。予測的分析によって多様なビジネスシーンにおいて先手を打った戦略的な意思決定を可能にします。
4.処方的分析
処方的分析は記述的分析から予測的分析までのステップを踏まえ「次に何をすべきか」を導くための分析手法です。過去のデータから現状把握を実施し、将来の予測を行った上で目標達成のための最適なアクションを具体的に導き出すことができます。
データ利活用に向けた手順
データ利活用はただ必要なデータを収集・分析するだけではありません。効果を最大化するために、次の4つの手順を踏みましょう。
課題や目標の定義・データの収集
データ利活用に取り組むのであれば、まずは企業課題や目標を明確に定義しましょう。そうすることで必然的に集める必要があるデータがどのようなものかを把握できます。
定義が終わったらデータ収集に移りますが、データ収集は顧客データや販売履歴、オンライン行動記録などさまざまな情報源から行うことを心がけましょう。事前に定義した課題や目標に即したデータを収集できれば、この後行う分析作業がより効率的かつ効果的なものになります。
整理(クレンジング)
次に収集したデータを整理します。集めたばかりのデータは複雑化していることが多く、分析を難しくさせます。収集後のデータはクレンジングを行い、不正確なデータの修正・除去や重複削除を実施し、分析しやすいよう整えておきましょう。
分析
次に、収集・整理したデータを分析します。データ分析ではこれまで行ってきた分析よりも幅広い視点を持ち、顧客の潜在ニーズや傾向、洞察を抽出することを心がけましょう。例えば顧客データの分析を通じて市場セグメントの特定を図るなどです。
活用
最後に分析したデータで得られた潜在ニーズや傾向、洞察を経営・ビジネス戦略に反映させます。例えば、潜在ニーズを捉えたマーケティング戦略を作成する、販売促進に有効なキャンペーン設計などです。詳細かつ根拠に基づくデータによって顧客1人ひとりに適したアプローチを実現できます。
データ利活用を成功へと導くポイント
データ利活用を実施する上では、これから解説する成功へと導くポイントを参考にしてみてください。
現状課題を洗い出す
データ利活用は企業に潜むさまざまな課題を解決するための取り組みです。そのため、データ利活用を成功させるためには、企業に潜む現状課題を洗い出すことが先決です。例えば企業のブランドイメージを向上させたい、売上アップを目指したい、DX推進に向けてDX人材を育成・確保したいなど、さまざまな視点から課題を洗い出しましょう。
目的を明確にする
データ活用はデータを使って業務・ビジネスそのものを見直していく取り組みであるのに対し、データ利活用は目的から逆算して必要なデータを集め分析し、課題解決へと導く取り組みです。したがって、データ利活用を成功させる上では、なぜ利活用する必要があるのかを常に振り返られるよう、目的を明確にすることが大切です。
例えば売上アップを企業課題とするのであれば、データ利活用に絡む目的には最適なキャンペーン施策の立案などが挙げられるでしょう。目的を明確にすることで、過去数年分の店舗別に分けた売上データやこれまで実施してきたキャンペーン情報、売上情報が必要であることが素早く判断できます。
スモールスタートする
データ利活用には、目的の洗い出しによって迅速かつ適切な意思決定につながるメリットがあるものの、一度に全部の企業課題を解決しようとすると膨大な時間を要します。データ利活用にどのような効果があるのかを判断するためにも、まずはスモールスタートすることが成功への秘訣です。
価値創出を確認後に組織展開する
スモールスタートでデータ利活用を実施し、企業に新たな価値をもたらすことが理解できたら、最後に組織展開するための環境を構築します。データ利活用が組織的に仕組み化されていないと、データの有効性については理解できても、利活用につながらずそこで終わってしまう可能性があります。
例えば生成AIを導入し、従業員を介すことなくデータ利活用の仕組みを維持・運用へとつなげる方法は効果的です。従業員に依存すると属人化を招く懸念もあるため、時代に則した方法で効率的に組織展開を図りましょう。

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /
各業界でのデータ利活用事例
データ利活用は各業界でどのように行われているのでしょうか。ここからは各業界でのデータ利活用事例について解説します。
農業
農業界ではこれまで人間の勘に頼りがちだった農業経営を革新するべく、IT技術を用い、世代を超えたノウハウの伝承を成功させています。また、これまでは農作業の記録を手書きで管理し多くの労力や時間を費やしていた課題も、パソコンやスマートフォンで農業日誌や圃場管理が行えるクラウド型農業生産管理ツールを活用し解決へとつなげています。
参考:デジタル庁|アグリノート
道路旅客運送業
道路旅客運送業ではセンサー乗降データの活用によってバス路線の最適化を実現させています。これまでは勘と経験に頼った経営が主流化していましたが、データ利活用を通じて車両数を増加することなく輸送量を1.5〜3倍に拡大させました。収益改善と併せて地域住民の利便性向上にも成功させています。
参考:デジタル庁|イーグルバス
情報サービス業
情報サービス業では読みたい本をどこの図書館で借りられるのかを確認できる蔵書検索サイトをスタートさせています。これまでにも図書館システムが設置されていましたが、各自治体が独自にサービスを確立させていたために利用者にとっては個別に蔵書情報や貸し出し状況を調べなければいけない手間がありました。
検索サイトの立ち上げによって、複数かつ多数の図書館の蔵書情報や貸し出し状況が容易に検索できるようになり、図書館の利用促進につなげています。
参考:デジタル庁|カーリル
製造業
アメリカのインテル社では半導体チップの品質テストにおいて、テスト回数が膨大であるために生産コストが増加する課題を抱えていました。データ利活用によって不要なテストを大幅削減に成功し、半導体チップの生産ライン1つにつき、約3億円のコスト削減を果たしています。
参考:インテルのIT部門、ビッグデータ活用で2013年度に約80億円の効果 | 日経クロステック(xTECH)
関連記事:製造業DXとは?必要性やメリット、手順や成功のポイントを解説
小売業
小売業界のなかでも精力的にさまざまな取り組みを図るローソンでは、顧客が抱える深いニーズを捉えるべく、顧客が店舗に入店してから退店するまでの一連の行動をデータとして取得し、より購買行動につながる施策を考察する方針に切り替えました。
データ利活用を通じて1店舗に3,000種類ほどの商品を置いたり毎週数十種類の商品を入れ替えたりしながら、多様なニーズに対応するための環境構築を実現させています。
参考:ZDNET|コンビニ内分析で購入率をどう高めているか、ローソンのビッグデータ活用
金融業
三井住友フィナンシャルグループでは、過去数か月分のクレジットカード利用に関するデータとディープラーニングを用いて不正検知アルゴリズムを開発し、不正取引における判定率の大幅な引き上げに成功させています。
従来の不正検知は、カードの利用時間や金額などのパラメータを人間が設定したルールに基づいてチェックし、従業員が店舗や利用者に問い合わせを行い、確認を通じて判断する手法でした。
不正検知アルゴリズムの導入と継続的な最適化により、約90%まで向上しています。
参考:「カード不正利用」の検知精度、深層学習で劇的向上 – 日本経済新聞
教育機関
教育機関では、データサイエンスのテストに向けて自身の実力がどの程度なのかわからないといった課題や、社会に出たあと速やかに通用するだけのスキルを身につけたいといった生徒の課題に対応するべく、実社会の知見を生かしたデータサイエンス講義の提供を実現させています。
大学という公的機関と民間企業の技術、そしてオープンデータの活用によって社会的意義の大きい取り組みへとつなげ、座学では得られない体験型カリキュラムの提供やリアルな講義を提供できるようになりました。
データ利活用の課題と対策
データ利活用にあたっては、いくつかの課題も潜んでいます。ここからは具体的な課題と対策方法について解説します。
データ人材の不足
経済産業省の資料では、データ利活用人材の不足に備え、早期からの確保・育成・外部リソース活用を推奨しています。データ利活用を実現し成功へと導くためには、データを適切に取り扱える人材が不可欠です。
しかし、現在の日本は少子高齢化により、人材そのものが不足している状況です。そのなかからデジタル人材をみつけ、確保することはさらに困難を極めることになります。
こうした問題を解決するためには、社内従業員をデジタル人材として育成する方法や外部リソースと連携し、強力なデジタル人材を確保する方法が有効と考えられます。
Peaceful Morningでは、DX推進を加速させるプロ人材を紹介するサービス「DX Boost」を提供しています。グループ600万名を超える人材データベースから、貴社に最適なDX人材を即日ご提案できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /
価値・リスクの判断が困難
データ利活用に取り組み始めたばかりの頃は、データの価値がどれほどのものであり、ビジネス上にどのようなリスクを及ぼすのかについて正確に判断することが困難です。これらの問題を解決するべく、まずはスモールスタートで効果検証と改善を繰り返しましょう。
小さな成功体験を積み重ねることで、データ利活用の価値やリスク判断を適切に行えるようになります。
まとめ
データ利活用は、企業が競争力を高め、新たな価値を創造する際に有効な取り組みです。単にデータを集め利用するのではなく、明確な目的に沿ってデータを活かすことが大切です。データ利活用に踏み切る上でDX人材が不足しているときは、お気軽にPeaceful Morningへご相談ください。

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /


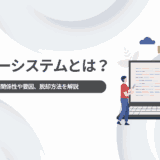
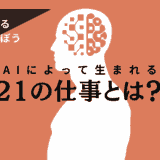
コメントを残す