デジタル技術がめまぐるしく発展する近年、さまざまな機能を搭載したシステムが次々と展開され、業務の効率化、自動化、従業員配置の最適化を図る企業が増えています。そのようななか、既存システムに依存しすぎていたために、新規システムへの導入検討が足踏み状態となっている企業も少なくありません。
この状況を改善する取り組みのひとつとして注目を集めているものがモダナイゼーションです。この記事ではモダナイゼーションの概要をはじめ、重要性や代表的な手法、成功させるコツについて解説します。モダナイゼーションによってDX推進の加速にもつながるため、どのような手法があり、どのような方法で成功するのかを押さえておきましょう。
目次
モダナイゼーションとは
モダナイゼーションとは老朽化した既存システムを、社内ニーズに応じた新システムへ最適化することを指します。例えばガラケーをスマートフォンに買い替えることもモダナイゼーションの一例です。過去の資産を活かしつつも、新たなシステムに切り替えることで生産性や安全性の向上につなげ、企業競争力の低下を防ぎます。
自社システムが古くから使われているものだと、その影響で業務端末のフリーズやエラー、故障のほか、新たなシステムと連携できないなどの不便さを経験したことがあるでしょう。これらの問題を解決できる手法がモダナイゼーションです。
レガシーシステムとの関係性
「遺産」の意味を持つ「legacy」を使ったレガシーシステムは、現代社会に対応しきれていない旧システムを指す言葉で、例えば創業当初から微調整や機能追加を行いながら使い続けているシステムなどを指し、DX推進を妨げる要因のひとつといわれています。
モダナイゼーションは既存システムを新たなシステムへと最適化することから、レガシーシステムにまつわる問題を解決する手法という関係になります。
モダナイゼーションとレガシーシステムが注目を集める理由のひとつに経済産業省が公表した「DXレポート」があります。DXレポートではレガシーシステムにまつわる企業課題を解決できなかった場合、DXの実現だけでなく、2025年以降に最大12兆円規模の経済損失を招く可能性を挙げています。この問題は日本の将来を左右する大きな問題として「2025年の崖」と呼ばれています。
「2025年の崖」を解決する上で有効な手法と考えられているものがモダナイゼーションであり、企業は早急な対応が求められています。
参考:経済産業省|DXレポート平成 30 年9月7日 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会
関連記事:「2025年の崖」とは?起こりうる問題や対応策を解説!
混同しがちなレガシーマイグレーションとの違い
モダナイゼーションと混同しがちな言葉のひとつにレガシーマイグレーションがありますが、これは「遺産の移行」という意味で、時代遅れな既存システムを新たな環境に置換する手法です。イメージしやすいものとしてはオンプレミスベースのデータ保存をクラウドに切り替える方法などがあり、既存システムの機能・構造の変更は行いません。
従来とは異なる環境でシステムやデータの利用を再現する手法のため、レガシーシステムに多くの課題がある企業にとっては身近な手法といえるでしょう。
一方、モダナイゼーションは社内に点在する過去の資産を活かしつつ、既存システムを新システムに最適化を図る取り組みです。どちらもレガシーシステムに関する言葉ではあるものの、手法の詳細に大きな違いがあることを押さえておきましょう。
モダナイゼーションが重要視される理由
モダナイゼーションが重要視される背景には、経済産業省の「DXレポート」公表を機に、さまざまな理由が浮き彫りとなっているためです。具体的には下記の通りです。
既存システムにおける課題の解決
企業で使用するシステムの多くは、機器や機能の追加などを繰り返しながら長期運用されていることが多く、次第に時代と共に変化するデジタル技術に沿わなくなります。その結果、業務効率や品質、作業速度などの低下を招いてしまいます。モダナイゼーションは既存システムにおけるこれらの問題を解決し、業務の効率の向上が実現できます。
生産性やパフォーマンスの向上
レガシーシステムは社内構築されてから機能の追加や微調整などを繰り返しながら使用され続けているため、既存従業員では手の施しようがない状態にまでブラックボックス化していることが珍しくありません。モダナイゼーションを通じて現状の可視化やアーキテクチャの再構築が実現できれば、新たなシステムの利用が可能になり、生産性や業務パフォーマンスの向上に期待できます。
コストの削減
老朽化をはじめとしたレガシーシステムは、故障やトラブルが発生する頻度が比較的高いために、補修運用費が掛かりやすい欠点があります。モダナイゼーションによって新システムへと最適化できれば、定期的に生じていたメンテナンスコストを削減できるほか、福利厚生の拡充や顧客への還元など、従来では実現できなかったコストの最適化につながります。
顧客体験の創出
膨大なデータを収集・分析し、自社商品やサービスに反映させる取り組みが一般化するなか、レガシーシステムを抱える企業では、データ共有の複雑化などの理由によって過去の資産を有効活用できず、商品・サービスの向上を妨げていることが少なくありません。モダナイゼーションによってデータ共有が円滑に行えるようになれば、市場ニーズに合わせた新たな顧客体験の創出につながります。
モダナイゼーションの代表的な手法
モダナイゼーションにはさまざまな手法があります。具体的には下記の通りです。
リプレイス
リプレイスは既存システムから最新システムに移行する手法で、抜本的な業務変革に適しています。企業が目指すビジネスモデルや業務プロセスに応じたシステムを導入できるメリットがある一方で、コストや業務負荷がかかりやすいほか、移行期間が長期化するデメリットもあります。DX推進を目指している企業にとっては有効な手法のひとつです。
リホスト
リホストは既存システムのアプリケーションコードは据え置いた状態で、サーバー・ソフトウェアといった稼働環境を新たなプラットフォームへ移行する手法です。アーキテクチャへの大規模な変更が必要ないためスムーズに移行できます。シンプルな操作感で使いやすいものも多く、既存システムのサポート期限が迫っている際の延命処置やクラウド移行の第一歩として利用されることもあります。
リライト
リライトは古いプログラミングコードを新しい言語やフレームワークに書き換える手法です。コードの書き換えによってシステムのコア機能は維持しつつ、UI/UXの改善や最新技術の活用が可能になり、業務パフォーマンスの向上が見込めます。比較的取り組みやすい手法である一方、プログラミング言語スキルを持つ従業員の確保や育成、または外部リソースの利用が必要です。
リファクタリング
リファクタリングは既存ソフトウェアの外部動作に変更は加えずコードを再構築する手法です。言語の見直しから行うリライトに対し、リファクタリングは言語の変更はせずに内部構造の複雑性を解消するため、システムパフォーマンスを保ちながら将来的な機能拡張を容易にするなどの効果が期待できます。
リドキュメント
リドキュメントは既存システムに関する各種マニュアルを現状に合わせて更新する手法です。システムに対する理解が深まり、運用効率の向上に期待できます。特に長期にわたって使用され続けているシステムの場合、開発者の変更が繰り返されていることがあるため、最新情報への更新によってエンドユーザーの影響を最小限に抑えつつ安定したシステム運用につながります。
モダナイゼーションを実施するためのステップ
モダナイゼーションを実施する際は下記ステップを参考にしてください。
現状を把握し予算・適応範囲を決める
まずはIT資産の現状を把握するため、各システムをリストアップしながら必要項目を可視化しましょう。どのような業務で使用しているのか、構築場所はオンプレミスとクラウドのどちらかなどを記入しながら課題を洗い出します。業務の影響度を踏まえて洗い出すことで、モダナイゼーションを実施するシステムの優先順位が付けやすくなります。
また、モダナイゼーションに適した従業員を決める必要があるため、全従業員のスキルを洗い出し、可視化しておくとスムーズに進められます。
手法を選択する
次にどの手法を用いて構築するかを決めます。リライトやリドキュメント、リファクタリングなどがありますが、システムの特徴や現状の業務影響度などを振り返りながら適切な手法を決めましょう。
選んだ手法によってはシステムの刷新や段階を踏んで取り組む必要があるなど、業務影響度や実装までの期間が大きく変動します。自社に無理のない範囲で実装できる手法を選びましょう。
移行計画を立てる
移行計画は選んだ手法によって大きく変わります。リプレイスであればレガシーシステムからの脱却を実現できますが、組織全体が一時的に混乱し、業務効率の低下など影響を与える可能性があります。移行時は業務や部署にトラブルが起こる可能性もあるため、無理なく進められる計画を立てましょう。
担当する従業員を決める
次に、実際に担当する従業員を決定します。可視化されたスキル情報をもとに、システムの最適化に適した人材をピックアップしましょう。
ただし、モダナイゼーションは一定の時間や労力を要するため、選定にあたっては従業員リソースの状況や、各部署への影響度も十分に考慮することが重要です。
実装・評価測定を行う
これまでのステップが終わったら、立案した計画を進め、社内システムに関する不具合などを確認します。既存システムと新システムを連携する場合は単独で動作確認を済ませてから行うよう注意しましょう。全システムに連携してしまうと、トラブルが生じた際に業務がすべて停止する事態を招いたり、原因特定が難しくなったりする恐れがあります。
一定期間が経過したら、システムの評価測定を行います。従来と比べてどのような効果がみられたのか、どの業務に利便性がみられたのかを細かく洗い出しましょう。効果や課題は従業員へのヒアリングやアンケートによって把握しやすくなるので、改善・実証を繰り返しながら最適化を目指しましょう。
モダナイゼーションを成功させるコツ
モダナイゼーションを成功させるためには下記のコツを押さえることをおすすめします。
業務の見直しを図る
モダナイゼーションの成功には業務の見直しが不可欠です。従来の業務フローを見直し、不要な工程や無駄な工程を省くことで、業務の効率化とシステムの最適化を実現できます。既存業務にシステムを合わせるスタイルではなく、システムを業務に合わせて変えていくスタイルを選ぶことで時代に則した業務フローを無理なく構築できます。
従業員からヒアリングする
モダナイゼーションは、従業員1人ひとりが抱える業務に対する不満や悩みを解決できてこそ成功といえます。モダナイゼーション実施に際しては従業員から業務プロセスやフローに対する不満や悩みなど、率直な意見をヒアリングしましょう。従業員によっては日常的な業務フローに疑問を抱き、自分なりに工夫して取り組んでいる場合もあります。
従業員から得た業務に対する意見を箇条書きなどを使ってまとめると、手法選びがスムーズになるほか、改善点を踏まえたシステム構築を実現できます。
取り組みやすい計画を立てる
モダナイゼーションはレガシーシステムを使う企業にとっては魅力的な側面があるものの、場合によっては従業員に負担を掛ける、コストが高くなるなどの欠点があります。モダナイゼーションは無理のない計画を立てることが重要なため、社内リソースを考慮しリホストからはじめるなど、いくつかの手法を織り交ぜながら取り組むのも有効です。
モダナイゼーションの3つの注意点
モダナイゼーションにはいくつかの注意点もあります。具体的な注意点は下記の通りです。
目的は明らかにする
モダナイゼーションを行う際は目的を明確にしましょう。システムのセキュリティ強化や信頼性の向上、従業員の利便性向上など、対象と効果を明らかにすることで改善点の特定がスムーズになります。また適切な手法を選びやすくなり、業務影響度を最小限に抑えることにもつながります。
リスク評価を実施する
モダナイゼーションを行う上ではシステムや業務効率に影響が出る点を念頭に置くことも大切です。事前に全社のリスク評価を済ませ、適切な対策を用意しておくとトラブルが生じても冷静かつ適切に対処できます。
テストとバリデーションを実施する
システムのモダナイゼーションには、既存システムの変更またはアップデートが伴います。そのため、十分なテストとバリデーションを実施し、システムにある課題や不具合を特定し、早期的な修正につなげます。モダナイゼーション後に安定的な稼動が確保できるため、業務や従業員への影響を最小限に抑えられます。
まとめ
モダナイゼーションとは、既存システムをさまざまな手法を用いて最適化する方法のことです。リホストやリライト、リファクタリングなどの手法がありますが、適切な手法を選ぶ際には従業員へのヒアリングなどを行いながら業務を洗い出す必要があります。
特にリプレイスやリライトのように大規模な変更を伴う場合、既存システムや新システム、プログラミングスキルに精通した人材確保が不可欠です。そのようなときは、社内にDX推進部門を設置し、各スキルを有した人材を配置した上で進めることをおすすめします。
Peaceful MorningではDXに求められる知識・経験を有した人材を最短即日でご提案する「DX Boost」を提供しています。専任のエージェントが貴社の既存システムや業務の現状をヒアリングし、最適な人材へとつなげながらDXを加速させます。モダナイゼーションを検討中の企業担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



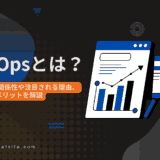
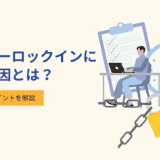
コメントを残す