少子高齢化によって若手人材の不足やベテラン従業員の退職が増え、企業はその規模を問わず早急な対策が迫られています。現代は多くのIT技術の進化がめざましいですが、そのなかでもAI技術を活用した業務の効率化・自動化を実現する企業が増加しています。
「業務効率化」という言葉は、主に人手不足解消を解決すべくITツールを導入して実現する取り組みについて理解する方が多い一方、「業務自動化」については「何を」「どこから」「どこまで自動化できるのか」について知らない方も少なくないようです。
この記事では、業務自動化の概念と注目される理由、メリットや業務例について解説します。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
目次
業務自動化はIT技術で効率化・生産性の向上につなげること
業務自動化は、IoTやAI、RPA、OCRなどのIT技術を活用して社内業務を自動化し、生産性の向上へとつなげることです。自動化できる業務は導入・活用するITツールによって異なりますが、例えば定型的・反復的なデータ入力業務にはRPAツール、いわゆる自動化ツールの導入によって作業をまるごと自動化できます。
近年の日本では経済産業省を筆頭にDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が行われています。この取り組みはIT技術を用いて組織全体を変革することで、人手不足問題の解決の糸口としても注目されています。
またDXは世界的に行われている取り組みであり日本は世界的に見ても遅れを取っている状態であることから、日本企業は早急に取り組むことが推奨されています。こちらの詳細については次項で解説します。
業務自動化が注目される理由
業務自動化が注目される理由は大きく分けて3つあります。具体的には下記の通りです。
少子高齢化による人手不足
現在の日本は少子高齢化が増加傾向にあり、企業全体に大きな影響を与えています。出生率は減少傾向にあり高齢化は加速をみせていることから、企業の担い手である若い人材が不足しているだけでなく、現在活躍しているベテラン従業員の定年退職によって人手不足はさらに加速すると予測されています。
こうした問題を早期解決すべく、24時間365日対応できるAIチャットボットによるカスタマーサポートの設置やRPAツールによるルーティンワークの自動化などを行いながら人手不足対策に踏み切る企業が増えています。
働き方改革の推進
人手不足問題がさらに深刻化すれば、従来の働き方では従業員1人あたりの業務量が増え、残業や休日出勤が増えることが懸念されます。労働時間が増えればその分だけコストも増えることから、解決を図る取り組みとして働き方改革の推進が推奨されています。
現在多くの企業ではDXの推進を通じて業務の自動化を実現させています。「国が推奨しているから」「世界的に進んでいるから」といった理由だけでなく、人手不足問題や働き方改革の推進とDXによる業務の自動化は、密接に関わる取り組みと考えられます。
DXの推進
近年の日本では、経済産業省を中心にDXの推進が積極的に行われています。その背景には少子高齢化社会による人手不足の解消や、2025年以降に生じるとされる年間12兆円の大規模な経済損失の防止が挙げられます。
特にグローバル企業や大企業ではすでにDX化が進んでおり、業務の効率化や自動化による生産性の向上、品質の向上を実現させています。仮にDX推進に本腰を入れなかった場合、多くの企業から後れを取る形となり、企業の市場競争力に大きな影響を及ぼす可能性も考えられます。
参考:経済産業省|DXレポート 平成 30 年9月7日 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会

\ 部署ごとのRPA活用事例100選 /
業務自動化が難航する理由
働き方改革やDXの推進によって加速を見せる業務自動化ですが、世界各国と比べると、日本は難航し後れを取っているのが現状です。ここからは業務自動化が難航する理由について解説します。
現状を把握することが難しい
業務自動化の実現にあたっては、現場で働く従業員の意見が欠かせません。日常業務に抱く不満や悩みを細かく把握するためには、従業員1人ひとりへのヒアリングやアンケートが必要ですが、日常業務と並行して行うとなれば業務遅延が懸念されるほか、調査結果から課題を洗い出すまでに時間と労力も掛かります。
特にバックオフィス業務に従事する従業員の方にとっては早期に取り掛かってほしい取り組みであるものの、経営層としてはこうした問題を懸念して難航することがあります。
関連記事:バックオフィス業務の効率化を図る方法|課題やメリット、ポイントを解説
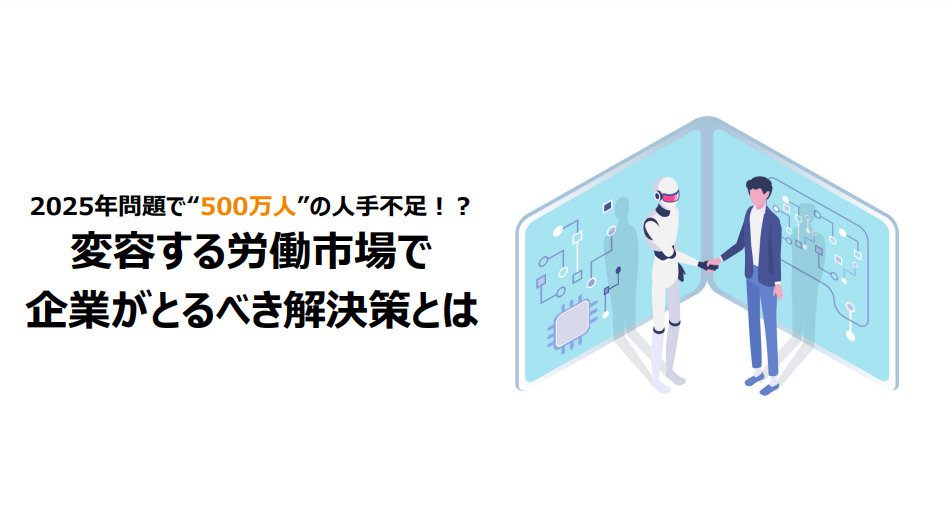
\ 業務可視化の方法を解説 /
業務自動化できる業務かわからない
業務の効率化までは理解していても、どの業務に対応できるのか、あるいはどのようなことを自動化できるのかについて経営層が理解していないために難航する場合もあります。特に経営層のデジタルツールに対する知識が不足していた場合、IT推進部門が詳細説明をしても具体的なイメージができず難航することがあります。
効果が分かりにくい
業務自動化の実施を経営層に打診しても、効果をイメージしにくいことを理由に難航する場合もあります。基本的に企業は営利目的で活動しているため、デジタルツールによる自動化を実現させるためには、具体的な数値を用いながら説明する姿勢が求められます。
デジタル人材の確保・育成が難しい
自動化実現に向けては、デジタル人材の確保・育成について検討する必要もあります。仮に経営層がデジタルツール導入に前向きな姿勢を見せても、実用化につながるデジタル人材が社内に存在していなければ自動化には至りません。特にデジタル人材は人手不足によって確保が困難になっているため、デジタル人材がいない企業ほど難航しやすいです。
外部のコンサルティングサービスを活用する
デジタル人材をすぐに採用するのが難しい場合、外部のコンサルティングサービスを活用するのも効果的です。 Robo Runnerでは、RPAやAI導入・開発支援を専門家が伴走しながら提供しており、Excel業務のVBA自動化など幅広い業務に対応できます。外部の知見を取り入れることで、短期間で成果を出しやすくなります。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
業務自動化を実現|7つのメリット
デジタルツールを用いた業務自動化には、大きく分けて7つのメリットがあります。
1.従業員配置の最適化
業務自動化によって従業員配置の最適化が実現できます。例えばこれまでバックオフィス業務にのみ従事していた従業員も、デジタルツールによる自動化を通じて企業のコア業務にリソースを充てることができます。
これまではルーティン業務の従事によってキャリアアップを諦めていた従業員も、自動化を機に別の部署での活躍が見込めるようになれば、知識や技術の底上げを通じてキャリアアップの実現につなげられます。
2.コスト削減
人手不足の影響を受けている従業員がすでに存在する場合、1人あたりの業務量が膨大に増えている可能性があります。業務自動化の実現によって、従業員1人あたりの業務量を減らすことができるため、残業代や休日出勤に発生していた人件費の削減にも期待できます。
3.ヒューマンエラーの削減
どの業務を自動化するかにもよりますが、仮にルーティンワークの自動化を実現させた場合、ヒューマンエラーの削減にも期待できます。例えばExcelを使用したデータ入力をRPAツールで自動化した場合、一定の速度で正確性を保った業務完遂を実現可能です。
4.人手不足への対応
デジタルツールでの業務自動化が実現すれば、限られた従業員でも無理なく既存業務に対応することができます。例えばAI-OCRとRPAツールの併用によって請求書や発注書などの入力作業を自動化できるため、業務量の削減と労働時間の短縮につながります。手間と労力が掛かる業務ほど自動化することで、必然的に人手不足に順応する環境を構築できます。
5.生産性の向上
デジタルツールを用いた業務自動化は、生産性の向上にも期待できます。例えばデータ収集・分析を生成AIで代替することで人間よりも正確かつ迅速に進められるため、業務スピードだけでなく従業員1人あたりの生産性向上にもつながります。
6.市場競争力の強化
多くの企業が抱える労働力不足をデジタルツールによる自動化で補うことができれば、企業の自律的な成長を支えることにもつながります。特にRPAツールによるルーティンワークの自動化によって、人手不足問題を解決へと導きながら企業の市場競争力強化も実現できます。
7.従業員・顧客の満足度向上
既存従業員にとって人手不足による業務量の増加やルーティンワークにおけるやりがいの低さ、適切な評価を得ることの難しさは深刻な課題のひとつですが、デジタルツールを通じて「ロボットができる業務はロボットに、人間にしかできない業務は従業員に任せる」といった環境構築を目指すことで従業員満足度の向上につながります。
また、人の手が欠かせない業務ほど従業員を配置する環境を意識できれば、製品・サービスの品質向上につながり、結果的に顧客満足度の向上にも期待できます。
業務自動化を進める際のデメリット
業務自動化を進めるにあたっては、以下のデメリットを念頭に置きましょう。
- 初期・ランニングコストの発生
- トラブルによる業務中断の可能性
- 雇用の減少
特にデジタルツールは導入・運用費用が高額になることが多く、価格によってはなかなか踏み切れないこともあります。コスト面をみると自動化における唯一のデメリットともいえますが、費用対効果を考えることでデジタルツールの導入が自社にとって最良かどうかを判断できます。
例えばデータ入力業務の自動化を検討する場合、年間費用を算出し、予想されるツール導入費用と比較検討してみましょう。データ業務に掛かる年間費用よりもツール導入に掛かる費用が下回る場合、自社にとっては費用対効果が高いと考えることができます。
価格だけをみると高額に感じてしまいますが、これからの企業には働き方改革やDXの推進が求められていることを踏まえ、費用対効果を考えた検討を心がけましょう。
関連記事:業務効率化に対する補助金はある?種類や要件、申請手順を解説
導入検討の前に!業務自動化の業務例
デジタルツールを中心に加速する業務自動化ですが、具体的にどの部署のどの業務で自動化できるのでしょうか。デジタルツールを導入検討する方へ、ここからは業務自動化の業務例について解説します。なお、この項で触れる各ツールの詳細については次項で解説します。
1.経理業務
経理業務で自動化できる業務は下記の通りです。
- 請求データの転記
- 資産管理
- 入金・支払確認など
経理業務は企業のなかでもルーティンワークが多い部署であるため、RPAなどを活用することで自動化できます。
関連記事:経理業務の効率化方法5選|メリットや注意点、成功事例を徹底解説
2.人事業務
人事業務で自動化できる業務は下記の通りです。
- 勤務時間の入力・編集
- 給与明細の作成
- 人事考課の作成
人事業務は勤怠データに基づいた給与の自動計算や明細発行、打刻データの集計などが多いため、マクロやRPAの活用によって自動化できます。
関連記事:採用業務の効率化方法6選|採用時の課題や自動化に役立つツールを紹介
3.総務業務
総務業務で自動化できる業務は下記の通りです。
- 備品管理
- 文書管理
- 各種申請処理
総務業務では、社内で使用する備品の管理をはじめ多くの文書管理が行われます。こうした業務は、AI-OCRで書類をデジタルデータ化しRPAツールで自動入力させることで効率よく進めることができます。
4.営業業務
営業業務で自動化できる業務は下記の通りです。
- 顧客情報の入力・管理
- 見積書作成
- 顧客ニーズの分析
名刺などによる顧客情報の入力はAI-OCRとRPAの併用によってデジタルデータ化・自動入力が可能です。営業戦略の策定に際して顧客ニーズの深掘りを行う場合、生成AIを活用することで迅速な情報収集・分析を実現できます。
5.販売・倉庫業務
販売・倉庫業務で自動化できる業務は下記の通りです。
- 受発注管理
- 在庫管理
ECサイトを利用している場合、RPAの活用によって注文情報を自動取得し、社内の受発注システムに自動入力されるため、ヒューマンエラーを減らすことができます。また、ECサイトと社内の受発注システムのAPI連携によって、注文が入った瞬間にリアルタイムで反映され、自動で在庫を引き当てることも可能です。
6.全社共通業務
全社で自動化できる業務は下記の通りです。
- データ集計・レポート作成
- 承認フロー
これらの業務はRPAやAPI連携、マクロやワークフローシステムの活用によって自動化できます。例えば承認フローは、ワークフローシステムとRPAの連携によって実現できます。具体的には、ワークフローシステムで承認された各書類の内容を、RPAで自社基幹システムなどに自動入力させるなどです。
このように、さまざまなツールの導入・併用によって多くの日常業務を迅速かつ正確に管理することができます。
業務自動化を実現する方法
業務自動化を実現する方法としては、以下7つの方法が有効です。
- RPA
- マクロ
- AI
- チャットボット
- OCR
- ワークフローシステム
- システム間のAPI連携
業務自動化の実現を検討する方は、それぞれの特徴について押さえておきましょう。
RPA
RPAは、定型的・反復的な業務をロボットで代行できるツールです。例えばWebサイトからのデータ抽出やExcelへのデータ入力、取引先や社内メールの送信作業はRPAで自動化できます。なおWindowsユーザーであればMicrosoft Power Automate Desktopを無料で使うことができます。
関連記事:自動化ツール(RPA)とは?おすすめの16種類や選び方、導入の注意点を解説!

\ RPAを導入するならまずはこれ! /
マクロ
マクロはExcelやAccessなどのMicrosoft Office製品に内蔵された機能で、パソコン上の一連の操作を記録し、ショートカットキーやクリック操作で繰り返し実行できます。日常的に行う集計・データ入力作業を手軽に自動化できるため、プログラミング知識がない方でも安心して活用できる手頃さがあります。
関連記事:Excelのマクロでできることとは?VBAとの違いや使い方を解説
AI
AIは人間のように学習を通じて判断・予測を可能にする最新技術です。バックオフィス業務ではメールの自動返信用テンプレートの作成や会議の議事録作成、データの収集・分析を任せることができます。AIの活用によって従来の業務時間を大幅に短縮できることに加えて、効率化・自動化を実現可能です。
関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介
チャットボット
チャットボットは、Webサイトや社内システムへの導入によって定型的な問い合わせを自動で対応してくれる最新システムです。カスタマーサポートにチャットボットを導入すれば、24時間365日顧客からの問い合わせに自動対応できるため、顧客満足度の向上にも期待できます。
関連記事:AIチャットとは?活用方法やメリット・デメリット、使用上の注意点について解説
OCR
OCRは、紙媒体に記載されたテキストをスキャナーで読み取り、デジタルデータに変換する技術です。OCRの活用によって、紙媒体の内容の手入力を省くことができるだけでなく、入力ミスの削減にもつながります。
また、近年ではAI技術を搭載したAI-OCRの誕生により、定型・非定型フォーマットの読み取りにも対応しています。AI-OCRとRPAを併用すれば、複雑なテキストを正確に読み取るだけでなくRPAが自動で必要フォーマットに入力(転記)する環境が実現し、さまざまな業務自動化に期待できます。
関連記事:OCRにはどんな機能がある?AI-OCRとの違いや導入手順について解説
ワークフローシステム
ワークフローシステムは、書類の各種承認作業を電子化し、システム上で管理できる技術です。申請・承認・管理までの可視化が実現し、どの工程で滞っているかを一目で確認することもできます。承認作業がスムーズに進むだけでなく、書類紛失や業務停滞の防止にもつながります。
システム間のAPI連携
APIは、システム間での情報共有を実現するための技術です。例えば販売管理システムと会計システムをAPI連携させれば、販売データの自動入力が実現し、二重入力やヒューマンエラーを防ぎながら情報を適切に管理できます。
業務自動化を成功させる8つのポイント
業務自動化を成功させるためには、下記8つのポイントを参考にしましょう。
目的を明確にする
業務自動化を成功させたいのであれば、自動化の目的を明確にしましょう。
- なぜ自動化するのか
- 自動化で何を解決させたいのか
- どのような効果を得たいのか
こうした項目を具体的にすることで導入後の効果について判断しやすくなります。例えばExcelによるデータ入力の自動化を検討する場合、その背景には従業員の労働負担や残業・休日出勤の増加、属人化などがあるでしょう。導入背景を改善目的に設定することで、例えば残業・休日出勤の減少がみられば効果は出ていると判断できます。
自動化の対象範囲を決める(絞る)
自動化を図る上では、対象範囲を決める(絞る)ことが大切です。いきなり全ての業務を自動化させた場合、各部署・各業務に混乱を招き、業務の遅延・停止を余儀なくされる恐れがあります。まずは高い効果が見込まれる業務、あるいは自動化への切り替えをスムーズに行える定型的な業務からはじめると混乱を最小限に抑えることができます。
費用対効果を判断する
自動化にあたってはデジタルツールの導入が欠かせません。仮にAPI連携を実施するとしても、自社基盤システムとの親和性の高いツール導入を検討する場合もあります。ツール導入を変革に向けた投資と捉え、投資コストに見合ったリターンが得られるかどうかを確認した上で検討しましょう。
無料トライアルは積極的に活用する
多くの自動化ツールには無料トライアルがついています。無料トライアルの利用によって、使用感や利便性、自社基盤システムとの親和性について把握した上で検討できます。業務自動化を成功させるためにも、無料トライアルは積極的に利用し、自社に最適なツールを選定しましょう。
スモールスタートを心がける
小規模な自動化からはじめることで成功体験を積み重ねることにつながります。仮に経営層に対して組織的な自動化を打診する場合も、スモールスタートによる成功体験があることで具体的な数値を用いた説明を実現できます。
デジタル人材の育成・確保を行う
業務自動化にはデジタルツールの導入・活用が欠かせないことから、デジタル人材が不足している場合には、育成・確保にも注力しましょう。例えば自社従業員をデジタル人材として育成する場合は、外部リソースを活用し、デジタル人材のプロに研修を依頼することで従業員の知識の底上げにつながります。
関連記事:DX人材に必要なスキルとは?育成方法やマインドセットを徹底解説
従業員配置の最適化を図る
自動化を通じて定型的・反復的な業務が削減された後は、従業員配置の最適化を図りましょう。例えばAIによって情報収集や分析が迅速にできたとしても、顧客ニーズを深掘りする業務は自社製品・サービスを取り扱う従業員にしかできません。デジタル技術がどれだけめまぐるしく発展していても、人間の心を理解する能力は不足しているからです。
細かな情報収集・分析ができたとしても、その情報を適切に取り扱えるのは従業員であることから、自社製品・サービスの品質に関する業務やクリエイティブな業務などに従業員を配置することで、顧客満足度の向上などさまざまなメリットに期待できるでしょう。
必要に応じて外部リソースを頼る
デジタルツールの導入・運用にあたっては何かとトラブルがつきものです。こうした問題を迅速に解決へとつなげ、安定的な自動化を実現させるためには、必要に応じて外部リソースを頼ると安心です。
Peaceful Morningでは、RPAやAI開発経験が豊富なプロによるツールの選定・導入・運用のサポートが受けられるサービス「Robo Runner」を提供しています。パソコン画面を共有しながら技術的な相談ができる月4時間のオンラインサポートも利用できるため、疑問や不安を解決しながら運用できます。
また、多くの労力や時間が掛かる現場へのヒアリングや業務データの分析も同サービスで利用できるため、属人化や効率を下げている業務プロセスを明らかにしながら最適なツール選定を実現できます。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
まとめ
総務や経理をはじめとするバックオフィス業務の自動化は、日常的な業務負担を軽減につなげ、企業全体の生産性向上に期待できる取り組みです。現状把握やデジタル人材の育成・確保に課題はありますが、自動化の目的を明らかにした上でスモールスタートすることで、自動化を成功へとつなげられます。
業務自動化についてデジタルツールに精通したプロに相談したい方や、具体的なツールについて把握したい方は、ぜひこの機会にRobo Runnerへお気軽にご相談ください。

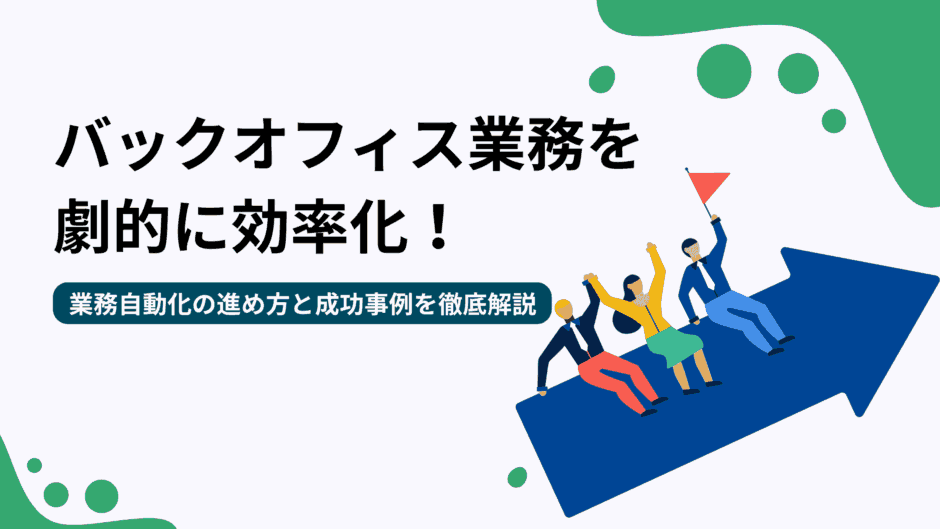
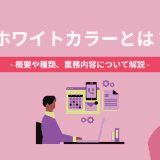

コメントを残す