発注書や請求書を中心とした紙媒体のやり取りは、事業成長とともに確実に増え続けます。会社法や消費税法、雇用保険法などによって書類の保存期間も異なり、また電子帳簿保存法(電帳法)についての課題もあることから、総務担当者や経理担当者の方のなかにはペーパーレス化を検討している方も多いでしょう。
この記事では、「書類を探すのに何時間もかかってしまう」「保管スペースが足りない」といったお悩みを持つ業務担当者の方に向けて、ペーパーレス化の概要と現状、重要性やメリットについて解説します。ペーパーレス化の詳細について押さえ、書類の課題解決へとつなげましょう。

\ AI-OCR無料トライアル実施中 /
目次
ペーパーレス化とは
事業では発注書や受注書、請求書や契約書など多くの書類のやり取りが行われますが、こうした紙書類の電子化を図ることをペーパーレス化と呼びます。単に紙媒体を電子化するだけでなく、パソコン上で編集・管理・共有がスムーズにできるメリットがあることから、業務効率化やコスト削減に期待できます。
ペーパーレス化の一例としては、従来の紙書類をスキャナーで読み取りPDFなどの電子データに保管する方法や、Microsoft OfficeのExcelやWordを使い、最初からデジタルデータ向けに作成する方法があります。
ペーパーレス化の現状
ある調査によると、2022年の時点ではアンケート対象企業の約半数がペーパーレス化に取り組んでいるようです。コロナウイルス感染症の世界的な蔓延によって多様な働き方が注目を集めた時期でもあり、また2019年に順次施行された働き方改革などの影響を受けて、現在はさらに増加していると考えられます。
日本のビジネス環境が大きく変化したことでペーパーレス化は着実に増加していますが、なかにはコスト面や紙書類の電子データ化によるITリテラシーの会得・向上などの課題により難航・失敗している企業も一定数存在します。この点については後述します。
参考:【リサーチ】「ペーパーレス化に伴う2023年度予算」に関する調査 – paperlogic
3つのシーンで見るペーパーレス化の重要性
多くの企業で推進されているペーパーレス化ですが、そもそもなぜ必要とされているのでしょうか。ここからは、3つのシーンで分けた場合の重要性について解説します。
経営面
経営面では、社内で取り扱う紙書類の取り扱いを電子化に切り替えることで、業務効率化やコストカットできる点が挙げられます。保管庫に探しに行く手間や探し出す時間、労力をなくすことができるほか、他部署とのやり取りもスムーズになります。
仮に紙書類の保管スペースをレンタルしていた場合、レンタル費用も削減できます。電子データの取り扱いが定着されればリモートワークなど多様な働き方にも対応できるため、働き方改革の推進にもつながります。
環境面
環境面では、紙生産における森林伐採・破壊や大量生産・廃棄で生じる大量の二酸化炭素削減が挙げられます。なかでも二酸化炭素の大量発生は地球温暖化の大きな原因でもあるため、ペーパーレス化によって環境保全につながることは、紙書類を多く取り扱う企業にとって重要度が高いといえます。
法令面
法令面では、従来の電子帳簿保存法が改正され、電子データで受領した帳票類は紙書類にせずそのまま保存することが原則化されました。そのため、電子データから紙書類へと印刷していた企業にとっては従来とは異なる環境への再構築が求められています。
ペーパーレス化が難航・失敗する理由
ペーパーレス化の背景や目的は企業によって異なりますが、場合によっては難航・失敗することもあるようです。具体的には、下記のような理由が挙げられます。
初期・ランニングコストがかかる
ペーパーレス化実現にあたっては、初期費用やランニングコストがかかることがあります。例えば新たにスキャナーを買い替える場合、全部署用に買いそろえる必要があるため、高額な費用がかかることが予想されます。また、電子帳簿保存法に則したシステムの導入にあたっても、別途費用がかかるでしょう。
印刷代や保管スペースのレンタル費用が節約できるとはいえ、機器の買い替えやツール導入におけるコストが膨大にかかるとなれば、経費捻出が難しい企業にとっては難航する理由になってしまうでしょう。
従業員のITリテラシーの差
ペーパーレス化は多くのシーン・従業員にメリットをもたらす取り組みではありますが、IT関連に苦手意識を持つ従業員からすれば働きにくさを感じる可能性もあります。
仮に電子データに関する取り扱い意識が不足していた場合、適切なやり取り・管理ができないことが予想され、実施が難航する場合もあります。
システムトラブルへの懸念
ペーパーレス化はデジタルツールを使用することが基本であるために、システムトラブルへの懸念が強いと難航する場合があります。特にデジタル人材が不足する企業であれば適切な運用・管理ができないと考え、データの紛失・損失を危惧した結果ペーパーレス化を断念する場合もあります。
ペーパーレス化に対する認識不足
ペーパーレス化によってどのようなメリットがあるのか、さらにはペーパーレスとは何なのかについて適切に理解していない点も難航・失敗する原因のひとつです。紙資料のままでも業務は遂行できるため、重要性を感じていないことが理由と考えられます。
世界的にデジタル化が進み、日本企業も後れを取らないようアナログ業務からの脱却は欠かせない企業課題ともいえます。ペーパーレス化を成功へと導くためには、重要性について説明を行い、浸透させていくことが大切です。
視覚的な問題
紙資料と比較して見えにくい点も難航・失敗に至る原因です。特に大人数で会議を行う場合、全員が同時に同じ資料を見る必要があれば、大きめのディスプレイを別途用意しなければならず、さらにコストがかかることが予想されます。
新たな環境構築を前に多くのコストがかかるだけでなく視認性も悪いとなれば、ペーパーレス化に必要性を感じられず途中で断念する可能性があります。

\ AI-OCR無料トライアル実施中 /
ペーパーレス化で得られる10のメリット
ここからはペーパーレス化における10のメリットについて解説します。詳細を押さえ、全社に重要性を浸透させましょう。
1.印刷コストの削減
ペーパーレス化によって印刷コスト削減につながります。印刷用紙やインクに加えて、プリンターの設置数も減らすことができれば、リース代や保守運用コストも削減できます。また、紙書類の場合、取引先や顧客への発送費用もかかることから、これらをペーパーレス化で削減できることは大きなメリットといえるでしょう。
2.書類の検索・共有が容易になる
ペーパーレス化を実現できれば、パソコンやUSBメモリ、クラウドサービスなどで管理できるため、必要な書類を素早く取り出せます。特に創業当初からの紙書類を保管する企業であれば必要書類を探す際に時間がかかるため、業務効率を下げている可能性が考えられますが、ペーパーレス化によって業務効率化につながります。
また、書類の内容は電子データ化されているため、各部署間でのやり取りもメールやチャットツールなどで容易に共有できる点もメリットです。
3.作業時間の短縮・カットにつながる
紙媒体であれば保管スペースへ移動したり探す手間が生じたりと、何かと時間が掛かってしまうことが挙げられますが、ペーパーレス化の実現によっていつでも必要なときに取り出すことができます。例えばパソコンのフォルダで管理していれば、メールやチャットツールを通じて他部署の従業員に共有することも可能です。
また、全社共通で活用するクラウドサービスに預けておけば、いつでもどこからでも誰でも必要な時にデータをダウンロードすることもできます。
4.保管場所の心配が不要になる
保管スペース確保における心配が不要な点もメリットです。社内を一部増築したり改装したりする必要がなくなるため、取引先や顧客の増加によって取り扱う書類が増える場合でも、場所を取ることなく保管できます。仮に保管スペースをレンタルしていた場合も、ペーパーレス化によってレンタル費用の削減にもつながります。
5.働き方改革に対応できる
電子データはオンライン上で取り扱えるため、リモートワークを中心とした多様な働き方に対応できる点もメリットです。仮に上司が出張中でも、確認を急ぐ書類を電子データ化していれば、メールやチャットツール、クラウドサービスなどを使えば速やかな確認も実現できます。
6.環境保全につながる
ペーパーレス化の実現によって森林伐採や大量生産・廃棄で発生する二酸化炭素の削減にもつながります。紙生産が森林伐採の主たる原因ではないとされていますが、紙資料の削減が世界各国で浸透すれば必要な木々を残すことにつながるでしょう。
7.企業イメージの向上に期待できる
ペーパーレス化を通じて自社が環境保全やサステナビリティに取り組んでいることをアピールできます。自社の業務環境に留まらず地球環境の保護にも貢献している企業という認識が広まれば、企業イメージの向上にもつながり市場競争力強化にも期待できるかもしれません。
8.DX推進が加速する
ペーパーレス化はDXを推進するための基盤にもなり得ます。紙書類の情報はスキャナーで電子化したあと、ITシステムやツール、サービスと連携しながら利用することになります。こうした環境を構築するためには親和性の高いデジタルツールの導入が不可欠となり、ごく自然な形でDXへ踏み切れる点もメリットです。
9.業務の効率化につながる
企業では申請書類や請求書類、稟議など、さまざまな書類がやり取りされていますが、紙資料のままだと、郵送後、到着するまでの間にタイムラグが生じ、承認作業までに数日掛かってしまいます。ペーパーレス化によってこれらを電子データ化すれば、各種手続きを効率的に進められます。
10.セキュリティの強化
紙資料のままだった場合、セキュリティが物理的な対策までで終わることが多く、人的ミスによっては紛失や盗難に遭う可能性が否めません。ペーパーレス化によって、紙資料が電子データ化されていればアクセスや閲覧に関する権限設定が行えるため、紛失や盗難被害リスクを最小限に抑えることができます。

\ AI-OCR無料トライアル実施中 /
ペーパーレス化に有効なシステムの一例
ペーパーレス化の実現に向けて、企業はどのようなシステムを使えばよいのでしょうか。ここからは有効なシステムの一例について解説します。
ワークフローシステム
ワークフローシステムは、申請処理や稟議などの手続きを電子化するシステムを指し、申請から承認までのフローをシステム上で完結できる特徴があります。承認作業に必要な押印もシステム内でのサインで済むことが多いため、場所や時間を気にせず手続きを進められます。
従来は「申請書の発送 → 担当者による確認 → 承認」という紙ベースのフローが当たり前でしたが、ワークフローシステムを導入することで大幅な業務効率化を実現できます。結果として、承認スピードの向上やペーパーレス化によるコスト削減など、企業全体の生産性向上につながるでしょう。
オンライン文書管理サービス
オンライン文書管理サービスは、クラウドサービス上に電子化データを保管し、業務に関わる従業員で共有できるサービスを指します。パソコンをはじめ、スマートフォンやタブレットなどさまざまな端末を使ってアクセスできることから、電子データの保管・管理に最適です。
サービスによって特徴が異なりますが、なかにはアクセス権限の詳細設定に対応したものやアクセス履歴を参照できるサービスも多く展開されています。
クラウド勤怠管理システム
クラウド勤怠管理システムは、従業員の打刻管理や勤務時間の集計作業をオンラインで完結できるシステムで、タイムカードをはじめとした紙媒体の申請業務を大幅に削減できる特徴があります。サービスによっては有給休暇の申請・承認作業や日数管理などもシステム上で行える場合があり、勤怠管理の効率化向上に期待できます。
オンライン請求書管理サービス
オンライン請求書管理サービスは、システム内で作成した請求書をPDFデータで出力し、メールやチャットツールなどでの共有・送付や支払処理の進行に対応したサービスです。請求書の印刷工程を省けるほか、多様なフォーマットの請求書も一元管理でき、印刷代や郵送代、手続きに要する人件費なども大幅に削減できる特徴があります。
電子契約システム
電子契約システムは、システム上で契約締結できるサービスを指し、送付・確認・編集・受領をオンライン上で一括で行えます。サービスによっては紙と電子データの契約書も電子データとして保存できるものもあり、自社の業務環境に合わせて選ぶことで業務の効率化、利便性の向上につなげられます。
AI-OCR
AI-OCRは、AI技術を搭載したOCR(光学文字認識機能)を指し、手作業で行うことが多い伝票の入力作業を効率化できる特徴があります。自動化ツールとも呼ばれるRPAと組み合わせて使うことで、AI-OCRで読み取った紙資料の内容をRPAでExcelやWordなどに自動で入力でき、定型的・反復的な業務の自動化や生産性の向上、人的ミスの削減につながります。
既存の書類をデジタル化するなら「AI JIMY」
AI JIMYは、定型的・反復的な業務の自動化に対応したAI JIMY Paperbotと、生成AI「GPT-4o」を活かした文字列変換ツールのAI JIMY Converterを展開するサービスです。RPAが標準搭載されているため、速やかにデータ入力の自動化を実現できます。
Peaceful Morningでは、AI-OCRツール「AI JIMY(エーアイ・ジミー)」の正規販売代理店として、導入のご支援を行っています。無料トライアルの提供に加え、サンプル帳票のご提出によって弊社での精度検証も無料で利用いただけます。OCRツールを導入し効率化を実現したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
https://go.peaceful-morning.com/l/1062562/2025-04-30/36yfvr
関連記事:AI JIMYとは?概要や種類、使い方について解説
まとめ
ペーパーレス化は従来の紙資料をスキャナーを使って電子データ化し、印刷コストや郵送コストなどの削減をはじめ、業務の効率化に期待できる取り組みです。必要なときに必要な従業員・部署へ共有できるほか編集作業も容易に行えることから、紙資料のやり取りにかかる時間や労力を減らしたい企業におすすめです。
電子データ化した書類はRPAの活用によって入力の自動化を実現できます。電子データの自動入力について興味をお持ちの企業担当者様は、この機会にお気軽にPeaceful Morningへお問い合わせください。

\ AI-OCR無料トライアル実施中 /


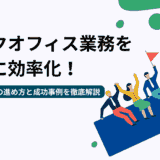
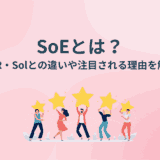
コメントを残す