めまぐるしい発展を遂げるAIによって、人々の暮らしは多様に変化しています。これからますますAI技術は進化を遂げることが予測されており、新たな技術の誕生が期待されています。この記事では、AIの次に来るとされる10種類の技術と、AIの進化によって生まれた最新技術、最先端技術と共存するために欠かせないスキルについて解説します。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
AIの次にくる技術10選
ここではまず、進化するAIによって新たに生まれるであろう、AIの次にくる10種類の技術について解説します。どのような技術が生まれようとしているのか、さっそく見ていきましょう。
1.自動運転|移動の未来を変える技術
AIの進化によって次に来ると考えられている技術として、自動運転が挙げられます。すでに自動車メーカーでは自動運転技術を搭載した自動車を開発していますが、公道を走るためにはまだまだ多くの先端技術が必要と考えられています。
なお、自動運転技術は6段階に分類され、各段階に定義が設けられています。
|
レベル0 |
運転自動化なし |
運転者がすべての操作を行う |
|
レベル1 |
運転支援車 |
・システムがアクセル・ブレーキ操作あるいはハンドル操作のどちらかを部分的に行う |
|
レベル2 |
運転支援車 |
・システムがアクセル・ブレーキ操作、またはハンドル操作の両方を部分的に行う |
|
レベル3 (限定領域) |
条件付自動運転車 |
・決められた条件下であり、すべての運転操作を自動化 ・ただし運転自動化システムが作動する間もシステムからの要請で運転者はいつでも運転に戻らなければならない |
|
レベル4 (限定領域) |
自動運転車 |
・決められた条件下であればすべての運転操作を自動化 |
|
レベル5 |
完全自動運転車 |
・条件なし すべての運転操作を自動化 |
レベル0からレベル2までは運転者が運転を主体的に行い、レベル3からはシステムが運転を主体的に行う構造になっています。現状の自動運転は主にレベル3相当の実装例が中心で、さらなる技術的進展が求められています。
参考:自動運転はどこまで進んでいますか? | JAF クルマ何でも質問箱
現状と今後の予想
自動運転技術は開発が進み一歩前進しているものの、法制度や基準の整備は道半ばで、枠組みの確立が課題です。現状の法規制は運転者の介入がメインであるため、自動運転の実現や普及にあたっては、法律を抜本的に変えることが必要になるでしょう。
活用例
自動運転技術が実現された場合、単なる自動車に限らずさまざまな業界で応用できると考えられています。公道を走る自動車をはじめ、購入した商品を顧客の希望する場所まで送り届ける物流ロボットや田畑で活用できるロボット農機などがあります。誕生が予測されているこれらのロボットは、いずれも配達ドライバーや農業人口の不足を解決するためです。
どちらも法改正や技術の進歩が欠かせないものですが、AIの進化によっては深刻化する人口不足問題を解決するかもしれません。
2.量子コンピューティング|超高速計算で未来を切り開く
量子コンピューターとは、量子力学の原理で計算を行うコンピューターです。従来機が「0」か「1」で情報を表すのに対し、量子ビット(キュービット)の重ね合わせ状態を利用して計算します。
例えば、コインを投げると裏か表のどちらかが出るのが従来機、裏と表が重なった状態を扱えるのが量子コンピューターというイメージです。量子コンピューターの存在によって摩訶不思議なデータ表示が可能になったことで、膨大な量の計算も一度に実施できるようになっています。
現状と今後の予想
現状の量子コンピューターは、量子の重ね合わせが外乱により崩れやすく不安定だとされています。そのため、エラーを訂正できるだけの技術開発がなされない限り、実用化はまだまだ遠いと考えられています。
活用例
仮に量子コンピューティングが実現した場合、暗号解読や機械学習分野において有効活用が期待できます。このほか、量子化学シミュレーションによって今まででは実現すら難しいと考えられていた新物質の開発も可能になると考えられています。
関連記事:AIによって生まれる21の仕事とは?なくなる仕事やなくならない仕事と理由を学ぼう
3.人工生命|コンピュータ上の生命モデル
人工生命とは、生物学的生命のプロセスをコンピュータモデルやロボットなどで人工的に再現することであり、その研究領域を人工生命研究と呼びます。生命現象における本質や進化、さらには行動原理などを模倣し、生命化学分野に新たな知見をもたらすことを目的としています。
現状と今後の予想
人工生命研究には、ソフトウェアシミュレーションやハードウェアでの実装、化学物質によるアプローチが必要とされています。しかし現状は、開発環境はオープンソースが中心であり、たとえ人工生命が誕生しても悪用されるリスクがあるなど、さまざまな課題が潜んでいます。
また、優秀な人工生命であるほど生物兵器への転用リスクも懸念されており、倫理的な問題が山積みであると考えられます。
参考:超知能が破る「人工生命」のタブー ゲノム学習に残るリスク – 日本経済新聞
活用例
人工生命の活用例としては、シミュレーションゲームや映画、アニメ用のCGが挙げられます。近年では企業と東京大学、大阪大学の研究室で共同開発した人工生命アンドロイドも誕生しています。人工生命が誕生し、今ある数多くの課題を乗り越えられれば、ドラえもんのようなロボットが誕生し、共存できる日がくるかもしれません。
参考:【人工生命】人類は「生命」を作り出せるのか? 進化の仕組みを解明し、さまざまな分野に貢献するための研究領域|スタディラボ
4.マテリアルズインフォマティクス(MI)|AI技術で新たな素材を創出
マテリアルズインフォマティクス(MI)は、AIやディープラーニングなどの情報科学を材料開発に応用し、新素材の候補や最適な製造プロセスを高速・効率的に予測する技術です。
従来の人間の勘や経験に頼った開発とは異なり、データに基づいた開発を可能にし、開発期間の短縮やコスト削減、人間では思いつかない発想によって材料を開発できると考えられています。
現状と今後の予想
現状のMI技術水準では材料開発において適用範囲が限定的であり、研究開発現場の課題解決に直接つながらない場合が多いといわれています。とはいえ、各国政府が主導でMI投資を行っていることで民間企業でも活用事例が増加し、2021年には横浜ゴムがAIを用いた配合物性値予測システムの開発に成功し、タイヤゴムの配合設計に実用化しています。
参考:横浜ゴム、AIを活用したタイヤ特性値予測システムを独自開発
活用例
NECと東北大学は独自のMIを用いて熱電変換デバイスを研究開発し、約1年で効率を100倍に向上させています。このほかENEOSでは、MIの活用によって石油化学基盤の素材開発における膨大なデータ解析を実現させています。
今後はバッテリーや半導体、医療材料など、さまざまな業界・分野での活用が進むと考えられています。
参考:2023年度 日本トライボロジー学会 技術賞を受賞|研究所NEWS & TOPICS
5.人工光合成技術|環境に配慮した燃料の生成
人工光合成は、植物の光合成を模倣し太陽光を化学エネルギーに変換する技術で、「第4の太陽エネルギー活用法」とも呼ばれます。水と光を原料とするため、エネルギーだけでなく有用化学物質を生み出す技術としても期待されています。
現状と今後の予想
人工光合成技術の現状は生産コストなどの課題も多く、実用的なシステムにはまだ到達していません。しかし、技術的・コスト的課題が解決され、順調に開発が進めば、数多くのエネルギー問題を解決できるとも考えられています。そのためには、エネルギー変換効率を高めるための触媒の探索をはじめ、企業にとって利益が見込めるシステム作りが急務となっています。
活用例
人工光合成技術が成功した場合、工場などから排出される二酸化炭素を原料としたプラスチック、化学繊維、合成ゴムの製造に欠かせないオレフィンやメタノールなどの化学品を生成できるようになります。
参考:太陽とCO2で化学品をつくる「人工光合成」、今どこまで進んでる?
6.水素エネルギー|次世代のクリーン燃料
水素エネルギーとは、水素と酸素の反応によって発生するエネルギーのことです。二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーであるため、製造が実現すれば燃料電池自動車や発電などに活用されると考えられています。
現状と今後の予想
水素エネルギーは、世界的に需要・供給ともに増加傾向にあります。資料によれば、2050年の需要は2022年比で約5倍に増加すると予想されています。しかし、現状は安定供給のためのインフラ整備が間に合っていないほか、グリーン水素の低コスト製造技術が実現していないなど多くの課題が表面化しています。
活用例
水素エネルギーが実用化されれば、燃料電池自動車や家庭用燃料電池、水素発電などが実現すると考えられています。水素エネルギーは再生可能エネルギーとの組み合わせによって、環境負荷の低いエネルギーシステムを構築できると考えられています。
7.汎用人工知能(AGI)|人間の思考を備えたAI
汎用人工知能(AGI)は、従来のAIと異なり、人間に近い汎用的な知能を持つAIを指します。AGIは人間に近い汎用的な知能を持つため、あらゆるタスクに対しても独自に学習や経験を積み重ねながら解決できると考えられています。
現状と今後の予想
AGIは人間の知能に非常に近い特徴を持つため、完全に表現することはまだまだ先と考えられています。しかし、AIがさらに進化し技術的進歩もみられれば、さまざまな業界で応用が進むといわれています。
活用例
AGIの活用例としては、医療業界では医師と同じように病気の診断や治療計画を策定すると予想されています。このほか、学習者1人ひとりにカスタマイズした教育指導の実現も期待されています。ただし、人間とほど近い能力を持つため、実用化にあたっては生物兵器への転用リスクなど多くの倫理的課題を解決する対策や法改正が必要となるでしょう。
8.IoT|あらゆるモノをネットに繋ぐ
IoTは、センサーや通信機能を持つ「モノ」をインターネットに接続し、データの送受信や可視化を行う技術です。現状ではスマート家電や産業機器などに広く用いられています。
現状と今後の予想
すでに多くのシーンで人々に用いられているIoTですが、今後は接続可能とする「モノ」がさらに増えると考えられています。インターネットに接続した際、データ収集が行われるようになれば、AI分析を通じてより高度なサービスや効率的なシステムが実現すると予想されています。
活用例
IoTの活用例としては、スマートシティやウェアラブルデバイスによる健康データのモニタリング、工場設備における稼働状況の可視化に用いられることになるでしょう。従来では人間が行っていた業務をIoTによってスマート化できれば、さらなる業務効率の向上を実現できるかもしれません。
9.6G|リアルと仮想を融合する次世代通信
6Gは、5Gのさらに先を行く次世代通信です。超高速・大容量・超低遅延・多数同時接続に加え、物理世界とサイバー空間をシームレスに融合する「サイバーフィジカルシステム」の実現を目指します。
参考:6G通信とは?いつから何が実現するのかを解説 | docomo business Watch | NTTドコモビジネス 法人のお客さま
現状と今後の予想
6Gは現在、研究開発段階にあり、2030〜2040年初頭に実用化されると予想されています。実用化された場合、仮想現実を指す「VR」にて、まるで社内でコミュニケーション活動が行われている感覚でのオンライン会議やリモートワーク環境が整備されると考えられています。
参考:AIが世の中にあふれる6G時代へ「AIのためのネットワーク」をテーマに共同でロボットを開発! | PORT
活用例
6Gの提供がスタートした場合、各地のセンサー・カメラから収集された情報に基づき、被害状況を速やかに把握し、適切な避難指示を出せるといわれています。また、行政手続きやインフラ監視においても自動化や遠隔化が進むとみられ、実現すれば住民にとって安心・安全・柔軟な都市運営につながるでしょう。
10.ゼロトラストセキュリティの実装|「信頼しない」前提のセキュリティ
ゼロトラストセキュリティは「すべてのアクセスを信頼しない」ことを前提とする新たなセキュリティモデルです。ネットワークの内外を問わずすべての通信を検証する環境を構築することでセキュリティリスクを下げることにつながります。
現状と今後の予想
セキュリティリスクの低下を図るべく、現在でも多くの企業で導入検討が進むゼロトラストセキュリティですが、その実現はまだまだ少ない傾向にあります。その背景にはリモートワークやクラウド利用の拡大で従来の境界型セキュリティが限界に達し、多要素認証は進むものの、動的なアクセス制御が追いついていないなど、多くの課題が足かせになっています。
活用例
ゼロトラストセキュリティを実装した場合、アクセスしたデバイスが社内承認が済んでいるものかどうかを逐一チェックできるようになったり、不審な行動を取っていないかを確認できたりと、これまで以上に堅牢なセキュリティ環境を構築できます。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
AIの進化によって生まれた最新技術
AIの進化によって、すでに誕生した最新技術も複数存在します。ここでは代表的な最新技術について解説します。
AIエージェント
AIエージェントとは、ユーザーに代わって自律的にタスクを遂行するAIのことです。従来のAIはユーザーが与えたひとつの指示をこなすことが主流でしたが、AIエージェントは複数のエージェントと連携しながら複雑なタスクをこなすことができる特徴があります。AIエージェントについては以下の記事で解説していますので、興味のある方はこちらも併せてご覧ください。
関連記事:AIエージェントとは?生成AIとの違いや仕組み、メリットを解説
フィジカルAI
フィジカルAIは、現実世界で物理的タスクを遂行できる、ロボットなどに搭載されたAIを指します。例えば製造ラインで製品を組み立てる際にロボットが活用されていますが、この部分を担当するAIがフィジカルAIです。AIがさらに進化することでフィジカルAIの動的機能はさらに複雑になることが予想され、人間が行ってきた作業の多くを代替できると考えられています。
最先端技術との共存に欠かせないスキル
AI技術がさらに進めば、次第に人間ができることは少なくなっていく可能性があります。AIの進化はまだまだ続くことが予想されていることから、共存は避けられないと考えられます。では、進化が加速するAIを中心とした最先端技術と共存する上で、人間はどのようなスキルを高めておく必要があるのでしょうか。
クリエイティブな思考
AIが人間のさまざまな行動に適応しても、人間ならではの創造的思考は代替できません。AIはインターネット上で閲覧・収集できるデータを学習データとしているため、文章や画像、動画の生成はできても、すでに存在しているモノと共通点が多いことがあります。
AIの欠点ともいえる特徴であるため、共存していくためにはクリエイティブな思考や着眼点を高めておくことが推奨されます。
共感力
AIは合理的な判断に優れている特徴がある一方で、人間が持つ感情がないために共感力がありません。人間には心があり、相手を思いやる優しさがあります。共感力は日常生活に限らず、サービス業・教育・介護など多様な現場で求められます。したがって、人間が持つ共感力を高めておくことで、AIでは代替できない業界で重宝されるでしょう。
問題解決能力
AIには苦手とする能力がまだまだ存在します。そのひとつとして問題解決能力があり、特に複雑な要因が絡む問題解決においては人間の柔軟な思考や判断が欠かせません。なかでも新規事業の立ち上げにおいては、状況に応じた対応や組織を俯瞰で見た上での解決策が必要です。問題解決能力に自信がある方は、最先端技術と共存できるスキルがあると考えられます。
倫理的判断力
AI活用が広まるにつれて、倫理的判断力の重要性が増しています。例えばAIが生成したデータにおいて法的に問題はなくても、人件や社会的観点から見たときに不適切であることが少なくありません。AI技術の進化次第では、不適切な出力や判断が生じるリスクもあります。こうしたトラブルを防ぐためには、人間による倫理観に基づいた判断力を高めておくことも大切です。
関連記事:AIリテラシーの概要や注目される理由とは?向上するためのポイントやおすすめの資格も解説
最新技術に通用する知識・技術
AI活用が進めば、社内にさまざまなデジタル技術が導入・運用されていくでしょう。こうした企業は今後ますます増加すると考えられることから、今のうちに最新技術に通用するだけの知識と技術を身につけておくことが大切です。
デジタル技術の活用が迫られるなかで社内リソースに限りがあり実用化が困難と判断される際は、Peaceful Morningが提供する「Robo Runner」をおすすめします。
これまで研修・サポートした人数は500名以上となっており、RPAプラットフォーム・UiPath製品に関するトレーニング提供において、トレーニング受講者数などの観点から最も貢献したパートナーに与えられる「Training Associate of the Year」を2年連続で受賞し、多くのお客様の業務における問題を解決した実績があります。
生成AIを含むデジタルツールの活用による業務効率化をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
AIの次にくる技術には、自動運転や量子コンピューティング、AIエージェントなど多岐にわたります。こうした技術は人々の暮らしやビジネスを抜本的に変える可能性を持つことから、共存が予想される現在のうちに知識や技術を身につけておくことが推奨されます。
デジタル技術の進化がめざましく、各部門での知識面・技術面に不安があるといった課題を抱える企業担当者の方は、この機会にお気軽にPeaceful Morningへご相談ください。弊社の各種サービスから、貴社に最適なプランをご提案いたします。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中

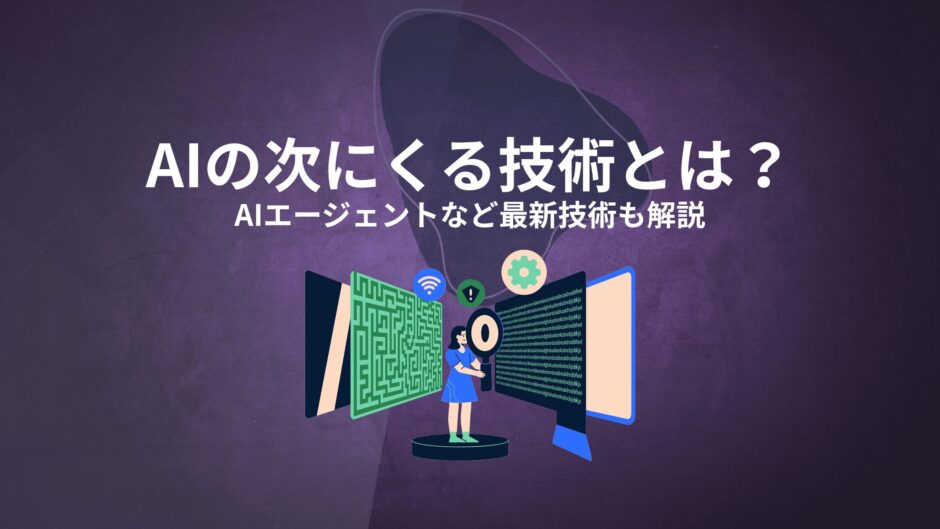


コメントを残す