国のDX推進によってデジタルツールの導入を検討する企業が増えていますが、なかには「どこから手を付けてよいのか分からない」「どのような手順で進めればよいのかわからない」など、DXに対してさまざまな悩みを抱えている方も多いようです。
この記事では、DX戦略の概要と必要とする理由、メリットや実行手順、推進する際のポイントについて解説します。DX戦略に絡むさまざまな要素を本記事で押さえ、自社のDX推進にお役立てください。
DX戦略とは?
DX戦略とは、企業や個人事業主がDXを推進するために策定する戦略のことです。企業および個人事業主は実現させたい目標を掲げ、そのために必要なDX戦略を策定し実施していくことが一般的な流れです。
DX戦略は企業の経営戦略と紐付いており、目標やビジョンなどに基づいて策定されるべきものです。戦略を策定する際は、こちらで解説する手順に沿って進めることをおすすめします。
必要とする理由
DX戦略を必要とする理由は、具体的な策定を決めずに進めることでDX推進そのものが頓挫する恐れがあるためです。実際「成功事例を参考にデジタルツールを導入してみたものの、全社でDXを受け入れる体制が整備されていなかったために理想とする業務変革に至らなかった」といった失敗例が少なくありません。
経済産業省の資料によると、デジタルツールなどを取り扱うベンダー企業は、ユーザーである企業に対し、下記のような現場課題を認識していると明記しています。
- 経営者がITやデジタルの重要性について理解できていない
- 経営者自身の言葉でDXおよびデジタルビジョンを発信していない
- CIOやCDOの権限、役割が弱い
DXの推進が頓挫する理由の多くは、企業経営者がデジタル技術およびツールにおける重要性を理解できていない、CIOやCDOの権限・役割が弱く、経営層に重要性を理解されにくいことなどが挙げられます。
DXを成功させるためには、まず経営層がDXについて理解を深めることが大切です。その上で明確な戦略を策定し、積極的に社内に共有・発信することが成功のポイントといえるでしょう。
なお、DXが必要とされる理由のひとつとして「2025年の崖」もあります。企業が使い続けるレガシーシステムに変革を取り入れない場合、2025年以降には年間12兆円の損失が生まれるとする日本の経済問題です。デジタルツールの重要性は、日本経済にも深く関わっていることは明らかです。詳細については以下の記事でまとめているのでぜひご覧ください。
関連記事:「2025年の崖」とは?起こりうる問題や対応策を解説!
参考:経済産業省|デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会 WG1 全体報告書
DX戦略のメリット
DX戦略には以下のようなメリットがあります。
- 生産性の向上に期待できる
- 顧客体験の向上につながる
- 既存システムにおけるリスクから脱却できる
- 働き方改革を推進できる
ここからはメリットの詳細について解説します。
生産性の向上に期待できる
DX戦略によって、改善すべき業務の洗い出しから評価・分析までを段階的に行えます。改善すべき業務に適切なデジタルツールを導入できれば、無駄な業務が削減され、生産性の向上に期待できます。また、膨大な作業時間を要していた業務もデジタルツールで自動化できれば一定品質を保ちながら生産数の増加にもつなげられます。
顧客体験の最適化につながる
顧客が製品・サービスを発見し、使用するまでの各プロセスで感じられる心理的価値を「顧客体験」と呼びますが、他社製品・サービスとの違いを実感する上で、顧客体験は差別化を決める要素になると考えられています。
例えば、マーケティング戦略では膨大なデータを収集・分析しますが、デジタルツールに任せることで従来よりも速くニーズ調査や市場分析が可能になります。デジタルツールの活用によって顧客1人ひとりのニーズや購買行動も深掘りできるため、従来よりもパーソナライズされた製品・サービスの提供につながります。
また、顧客から届くフィードバックもデジタルツールでリアルタイムに収集・分析し、製品・サービスに反映する姿勢を心がけることで、迅速に対応する企業の誠意が伝わり、顧客満足度の向上にも寄与します。
既存システムにおけるリスクから脱却できる
複雑化、老朽化などが懸念されるレガシーシステムには、放置によって維持コストが高額になったり、運用・管理する人材の属人化によって他従業員では対処できなかったりするなど、さまざまな問題が起きやすいです。こうした既存システムにおける問題も、DX戦略を通じて適切なシステムへ刷新することで、業務効率の向上や生産性の維持につなげられます。
働き方改革を推進できる
DX戦略を元に働き方改革を推進することも可能です。多様な働き方が推奨される近年ですが、DXを活用することでリモートワークやフレックスタイム制度などを円滑に進めることができます。結果的に従業員の離職率の低下や人材不足の解消にもつながることから、DXは働き方改革と連動できる点もメリットと考えられます。
DX戦略の実行手順
DX戦略は下記項目に沿って策定することをおすすめします。また、DXの進め方については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
関連記事:DXの進め方完全ガイド|失敗例をもとに解決策やコツを徹底解説
目標を明確にする
まずはDXを推進するための目標を明確にしましょう。例えばDXを通じて生産性を向上させたい、従業員数や作業時間が多く掛かる業務の効率化を図りたいなどです。このような目標を立てることで、自社課題に適したデジタルツールが選びやすくなります。
社内における課題を抽出する
次に全社に点在する業務を1つひとつ洗い出します。例えば想定よりも多くの時間や労力が掛かっている業務や従業員数が多い業務などは「早急に改善すべき業務」として課題に設定します。
課題の優先順位をつける
業務の洗い出しによっては、早急に解決させたい業務が複数抽出されることがあります。そのようなときは、解決すべき課題に優先順位を付けることで、1つずつ着実に解決へつなげることができます。
例えば5人の従業員で8時間掛けて行うAの業務と、1人の従業員で8時間掛けて行うBの業務では、従業員数の多さからAの業務を優先的に解決させる方がデジタルツールによる効果が高いと考えられます。デジタルツールの導入によってどの程度の効果が見込まれるのかを主軸とすることで、適切に優先順位を付けることができます。
目標値を設定する
デジタルツールを導入しても、すぐに目標を達成できるわけではありません。数回の評価測定と効果分析を実施し、トライアンドエラーを繰り返しながら段階的に目標を達成することが大切です。デジタルツール導入後は、そのツールが自社に適切な効果を与えられているかを判断できるよう数段階の目標値を設定しましょう。
例えば従業員5人で8時間掛けていた業務に対してデジタルツールを導入し、3か月単位でどのくらい時間削減につなげられたのかを見る場合です。このようなときは、最初の3か月は1~2時間程度、次の3か月では2~3時間程度、次の3か月では半分以上時間削減につなげられているかをチェックします。
細かく目標値を設定することで、デジタルツールの選定を中心に、適切な策であったのか、どの程度改善されているのかを満遍なく分析することができます。
なお自社の状況を正しく把握したいときは、経済産業省が推奨するDX推進指標を活用することをおすすめします。DX推進指標とは企業がDXを推進する上で抱えやすい課題や陥りやすい現状を正確に把握することができる自己判断ツールです。詳細については、経済産業省および情報処理推進機構の公式ホームページまたは以下のリンクをご確認ください。
参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構|DX推進指標のご案内 | 社会・産業のデジタル変革
ツールを選び実行計画を策定する
目指すべき目標が明確になった後は、適切なデジタルツールを選び実行計画を策定します。デジタルツールの種類は豊富であることから、設定した目標を成し遂げられるものを選ぶことが大切です。例えば毎日一定時間にデータ入力をしなければならない業務であれば、AIやIoTなどを導入し自動化を図ることが推奨されます。
自動化や効率化を図りたい業務をあらかじめ決めておくことで、自社にとってふさわしいデジタルツールとは何かが明確になり、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
デジタルツールを選定した後は、目標を達成するための推進フローを策定します。推進フローではデジタルツールの導入から評価測定までを1~3か月程度で区切り、一定期間でどの程度目標に近づいているかをチェックすることをおすすめします。評価測定の方法については、次の項をご覧ください。
関連記事:DX化を実現させるデジタル技術とは?事例やメリット、選び方を解説!
導入後は評価測定を行う
デジタルツールの導入後は、どのくらいの効果が得られているのかを判断するため、評価測定を行います。例えば導入から1~3か月の間で目標の4分の1程度まで進んでいるのであれば、デジタルツールの効果が見え始めていると判断し、使用を継続します。
なお、デジタルツールを導入したからといってスムーズに目標を達成できることはほとんどありません。目標に到達できなかったという理由から数か月でDXに見切りを付けるのではなく、数年単位で徐々に目標を達成できるよう、トライアンドエラーを繰り返す姿勢が大切です。
DX戦略を推進するポイント
DX戦略を適切に推進するためには、これから解説する下記のポイントを意識しましょう。
スモールスタートを心がける
DXには優秀なデジタル技術が搭載されているものが多いですが、決して万能というわけではありません。そのため予想していた効果が顕著に見られなくても、早期に失敗と判断せず、長期的な視点で取り組むことが大切です。
長期的に変革するなかでは、コストは最小限に抑えたいと考える方も多いでしょう。これらのことから、DX戦略を推進するためにはスモールスタートではじめ、小さな成功体験を積み重ねることを心がけましょう。
目標値は安易に変えない
あらかじめ設定した目標値に達成しなかった場合、妥協して目標値を下げるケースも少なくありません。しかし安易に目標値を変えてしまうと、最終的な目的がブレてしまい、当初目指していた目標から遠ざかる可能性があります。数か月単位で評価分析を実施しても目標値を達成できなかったときは、データを細かくチェックし成功体験を見つけましょう。
例えば初回の評価分析における目標値が1時間の業務時間削減だったのに対し、実際は40分だった場合です。このような場合、使用する従業員がデジタルツールに慣れるまでに時間が掛かった可能性もあることから、必ずしも失敗とはいいきれないでしょう。これらのことから、目標値は安易に変えず、達成できなかった理由や背景を振り返ってみましょう。
DX戦略に必要な人材を確保する
適切なDX戦略を策定したいのであれば、DXの中枢を担う人材確保が欠かせません。例えば自社に在籍するデジタル技術に詳しい従業員をDX推進部門に配置するなどです。DXに詳しい従業員が複数名いることで、計画通りに進められるほか、経営層に対してデジタルツールの必要性を説明することも可能です。
現在の人材リソースではDX推進部門の設置が難しいときは、PeacefulMorning株式会社が提供する「DX Boost」をおすすめします。DX Boostは貴社に適したDXプロジェクトに最適な人材を最短即日でアサインするサービスです。エンジニアやプロジェクトリーダーなど、優秀な人材を即日提案できるため、DX推進部門の設置も速やかに実現することができます。
関連記事:DX人材に必要なスキルとは?育成方法やマインドセットを徹底解説
DX戦略における注意点
DX戦略を成功させるためには下記の注意点に留意しましょう。
1回で終わらせない
DXは業務の自動化や効率化、最適化に留まらず、企業成長を継続的に支援するための経営戦略です。仮に目標を成し遂げられたとしても、一過性のもので終わらせないようにしましょう。
従業員からフィードバックを受ける
デジタルツールを導入後は、従業員からフィードバックを受けることをおすすめします。実際に使ってみた結果をヒアリングやアンケートで受けることで、デジタルツールや活用方法における課題を見つけることができます。
デジタルツールは優秀な機能が豊富であっても万能ではないため、何のトラブルもなくスムーズに目標を達成できることは稀です。導入後は積極的に従業員から詳細なフィードバックを受け、共有された改善点を全社の課題として共有することで、戦略そのもののブラッシュアップへとつなげることができます。
フィードバックを元に改善を図る
従業員から受けたフィードバックを元に改善を図ることも大切です。フィードバックは実際にデジタルツールを活用した従業員からの素直な意見です。機能性や利便性などを総合的にチェックすることで、デジタルツールと企業の相性を従業員の意見を元に評価することができます。
導入によって利便性が低下したのであれば、既存システムとの相性が悪いかデジタルツールにまだ慣れていないなど、いくつかの可能性が考えられます。経営層はベンダーをはじめDX推進部門と連携を取り、課題を解決しながら企業の変革を目指しましょう。
業務フローやビジネスモデルそのものの変革も検討する
DX戦略における最終的な目標は、デジタル技術の活用によってビジネスモデルを根本から変革し、企業価値を高めることです。そのため、DXにおいては全社に滞留する業務の自動化・効率化・最適化だけでなく、ビジネスモデルそのものを見直すきっかけと考える姿勢も大切です。
まとめ
DXを成功させるためには、自社にとって適切なDX戦略を策定し、その内容を通して実現すべき目標を明確にする必要があります。とはいえ、DXを推進するためには、デジタル技術に精通した人材確保が欠かせません。自社の従業員だけでは不安なときや人材リソースが不足しているときは、この機会にPeacefulMorning株式会社の「DX Boost」をぜひご検討ください。

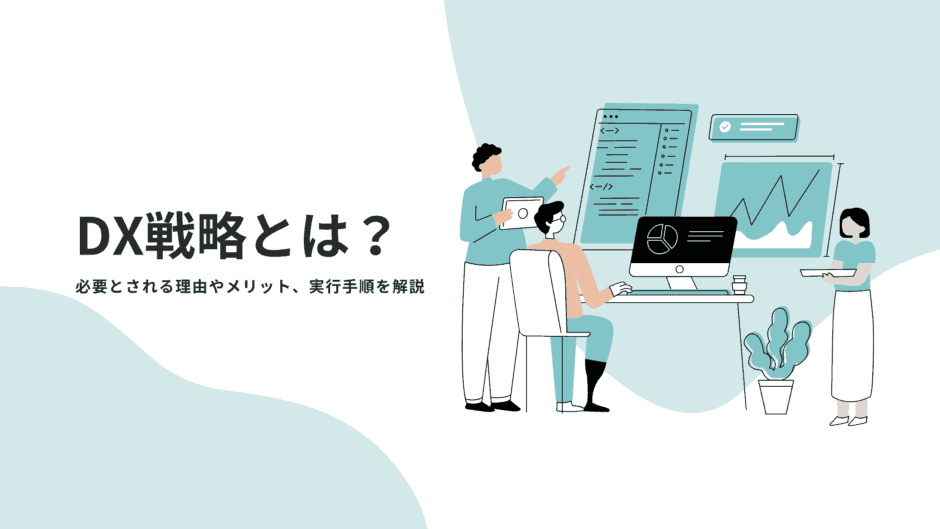



コメントを残す