持続的な成長へとつなげることを目的に、多くの企業では定型的・反復的な業務をRPAツールを用いて自動化を実現させるなど、さまざまな取り組みを加速させています。しかし、RPAのみでは業務の一部分的な自動化に留まることから、業務全体の非効率性を解決できる取り組みが必要とされています。
こうしたときに効果的な概念がハイパーオートメーションです。この記事では、ハイパーオートメーションの概要とRPAの違い、メリットや課題について解説します。
ハイパーオートメーションとは
ハイパーオートメーションとは、生成AIやLLM(大規模言語モデル)、iPaaSなどのデジタル技術を組み合わせて実現させる業務自動化における新たな概念のことです。企業に点在するさまざまな業務プロセス全体を自動化できることから、RPAによる自動化と比べても広範囲という特徴があります。
この概念のルーツはガートナー社が2020年に提唱したものであるものの、業務プロセスを根本から見直し最適化を図るための近年のビジネス社会に不可欠なDXの加速につながる理由から、多くの企業からも注目を集めています。
参考:ガートナー、2020年の戦略的テクノロジ・トレンドのトップ10を発表
用いられる技術・ツールの一例
ハイパーオートメーションは単一のデジタル技術で実現できるものではなく、複数のデジタル技術を組み合わせ、各システム・ツールの特徴を活かすことで高い相乗効果に期待できます。一例としては、下記のようなものが用いられています。
| システム・ツール | 概要 |
| RPA | ・定型的・反復的な業務を自動化するツール・ハイパーオートメーションのなかでも「手」や「足」に位置する |
| 生成AI | ・非定型業務における判断・予測をはじめ、データからのパターン認識を実現する・ハイパーオートメーションのなかでも「脳」に位置する
・OCR(光学文字認識)との組み合わせによって誕生したAI-OCRは、AIの画像・音声認識技術を採用している |
| iPaaS | ・クラウド上にある複数のアプリケーションをシステム間で連携・統合するためのプラットフォーム・ハイパーオートメーションのなかでもデータ連携のためのハブのような役割を担う |
ハイパーオートメーションにおいてはこのほかにもさまざまなシステム・ツールが用いられています。それぞれが相互に連携し、組織に点在するあらゆる業務プロセスをカバーできれば、従来よりも広い部署・業務での効率化、自動化を実現できます。
ハイパーオートメーションとRPAの違い
ハイパーオートメーションと混同されやすい言葉として、RPAが挙げられます。ここからは、RPAとの違いについて解説します。
関連記事:https://rpahack.com/rpa-summary
自動化の対象範囲
ハイパーオートメーションは、さまざまなデジタル技術を活用して広範囲にわたる業務プロセスの自動化を図る概念を指します。一方RPAは、定型的・反復的な業務を自動化へとつなげるツールであるため、自動化の対象範囲に違いがあります。
例えば、Excelのセルに記載された数値を別セルへコピー&ペーストを繰り返す作業は定型的な業務に位置づけられますが、このような作業を自動化するツールがRPAです。一方ハイパーオートメーションは、紙書類に記載された情報をAI-OCRを使って読み取ったあと、RPAツールを使ってExcelの指定セルに自動入力させる仕組みを指します。
重要な判断の実現
RPAは、自動化したい業務をあらかじめ登録し、この内容をひとつのルールとして設定し動作させるという特徴があります。一方ハイパーオートメーションは、「脳」に位置づけられるAI(生成AIを含む)や機械学習、LLMなどとの連携を通じて、単純な操作(動作)に留まらず、従来は人間の判断が伴っていた意思決定の実現も可能です。
技術の組み合わせ
RPAを使用する際は、一般的にひとつのツールを導入し、特定のパソコン操作を自動化します。一方ハイパーオートメーションは、RPAや生成AIやiPaaSなどのさまざまなデジタル技術を複合的に組み合わせて新たな業務変革をもたらすことを指し、RPA単体では実現できなかった複雑な業務も自動化・効率化へとつなげることができます。
ハイパーオートメーションのメリット
ハイパーオートメーションの導入によって下記のメリットに期待できます。
最適化の範囲が広がる
RPAは「データ入力」といった単発の作業を自動化しますが、ハイパーオートメーションは「受注→在庫確認→出荷指示→請求書発行」のような一連の業務フロー全体を自動化します。これにより、単純作業から解放された従業員を、顧客対応や企画立案など、より付加価値の高い業務に配置できるようになります。
企業全体の業務環境が大きく変革されれば、顧客ファーストでの業務体制を構築できます。事務処理から解放された従業員が顧客対応や商品開発に集中できるようになり、製品・サービスの品質向上につながります。その結果、顧客満足度の向上が期待できます。
人的ミス・不正を低減できる
手作業で行われる業務には人的ミスが起きやすいという課題が潜んでいるほか、承認フローが複雑な業務や特定の従業員に権限が集中している場合、不正のリスクがゼロではない点を念頭に置かなければなりません。
ハイパーオートメーションを導入すると、定型的・反復的な業務の自動化や人的ミスの削減に加えて、生成AIによるデータに基づく判断を通じて適切な意思決定を実現できます。
各種システム・ツールによる自動処理はあらかじめ設定したルールに基づいて行われるほか、作業履歴はすべてデジタルデータとして記録されるため、必然的に内部統制の強化やコンプライアンス遵守にもつながり、経営に透明性をもたらします。
生産性の向上
自動化の実現によって従来の定型的・反復的な業務はRPAや生成AI、AI-OCRなどに代替できます。デジタル技術は体調やモチベーションに左右されることがないことに加えて24時間365日稼働できる特徴があります。そのため、従来は数名の従業員で数日費やしていたルーティンワークも、ハイパーオートメーションによって数時間程度で完遂でき、生産性の向上を実現します。
ビジネスモデルを革新できる
ハイパーオートメーションは既存業務の効率化に留まりません。生成AIをはじめとした最新技術を用いることで、ビジネスモデルそのものの革新にも貢献します。例えば、迅速なデータ処理と高度な情報分析、データに基づいた適切な意思決定が実現されれば、顧客ニーズを的確に捉えた製品・サービスへの改善、さらには新たな価値創造につなげられます。
ハイパーオートメーションによって劇的に効率化し新たな業務環境を構築できれば、既存顧客の囲い込みや新規客・見込み客へのアプローチもより広範囲かつ高速で実施でき、競争優位性の確立にも期待できます。
コンプライアンスの強化を実現できる
常に変化する法規制やデータガバナンスの重要性が高まる現代において、ハイパーオートメーションは企業のコンプライアンス強化にもつながります。
例えば自動化された業務プロセスは常に設定したルールに基づいて実行されますが、このルールが変更された場合、履歴やログが生成される仕組みのため、監査業務を容易にします。
組織独自の規制に則したデータ処理などもハイパーオートメーションで自動化できるため、必然的に企業の信頼性強化にも期待できます。
ハイパーオートメーションの課題
さまざまなメリットに期待できるハイパーオートメーションですが、導入は決して容易なものではありません。ここからは、導入前に把握しておきたいハイパーオートメーションにおける課題について解説します。
コストが高額
ハイパーオートメーションは、使用するシステム・ツールが複数必要になるために、コストが高額になりやすいといった課題があります。ルーティン(単一)業務を自動化するRPAと比べても、初期投資やランニングコストが高額になりがちである点はハイパーオートメーションの課題のひとつです。
導入工数が多い
ハイパーオートメーションはRPAと比べても広範囲にわたる業務プロセスの変革を伴うことから導入・運用までの工数が増えやすい点も課題です。特にレガシーシステムだった場合、最新のデジタル技術・ツールとの連携が難しい、あるいは非対応といったトラブルによって実現が困難になる可能性もあります。
セキュリティ対策が必至
レガシーシステムではなかったとしても、複数のシステム・ツールとの連携によっては情報漏洩やサイバー攻撃から守るため、堅牢なセキュリティ対策を講じなければならない点も課題のひとつです。仮に個人情報がサイバー攻撃によって漏洩したとなれば多大な企業損失となり、信頼失墜による経営危機に陥る可能性もあります。
デジタル人材の育成・確保が伴う
ハイパーオートメーションには、RPA開発者に限らず、AIエンジニアやデータサイエンティスト、業務プロセスに精通したデザイナーなど、多岐にわたるデジタル人材の育成・確保が欠かせません。仮にデジタル人材が不足したまま実現に踏み切った場合、システムやツールを適切に運用・管理できず、業務プロセス全体の最適化が足踏み状態となってしまいます。
また、技術的な問題に留まらず、デジタル技術活用による企業変革に対して不安や不満を抱く従業員も一定数存在します。「自分の仕事がデジタル技術によってなくなってしまうのでは」「新しいシステムを使いこなせるか不安がある」といった従業員1人ひとりの懸念に対し、気軽に相談できる窓口の設置や研修プログラムの提供なども検討する必要があります。
従業員とITのバランスを考慮する必要がある
ハイパーオートメーションは、推進にあたっては従業員とITとの最適なバランスについて考えることも大切です。自動化によって多くのメリットに期待できる一方、従業員にとっては自身の役割が減ってしまうことを不安に感じたり、組織的な変化に適応できるのかといった心配を抱えたりすることが考えられます。
- 従業員の業務を奪うものではなく、創造的な業務に従事できるようになる
- 従業員にさらなる付加価値を提供できる環境を構築し、企業力強化を図る
こうした目的を全社で共有することで、従業員の不安を払拭しながら業務の効率化・自動化を実現できます。デジタルで代替できる業務はシステム・ツールで自動化を図り、人間にしかできない業務は従業員に振り分けるといった業務環境が構築できれば、従業員も強いやりがいを感じながら業務に取り組めるでしょう。
ハイパーオートメーションを導入する方法
ここからは、企業にハイパーオートメーションを導入する方法について解説します。
業務プロセスを洗い出す
まずはハイパーオートメーションの対象となり得る業務プロセスを洗い出します。どの部署のどの業務が定型的(あるいは反復的)で、どの業務が非定型的であるかを細かく分析します。その後「Excelのデータ入力業務に関する処理時間を従来の30%削減する」など自動化を通じてなりたい企業像を明確にし、全社に共有します。
ソリューションを選定する
自動化を通じてなりたい企業像を明らかにした後は、ハイパーオートメーション実現に向けたソリューションの選定を行います。
定型的・反復的な業務の自動化であればRPAを、迅速な意思決定を行いながら業務の自動化を図りたいのであれば生成AIを、紙書類の電子化、電子化したデータの自動入力を実現させたいのであればAI-OCRなど、業務プロセスに適したシステム・ツールを選びましょう。
デジタル人材を育成・確保する
次に、ハイパーオートメーションの実現・運用に欠かせないデジタル人材の育成・確保です。自社リソースで完結させる場合には、専門チームの立上げを行い、RPA開発者やAI技術者、プロセスデザイナーを配置しましょう。
社内リソースでの人材確保が難しい場合は、外部企業と連携する方法が有効です。Peaceful Morningでは、企業のDX推進を加速させるサービス「DX Boost」と「Robo Runner」を提供しています。
DX Boostでは、企業へのヒアリングを通してデータサイエンティストやプロジェクトマネージャーをはじめとしたDX推進部門の設置に欠かせない人材を最短即日でご案内しています。
また、Robo Runnerでは、RPAやAI開発経験が豊富なプロからシステム・ツールの選定から導入・運用支援が受けられるサービスとなっており、社内の人材を育成したい場合におすすめです。
自社リソースではハイパーオートメーションまでの道のりが困難だと感じられたときは、ぜひこの機会にお気軽にPeaceful Morningへご相談ください。
実行・効果測定
適切なシステム・ツールの選定が終わり、デジタル人材による導入が済んだ後は自動化・効率化に向けて運用しましょう。1か月、あるいは3か月などの一定期間ごとにハイパーオートメーション実施後の効果測定を行うことで、従来と比べてどの程度の自動化・効率化がみられているのかを適切に分析・判断できます。
まとめ
業務の自動化といえば従来はRPAが一般的でしたが、一部分的な業務にのみ対応する特徴から、業務プロセス全体の改善を図る上では多くの課題がはらんでいました。ハイパーオートメーションはRPAでは解決できなかった組織内の多くの業務プロセスを自動化・効率化できる概念(アプローチ)を指し、DX推進が推奨される日本でも多くの企業から注目を集めています。
しかし実現にあたっては複数のシステム・ツール導入が欠かせなかったり、高額なコストが掛かる、導入・運用までが長期化しやすい、デジタル人材の育成・確保が不可欠であったりするなど、いくつかの課題も潜んでいます。
ハイパーオートメーションの実現に向けて一歩前進を検討される企業担当者様は、この機会にお気軽にPeaceful Morningへご相談ください。自社の業務プロセス診断、最適なツールの選定支援など初期段階からサポートさせていただきます。




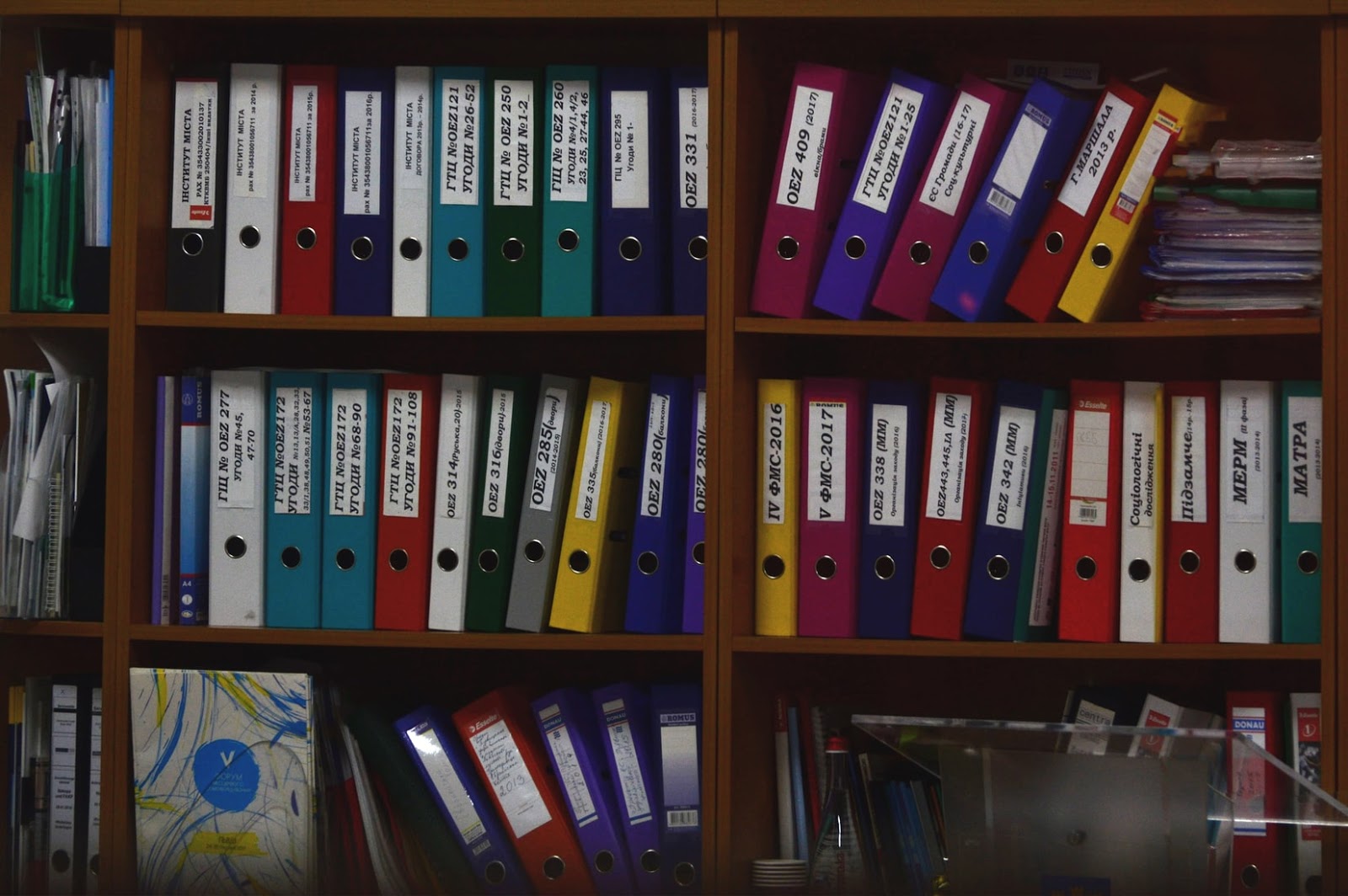
コメントを残す