医療DXとは?概要やメリット、詳しい手順や事例を解説
2024年4月より日本では医師の働き方改革が施行されました。960時間の年間労働時間に加えて100時間未満の月間労働時間に制限するなど、国はかねてから懸念されていた医師の健康状態を守るため、さまざまな取り組みを進めています。
国が後押しする動きには、ほかにも医療DXが挙げられます。少子高齢化による医療機関の人材不足を解消することを目的に国が後押ししていますが、医療機関では「どのように始めてよいのかわからない」「現場スタッフにどのような説明をするべきなのかわからない」などの悩みを抱える方も少なくありません。
そこでこの記事では、医療DXの導入を検討される医療機関へ、医療DXの概要とDXが求められる背景、事例や進め方について解説します。
参考:厚生労働省|診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の特例的な上限水準
医療DXとは?
医療DXとは、医療分野にデジタル技術を取り入れる取り組みのことで、医療サービスの質や提供する際の効率を向上させることを目的としています。具体的な内容としては、政府による「医療DX令和ビジョン2030」に基づき、医療機関でのオンライン予約・診療のほか、AI技術などを用いた院内デジタル化の推進です。
院内デジタル化によって医療機関ではオンライン資格の確認や電子カルテの標準化が浸透し、業務の効率化につながります。また、財源・人材・設備を指す医療資源の効率的な利用や、新薬・新治療法の開発にもデータを活用できることから、医療の質を全体的に高める効果にも期待できます。
参考:厚生労働省|「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム
政府の動向
政府は「医療DX令和ビジョン2030」以外にも、以下のような取り組みも目指しています。
- 診療報酬に医療DX推進体制整備加算を追加
- 全国医療情報プラットフォームの推奨
医療DX推進体制整備加算は、デジタル技術を導入する医療機関に対して、医療DXの推進を評価された場合に加算されるものです。電子処方箋や電子カルテといった情報共有サービスの導入のほか、医療DXに対応可能な体制の確保が評価され、加算される仕組みです。
全国医療情報プラットフォームは、医療機関で取り扱う患者情報を集約し、共有・管理するシステムです。患者情報を集約し、システム上で共有できるようにすることで、全国いつでもどこからでもリアルタイムでの閲覧・編集が可能になります。
参考:厚生労働省|医療DX推進体制整備加算の 算定要件について 厚生労働省保険局医療課
参考:厚生労働省|全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)
医療業界でDXが求められる背景
医療業界でDXが求められる背景には、下記のような理由が挙げられます。
人手不足
医療業界における問題として、懸念されていることが人手不足です。少子高齢化社会に突入した日本では、医療機関を利用する患者数が増加する一方で、医療現場の労働力が減少傾向を辿り、需要と供給が偏った状況を迎えています。
人手不足が続けば、医師1人あたりの診察数が増大し、荷重労働につながる恐れがあります。過重労働が慢性化すれば、次第に医師は退職を余儀なくされ、医療機関そのものが麻痺する可能性も考えられます。
長時間労働
医療業界は他職種と比べて労働環境が整備されていないことから、長時間労働が一般化されていました。さらに、医師をはじめ看護士などのスタッフは、昼夜を問わず患者対応を行わなければならない勤務態勢から、長時間労働になりやすい環境でもありました。
長時間労働に陥りやすい業種ならではの特徴から、2024年4月には医師の働き方改革が施行されています。このような取り組みの浸透によって長時間労働は改善されつつある一方で、夜間勤務による睡眠不足・疲労から作業能力の低下し、医療事故につながるリスクの予防策など、まだまだ多くのシーンで改善が余儀なくされています。
参考:厚生労働省|診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の特例的な上限水準
経営難
少子高齢化によって、若手スタッフの不足や第一線で活躍していた医師・看護師の引退など、さまざまな影響がみられています。その結果、経営難に陥る医療機関が増加している点も医療業界でDXが求められる背景のひとつです。
すでに日本は超高齢化社会であることから、将来の担い手不足や医師・看護師の引退が続けば、閉院を迎える医療機関はますます増え、医療アクセスの悪化が強まると予想されます。
医療DXのメリット
医療DXの導入にあたっては、4つのメリットがあると考えられています。
業務負担の軽減につながる
労働環境は医師の働き方改革によって改善傾向にあります。しかし、医療機関の予約・受付対応など、改善を心待ちにする業務はまだまだ多いのが現状です。オンライン予約システムを導入することで、予約や受付対応をマイナンバーカードなどで受けることができ、業務負担の軽減につながります。
一例としては、マイナンバーカードを使った予防接種の受付業務です。オンラインで接種対象者の情報を確認できるので、カルテを探す手間がなくなり、作業の効率化にもつながります。
また、RPAを導入することにより、現場の業務負担を軽減できます。医療現場でのRPA活用事例については、以下の記事をご参考ください。
関連記事:【業界別導入事例】医療現場におけるRPA導入の効果とは
経営改善・コスト削減
医療DXの導入によって、経営改善やコスト削減にも寄与します。例えば紙カルテを電子化することで、紙カルテに掛かっていた費用を削減できます。このほか、紙媒体で管理していた書類の保管コストの削減にもつながるでしょう。電子カルテの導入によって業務が効率化されれば、人件費も削減できます。
これらのことから、さまざまなシーンでのコスト削減が実現し、経営改善へとつなげられるのは医療DXのメリットといえるでしょう。
チーム医療の活性化
医療DXには、予約管理システムやオンライン診療システムなど、受付業務に限定したシステムに留まりません。例えば透析管理システムと電子カルテの導入・連携によって、診療・透析に関するデータを一元管理できます。
透析管理システムには、透析前後の患者の体重や透析中の循環動態などが反映されます。電子カルテと連携することで、カルテの内容を各チームで共有でき、チーム内での情報共有が可能・円滑になります。
医療サービスにおける質の向上
医療サービスにおける質の向上も期待できます。例えば電子カルテの導入によって、医療チームでのデータの共有・閲覧が実現します。通院歴や病歴、処方歴などのデータをいつでも閲覧できるので、患者情報を知るために要していた時間を、これからは患者と直接コミュニケーションを取れる時間に充てられます。
患者との心理的距離が近くなれば、患者1人ひとりに寄り添った適切なケアの実現も可能になるでしょう。
医療DXの事例
医療DXを導入した医療機関は、国のDX推進によって増加傾向にあります。ここでは5つの事例について、厚生労働省の資料をもとに解説します。
参考:厚生労働省|令和2年度 医師等医療従事者の勤務環境改善の推進にかかるICT機器等の 有効活用に関する調査・研究
勤怠管理システムによる時間把握・管理
静岡県の医療機関では、医師による自己申告での出退勤管理を、ICT機器の導入を通じICカードの読み取りカードでの打刻に切り替えました。
自己申告制であったため、どの医師が何時に出勤・退勤したのか正確な時間を把握できなかった課題をはじめ、平成30年3月に厚生労働省がとりまとめた「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」により医師の在院時間の客観的な把握が必要と判断し、ICT機器の導入に踏み切っています。
具体的には、ICカードを全職員に配布したことに加えて、正面玄関、裏玄関などに打刻機を9台配置しています。その結果、勤務時間に対する意識の醸成につながったほか、医師の早すぎる出勤の抑制や健康管理に対する意識の向上が実現しました。
Web会議システムによるオンライン診療・カンファレンスの参加
福島県の医療機関ではWeb会議システムを活用し、柔軟な働き方を実現しました。導入に踏み切った理由は、育児休業を終えた医師が時短勤務での訪問診療に復帰したところ、時間内での訪問診療カンファレンスへの出席に難しさを感じたためです。
医療機関がオンラインに対応したことで、出勤時間に囚われることなくカンファレンスへの参加が実現しました。また、オンライン診療も可能になり、訪問の際の移動時間を削減し、より多くの訪問診療に対応できるようになりました。
医療支援システムによる情報共有の効率化
愛知県の医療機関では、同院では電子カルテに表示された情報を看護師がメモ用紙に書き込み、患者のベッドサイドに貼り付けるといった作業が慣例となっており、医師の指示が変わるごとにメモ用紙に転記する作業が増えていました。状況によっては、転記作業のために残業する日も発生していました。
医療支援ピクトグラムシステムの導入・併用によって、医師の指示が変わっても転記する作業が不要になりました。また、患者の安静度などに関する最新情報を正確かつリアルタイムで共有できるようになり、安全で質の高いケアの提供を実現しています。
遠隔システム導入による相談体制の確保
愛知県の医療機関では、専門医不在における問題をICT機器などの導入で解決へとつなげました。二次救急の告示病院ではあるものの「断らない医療」という方針のもと、三次救急も一部受け付けているため、年間2,000件以上の救急搬送に対応しています。
集中治療専門医がいないことから、医師は場合によって専門外の重症患者の治療に当たることもあり、医師は治療の妥当性に、その医師につく看護師は医師の診断が的確かどうかについて不安を感じ、周囲に相談できないケースがありました。
この問題を解決すべく踏み切ったのが、遠隔集中治療システムの導入です。24時間365日相談可能な体制を確保したことで、医師・看護師は的確なアドバイスを受けられるようになりました。遠隔の専門医とは電子カルテや生体モニターの端末画面を共有でき、患者情報を一緒に確認しながら的確な診療につながり、医療チームの不安の払拭を実現しました。
AI問診による対話時間の増加
東京都の診療所では、AI問診の導入を通じて、患者との対話時間の増加につなげました。同診療所の院長は、頭痛専門医として慢性頭痛患者の診療にあたっています。慢性頭痛、特に偏頭痛では、光過敏や音過敏、嗅覚過敏や悪心・嘔吐などの症状の有無で診断することから、症状の有無についてクイズ形式にできないか検討していました。
そこでAI問診を導入したところ、診察前に症状などを入力してもらうことで、予備的な問診が完了し、頭痛に関する説明時間など、患者と対話する時間を増やすことに成功しています。
医療DXの進め方
医療DXを導入する場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。
- 現状の課題を明確にする
- 適切な人材を探す
- 課題に即したツールを探す・導入する
- スタッフへ共有する
- 段階的に使用し効果を測定する
- スタッフからフィードバックを受ける
- フィードバックをもとに改善する
ここからは、上記7つのステップについて解説します。
現状の課題を明確にする
医療DXを導入するためには、医療機関が抱える課題を明確にすることが大切です。闇雲にデジタル技術を導入しても、解決すべき課題が明確でなければ、導入による効果を実感できません。
アナログな業務が慣例化しているために残業する看護師が増えている、スタッフの数が多く患者の情報共有がうまくできていないなどの悩みがあれば、まずは紙に書き出してみましょう。チーム内で課題や悩みをヒアリングしてもよいかもしれません。
抽出された悩みや課題、問題には優先順位を付けることで、医療機関が抱える課題・問題の洗い出しと早期解決を目指すべき問題を区別でき、適切なデジタル技術について考えることができるでしょう。
適切な人材を探す
医療DXにはさまざまなデジタルツールが展開されていますが、スタッフのITリテラシーが不十分だとデジタルツールを活用することができません。つまり、IT技術に詳しい人材の育成・確保や、ITリテラシーの向上を目指した研修が必要です。また、導入にあたっては医療DXに詳しいベンダーなど外部人材との連携も必要になります。
DXに詳しい人材を探すのであれば、PeacefulMorning株式会社が運営する「DXBoost」をおすすめします。DXBoostはDX即戦力人材を即日提案するサービスです。通常雇用ではアプローチの難しい人材の契約継続率は約98%と高く、プロジェクトに応じて柔軟な工数を調整しながらDX導入をサポートします。
サポートチームが稼動エンジニアをバックアップするため、スムーズな課題解決を実現します。技術力が高くコミュニケーション能力に長けたDX人材のご紹介が可能なため、ご興味のある方は以下リンクよりお気軽にお問い合わせください。
課題に即したツールを探す・導入する
早期解決すべき課題を見つけた後は、適切なツールを探し、導入しましょう。課題や悩みを洗い出し、優先順位を付けた上で厳選・導入することから、業務改善の効果を最大化できます。
医療ベンダーなど外部人材に依頼する場合は、複数の企業から見積りを取ることをおすすめします。機能や操作性、既存システムとの利便性などを総合的に判断し、費用対効果が得られるツールを厳選しましょう。
スタッフへ共有する
医療DXの導入にあたっては、現場のスタッフからの理解や協力が欠かせません。なんの相談もせずにシステムを導入してしまえば、システム変更を知らない方が操作できなくなるなど、大きな混乱を招く可能性があります。
システムを導入する際は、理由と効果を伝えるよう心がけましょう。どのような理由でシステムが変更され、どのような効果が得られるのかを理解することで、スムーズな活用につながるでしょう。
なお、スタッフへ共有する際は、分かりやすく作成されたマニュアルの配布をはじめ、eラーニング教材の活用、個別サポートや質問窓口の設置を行っておくと、万が一のトラブルにも柔軟に対応できるでしょう。
段階的に使用し効果を測定する
医療DXは段階的に使用しましょう。医療機関の中枢を担うシステムの場合、大規模なトラブルによってスタッフの混乱や負担が大きくなる可能性があるためです。導入初期は使用する部門や機能を限定することで、混乱を最小限に抑えられます。
例えば予約システムを導入するのなら、まずは一般外来での受付に対応させ、効果測定を行います。大きな混乱やトラブルがなければ、専門外来へと広げるイメージです。
なお、デジタルツールの導入に際しては、医療機関を利用する患者への周知も実施しましょう。院内掲示をはじめ配布物などを用いて説明することで、システムの利便性や必要性についての理解を得ることができます。
スタッフからフィードバックを受ける
デジタルツールの導入から1〜3か月ほど経過した後は、現場スタッフからシステムに関するフィードバックを受けましょう。
例えば「使いにくい」「よく分からない」といったフィードバックが多ければ、システムに関する研修の実施や配布物を使った認識の周知を行いましょう。もし、具体的にどのような点が使いにくいのかが記載されているのなら、DXベンダーなどに操作感について相談・改善を申し出てもよいかもしれません。
フィードバックをもとに改善する
フィードバックを受けた後は、必ず何らかのアクションを取りましょう。フィードバックを受けたまま放置してしまえば、スタッフにとって使いにくさが残り、業務改善が実現できません。システムやスタッフには適切なアフターフォローを行い、業務改善につなげていきましょう。
医療DXを推進する際の注意点
医療DXの導入には、下記の3点に注意しましょう。
- セキュリティ対策が必要
- スタッフのリテラシー向上が伴う
- コストが掛かる
デジタルツールの利活用は、主にインターネットを使用します。そのため、情報漏洩リスクが潜んでいることを理解し、万全なセキュリティ対策を講じることが大切です。同時に、スタッフのリテラシー向上にも努めなければなりません。ITリテラシーの理解度に不安があるのであれば、分かりやすいマニュアルの作成や研修などのサポートが必要になるでしょう。
さらに、DXの導入には費用が掛かります。条件を満たすことで補助金や助成金を利用できる場合もあるので、検討の際は経済産業省や自治体ホームページを確認することをおすすめします。
参考:サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2025)事務局|IT導入補助金
まとめ
医療DXは、AIやデジタル技術を活用し、医療機関におけるさまざまな課題を解決へと導く手段のひとつです。医師や看護師の不足をはじめ、医療機関ごとに潜む問題も、デジタルツールの導入によって改善につながる可能性を秘めています。
医療DXの推進に踏み切ることを前提に、DXにおける強力なサポートを受けたいときは、ぜひPeacefulMorning株式会社のDXBoostをご活用ください。

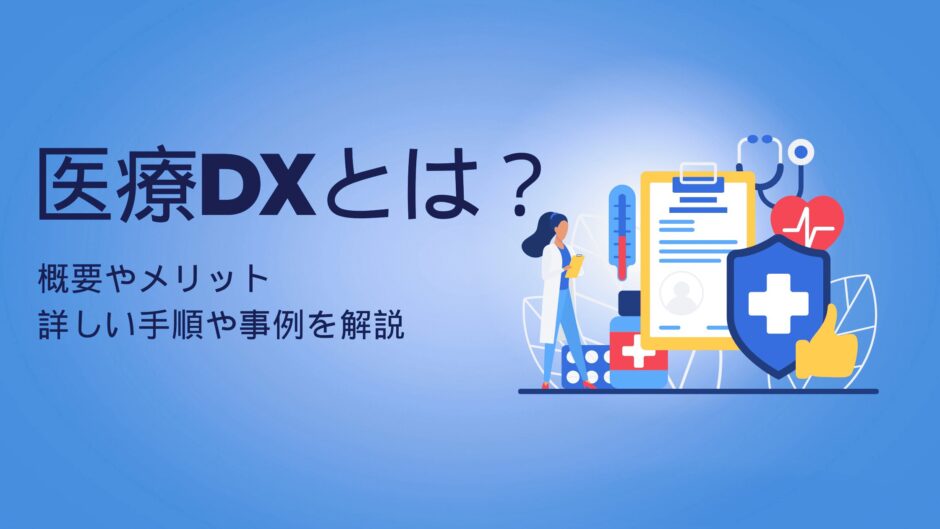




コメントを残す