世界的にDXに取り組む企業が増えていますが、DXにはどのような効果があるのでしょうか。自動化や省人化、さらには効率化といったメリットが多く注目されていますが、その背景には、業界・企業の業務にある課題が関係しています。
この記事では、業務のDX化の概要と業務改善との違い、効率化につながる理由やメリット、事例について解説します。
業務のDX化とは?
業務のDX化とは、デジタル技術を活用して業務に関するプロセスや組織に変化を加える、または企業文化の変革のことです。日本でも経済産業省を筆頭としたDX推進が行われていますが、その根本には、デジタル技術を活用してこれまでの業務を自動化・効率化し、その上で新たなビジネスを創出しながら企業競争力の向上を図ることが含まれています。
目的
国をはじめ世界的にDX化が進められている目的は、先述した企業競争力の向上とあわせて、業務効率化による生産性の向上が挙げられます。
特に日本は超高齢化社会に突入し、若手の人材不足が深刻化しています。人材不足がさらに進行すれば、大多数の従業員を必要としている業務ほど人材リソースが足りなくなり、ビジネスを継続することが難しくなるでしょう。また、現在活躍するベテラン従業員の高齢化による退職も増え、熟練の技術など後世に残すべきものほど引き継ぎが難しくなっている現状もあります。
こうした問題を解決するために推進されているのがDXです。自動化・効率化できる業務はデジタル化し、限られた資源ともいえる現在の人材に、残すべき技術や知識を継承させ、生産性の維持、さらには向上を目指していくことが重要視されています。
業務改善との違い
DXと業務改善の違いは、最終的な目的や目標です。業務改善とは、業務プロセスの大幅な変更はせず、プロセスそのものに微少な変化を加えたり、周辺業務のやり方や体制・コストの見直しを図ったりすることです。
一方DXは、業務はもちろん、各部署や全社に対してデジタル技術を活用して変革することを指します。DXと業務改善は目的や目標に加えて、対象規模が広くなることが大きな違いといえるでしょう。
業務のDX化が進む背景
業務のDX化が進む背景には、2018年に経済産業省が発表したレポートのなかで指摘した「2025年の壁」という問題と、それに伴って施行された国によるDX化の支援政策の2つがあります。
「2025年の壁」は、DX化が進まなければ2025年以降には最大で年間12兆円の経済損失が生まれる可能性が高いというものです。そこで国は、経済損失を防ぐため、企業にDX化に対する支援を進めます。
DXはデジタル技術を中心とします。そのため、導入前後には高額なコストが掛かります。スモールビジネスを展開する企業や中小企業の場合、DXを導入したくてもコストが気になり、踏み切れないケースもあるでしょう。
そうした事実を踏まえ積極的に取り組まれているのが「IT導入補助金」をはじめとした支援政策です。さまざまな支援が生まれたことで企業はDX導入に踏み切ることができ、DX化が加速していると考えられます。
DX化に有効なツールを導入する手順
企業がDX化に取り組む上では、ツールを導入する際の手順について押さえておくことが大切です。ここではDX化に伴うツールの導入手順について解説します。
自社課題を明確にする
まずはDX化に向けて、どの業務をどう改善したいのかを洗い出しましょう。現状と改善したい理由、どのようにしたいのかを洗い出すことで適切なデジタルツールが選びやすくなります。
自社に潜む課題の多くは現場従業員が把握している項目です。そのため、DX推進において解決してほしい課題や悩みについては、従業員にヒアリングすることを意識しましょう。Googleフォームなどを活用すれば紙媒体を使用せずに済むほか、従業員のタイミングで投稿できるので便利です。
なお、目標や目的は目に見えないものです。頭に入れておくだけでは全社に浸透しきれないだけでなく、改善したい課題が見つかれば見つかるほどブレます。DX推進を図る際は、目標・目的はいつどのようなときでも誰もが確認できるよう、周知や理解の時間を設けるようにしましょう。
改善させたい業務を洗い出す
従業員などからのヒアリングを通じて、社内における課題をあぶり出した後は、改善させたい業務に優先順位を付けましょう。得た回答によってはどれも早急に解決したくなりますが、全てに着手しようとすれば初期費用が高額になるだけでなく、導入にあたっての混乱を招きかねません。
DXは、長期的に実施し、デジタル技術の精度を自社の理想に近づけながら徐々に社内を変革させる取り組みです。そのようなことから、DX導入に踏み切る際は早期に解決すべき課題から改善を図るなど、スモールスタートを心がけましょう。
短・中・長期での目標を設定する
DX導入に踏み切るときは、短・中・長期での目標を設定することをおすすめします。3か月・6か月・1年といった期間を設けることで、DXによって自社課題がどのように変化したのかを細かく評価することができます。
また、デジタルツールの精度分析にも有効です。例えば、導入後3か月の時点ではC評価だったものの、1年ではB+にまで上がっているなど、ツールそのものの分析にも活用できます。
モデルの運用
自社課題に適したデジタルツールを見つけた後は、導入し、モデル運用を行いましょう。なお導入したばかりのツールは、最初から高い精度を発揮するわけではありません。まずは業務に関するデータをツールに取り込み、初期設定を行いましょう。
ある程度精度が上がった後は、より細かなデータを取り込み、チューニングすることで、さらに精度を上げることができます。
評価・分析
デジタルツールの設定・チューニングが終わった後は、スモールスタートを意識し、早期解決させたい業務に取り入れます。毎日使うツールであるほど直感的な操作感や既存システムとの互換性が高い方が慣れ親しみやすいです。
なお、利用した従業員からは必ずツールに対するフィードバックを受けるようにしましょう。フィードバックによってツールの改善へとつながり、自社に順応したものへと進化させることができます。
また、ツールの精度は変革に大きく影響します。デジタルツールを導入した後は、課題の変化やツールの精度を細かく振り返り、DXによって企業がどのように変化しているかの確認も欠かさず行うようにしましょう。
本格的に導入する
デジタルツールの導入によって自社課題の解決につながると判断できたときは、全社に導入し、一定期間活用してみましょう。
なお、DXは導入して終わりではありません。DX化の目的は、企業競争力の強化と業務の効率化です。そのため、導入したツールの修正・評価を繰り返しながら長期的に活用し、企業競争力を向上させることを意識しましょう。
業務のDX化のメリット
業務のDX化には、さまざまなメリットがあります。具体的には下記の通りです。
企業競争力の向上
ビッグデータの処理・分析に有効なデジタルツールを導入すれば、競合他社をはじめ市場における自社の立ち位置も迅速かつ正確に分析できます。高精度なデータ分析が可能になれば企業戦略の策定の迅速化が実現します。
企業の方向性を決める際、客観的な意見として高精度なデータを求められることが多いです。迅速な意思決定に必要となるデータ分析をDXで実現することは、企業競争力の向上に大きく貢献するといえるでしょう。
業務効率化
DX化によって、人間が従事していた業務をロボット・デジタル技術へと代替できるので、必然的に業務を効率化することができます。そもそも国のDX推進の目的にも業務の効率化が含まれています。そのことから、多くの時間・労力を費やしている業務ほど、デジタルツールを活用し業務の効率化を図ることが望ましいといえるでしょう。
新サービスの開発
新サービスの開発につながるのもDX化のメリットです。例えばこれまで取得・分析することが困難だった膨大なデータも、DX化によって迅速かつ正確に行うことが可能です。これまで取得できなかったデータを取り込めるようになれば、新たなデータによって新サービスの開発につなげることもできます。
働き方改革の推進
DX化によって働き方改革の推進も可能です。例えば完遂までに時間や労力を必要としていた業務を自動化・効率化させれば、残業時間の減少に期待できます。各部門をDX化させれば、働き方改革の実現に大きく近づけることができるでしょう。
人材不足の解消
デジタルツールの活用によって人材不足の解消も実現可能です。人手不足によって業務の完遂が難しい部門をDX化することで、人間の代替ができるからです。また、デジタル技術によって迅速かつ正確に業務をこなすので、生産性の向上にも期待できます。
人材配置の最適化
これまで人数を要していた業務や反復・単純作業が中心だった業務をDX化できれば、人員削減も可能になり、適材適所の人材配置も実現します。人材配置の最適化ができれば、従業員のスキルアップにつながり、結果的に企業力の底上げに期待できるでしょう。
業務のDX化の取り組み事例
ここからは、業務のDX化に取り組んだ企業の事例について解説します。
- ダイキン工業株式会社
- トヨタ自動車株式会社
- キヤノン株式会社
- 株式会社LIXIL
- 旭化成株式会社
- 株式会社ブリヂストン
- 株式会社日立物流
- 日本郵便
- ユニ・チャーム株式会社
- 株式会社商船三井
- 株式会社NTTデータビジネスシステムズ
DXによってどのように変化を遂げたのかさっそく見ていきましょう。
ダイキン工業株式会社
ダイキン工業株式会社では、ビル用マルチエアコンを生産する新工場においてIoT技術を活用し、受注生産品の大量生産を可能にする体制を実現しました。
ビル用マルチエアコンは、1台の室外機と複数の室内機を接続できる業務用エアコンで、オフィスなどの広い空間を効率的かつ快適に空調できる特徴があります。同社がグローバルで普及を目指す主力商品である一方、異なる仕様の商品も並行して作るための整備が必要でした。
そこで同社は、異なる仕様の製品もたった1つの生産ラインで、さらに流れ作業で組み立てるマスカスタマイズ生産に成功し、納期の6割短縮を実現させました。
参考:東洋経済ONLINE|ダイキン「新工場のIoT化」に熱心な理由 第4次産業革命で勝ち残るのは誰だ
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社では、日立製作所と協業し、IoT技術を活用した工場の生産効率化を発表しました。日立が手掛けるIoT基盤をトヨタの車両工場やエンジン工場に導入し、生産効率を高めることが目的です。
目的を具体化させて構築された工場のIoT化により、開発や市場のデジタル化へと進み、上表共有基盤の強化を図るとともに、オールトヨタと顧客がつながる新たなものづくりを目指しています。
参考:日刊工業新聞 電子版|トヨタ、日立と協業−IoTで工場生産効率化 | ICT ニュース
参考:トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト|トヨタと日立がIoTプラットフォームを活用した高効率生産モデル構築に向けて協創開始
キヤノン株式会社
社内における情報共有にさまざまな課題を抱えていたキヤノン株式会社では、社内コミュニケーション向上を目的にMicrosoft365を導入・活用しています。
同社では、ITを使った情報共有をはじめ、社内コミュニケーション強化のニーズが高まっているものの、少人数のIT管理者によっていかにスマートな環境整備、運用を実現できるかは中小企業の競争力を左右する重要課題と考えていました。
Microsoft365の導入によって、従業員1人ひとりのスケジュールが把握しやすくなり、プロジェクト管理がスムーズになったほか、利用者の追加も想像以上に簡単にでき、高い利便性を実感しています。
またクラウドサービスであるためオンプレミス環境が不要となり、サーバーのメンテナンスから解放され、業務に集中できるといったメリットも得られています。
参考:キヤノン株式会社|限られたIT管理者でもMicrosoft 365をスムーズに導入・運用できる環境を実現し情報共有基盤を強化|中小企業ソリューション|法人
株式会社LIXIL
株式会社LIXILでは、生産性の向上、さらにはデータドリブンな意思決定を可能にするため「LIXIL Data Platform」を立ち上げ、データの一元管理と高速な分析を目指しています。専門知識の少ない従業員でも、業務に必要となるツールの開発・運用が可能になり、業務の効率化を進められています。
参考:株式会社LIXIL|デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組み | 経営方針・体制 | 株主・投資家向け情報
旭化成株式会社
旭化成株式会社では、経営の基盤強化や持続可能な社会への貢献、持続的な企業価値向上につなげるため、そしてグループにおける全従業員のデジタル活用を当たり前とするため「デジタルノーマル期」となるよう、DX推進の取り組みを強化しました。
具体的には、特許データから知的財産情報を抽出・分析し、コア技術を用いた経営戦略の策定などです。部門ごとでもDXを展開できるようデジタル共創本部を設け、各部門と本部の連携体制も整えるなど、デジタル技術を使いこなす人材育成の仕組みを構築しました。
参考:旭化成株式会社|DX戦略説明会 – デジタル人材の強化とビジネス変革
参考:旭化成株式会社|戦略 | デジタルトランスフォーメーション | 企業情報
株式会社ブリヂストン
株式会社ブリヂストンでは、DXによって匠の技を効率的かつ確実な伝承を実現しました。株式会社ノビテックと共同開発されたシステムによって、向上における成型作業に必要な暗黙知を形式知化および定量化し、熟練従業員の技を伝えていくものです。
航空機用タイヤを生産する久留米工場をはじめ、建設・鉱山車両用タイヤを生産する北九州工場に導入されており、ソリューション事業を支える有力商品の安定供給につなげています。
株式会社日立物流
株式会社日立物流では、3種のDXソリューションを開発し、事業領域の拡大とあわせて業界全体のDXにも貢献しています。
|
SCDOS (Supply Chain Design & Optimization Services) |
サプライチェーン上の情報をデジタル基盤での一元管理・可視化させ、分析・シミュレーションをプラスして課題解決を補助するソリューション |
|
SSCV (Smart & Safety Connected Vehicle) |
トラックドライバーに掛かる負担を考慮し、安全を図ることを目的としたソリューション |
|
SWH (Smart Warehouse) |
Eコマース事業者向けの物流業務に関する自動化・省人化・標準化を目的としたソリューション |
これらのソリューションを活用するとともに顧客へ提供することで、持続可能な物流構築や新事業・サービスの展開を目指しています。
参考:株式会社日立物流
日本郵便
日本郵便では、ネット通販の拡大とともに増えた物流量と配達員の不足を受けて、輸送コストが懸念されていた地域を優先し、ドローンを使った荷物の輸送をスタートさせました。
自立飛行機能が搭載されたドローンのため、陸路の配送をはじめ倉庫への飛行は自動化に対応しています。現在、ドローン飛行については法律で厳格に定められており、完全自動で配送できる地域は限られていますが、ドローン輸送はできるという結果から配達員の負担軽減につながると判断できたことを受け、今後は配達時間の短縮を目指すとしています。
参考:経済産業省|デジタル トランスフォーメーション 銘柄 ─
参考:日本郵政グループ|未来の物流レボリューションVol.4 日本初!レベル4飛行でのドローンによる配送を実施!
ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャーム株式会社では、デジタルスクラムシステムの導入によって、10分の1ミリの精度で顧客の表情や繊維の微細な変化、設備の点検などを数千キロ離れた場所からでも把握できる環境を実現しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって国内から海外への出張ができなくなることが増えました。出張ができなくなれば、現地設備のメンテナンスや顧客へのインタビューが延期・中止になることが多く、業務に支障をきたしていたことが課題でした。
こうした環境が続いたことを機にデジタルスクラムシステムの導入を実施し、インターネットに接続可能な画面などを通して、世界各国にある生産設備稼動の検証をはじめ、点検・調整もミリ単位で視認できるようになりました。
画面を通して詳細な現状把握が実現したことによって、複数の開発者や調査員がありのままの生活環境や表情をみながらの直接対話や、赤ちゃんやお年寄り、ペットの居住空間を複数の現地法人から24時間遠隔モニタリングすることを可能にしています。
参考:ユニ・チャーム株式会社|DX「デジタルスクラムシステム」を開発|2021年|ニュースリリース|企業情報-ユニ・チャーム
株式会社商船三井
株式会社商船三井では、サステナビリティ課題への取り組みのひとつとしてDXを位置づけ、デジタル技術を活用して安全や環境などのサステナビリティ課題の解決やグローバル市場での企業競争力の強化、新たなビジネスモデルの創出につなげています。
例えば、船舶運行におけるDXの核となるデータ基盤である「FOCUS」を活用してセンサーデータや実海域観測データを収集し、AIをはじめとする先端技術を駆使して効率運航や安全性の向上を図るなどです。
機器故障予兆診断によって安全性向上を実現しながらデータ分析に基づく最適運航によって、環境負荷を低減し、持続可能な船舶運航の実現を目指しています。
参考:経済産業省|デジタル トランスフォーメーション 銘柄 ─
株式会社NTTデータビジネスシステムズ
NTTデータビジネスシステムズではこれまでの「モノづくり」を超えた「価値づくり」に向けた取り組みにDXを活用しています。DXの考え方を2つに分け、それぞれの方向からアプローチを行い、縦横無尽に世界を変えるという目的を掲げています。
|
Of-DX |
従業員1人ひとりの知識・技術・知恵を集め、企業のケイパビリティを飛躍的に向上させる |
|
By-DX |
顧客と共にイノベーションを実現させ、新たな価値を創造する |
Of-DXでは従業員全員が「ジブンゴト」として自律して行動できるよう、DXを通じて高付加価値・高生産性の活動を実行するとしています。一方By-DXではDXを武器に顧客とイノベーションを起こし、新たな価値を創り出すことを目標にしています。
DXを活用して顧客情報を収集・分析し、製品・サービス向上を図る企業は増えても、DXと顧客を絡めた取り組みを進める企業は多くありません。また、By-DXでは顧客だけでなく、社会の変革の促進も見据えていることから、同社グループのめまぐるしい進化が期待されます。
参考:株式会社NTTデータビジネスシステムズ|DX推進の取り組み
業務のDX化の課題
業務のDX化には、課題や問題の改善・解決などのメリットが多くある一方で、いくつかの課題もあります。ここでは、業務のDX化における課題について解説します。
DX人材の育成・確保
業務のDX化においては、デジタル技術に精通した人材の育成・確保が必要です。知識や技術を持つ従業員がいないままだと、ツール導入の前後における設定やトラブルの適切な対処が行えず、全体業務がストップする可能性があります。
DX人材の育成を検討される際は、PeacefulMorning株式会社のDXBoostをおすすめします。グループ累計600万名を超える人材データベースから、企業に必要なスキルを持ち合わせた人材を紹介するサービスです。案件参画まで最短1週間のため、欲しい人材をすぐに確保できます。
導入前後のコスト
DX化にはコストが掛かることも念頭に置く必要があります。特にツールの精度によっては初期投資が高額になることもあるため、費用対効果を考慮しながら適切なツールを探すことをおすすめします。
既存システムのIT化
社内で活用する既存システムの利用期間が長いと、新たなツール導入に不安を持つ従業員も少なくありません。この状況のままでは、DX化が難航する恐れがあります。
既存システムの利用期間が長ければ長いほどブラックボックス化しやすいため、現状把握が困難になることもあります。
DX化には既存システムのIT化が必要です。そのため、まずは1つひとつのシステム把握からはじめ、徐々にIT化へとつなげていきましょう。
透明度の高い目標の設定
目標や目的は、できる限り透明性を保ちましょう。DX化に取り組むなかで従業員から寄せられた課題や悩みが集まるほど、設定した目標・目的がブレてしまいます。また、DX化そのものがゴールに切り替わることで失敗を招くケースも少なくありません。
DX化を図るためには、透明度の高い目標や目的を設定し、全社に共有し、共通認識として把握できる環境にすることも大切です。
まとめ
業務のDX化は、AI技術やデジタル技術の活用を通じて、業務に関するプロセスや組織の改善を図ることを指します。国によるDXの取り組みでは企業競争力の向上と業務の効率化を目的としていることから、デジタル技術をいかに企業に役立てていくかが重要となります。
デジタル技術の活用にあたっては、あらかじめDX事業部や開発部の発足が欠かせません。しかし、社内従業員ではリソースなどに不安を感じることもあるでしょう。そのようなときは、弊社の「DX Boost」をご活用ください。
DX Boostは、企業のDXプロジェクトに最適な人材を最短1週間でアサインするサービスです。スキル面はもちろんコミュニケーション能力の高い人材をご紹介いたします。業務のDX化をはじめ適材適所な人材配置、働き方改革の推進を図りたい方は、この機会にお気軽にご相談ください。




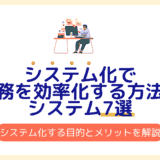
コメントを残す