スタートアップ企業を中心に現在「リーンスタートアップ」と呼ばれるビジネスモデルが注目を集めています。最小限のコストとリスクで製品・サービスを作り、迅速な事業展開のなかで得た顧客フィードバックを取り入れ、より優れたモノを作り上げていく方法です。
コストやリスクが最小限に抑えられる方法ではあるものの、検討や実施に移る際には、具体的な考え方や実践方法について押さえておくことでトラブルの防止につながります。この記事では、リーンスタートアップの概要と手法、メリット・デメリットや活用事例について解説します。
リーンスタートアップとは
リーンスタートアップとは、できる限りコストとリスクを抑えた上で製品やサービスを作り、顧客によるフィードバックを繰り返し取り入れながら方向性を定めていくビジネスモデルのことです。最小限の製品・サービスから事業をスタートするため、ビジネスに潜むあらゆる無駄がなく、顧客ニーズに沿った製品・サービスの展開が期待できます。
「細い」「痩せた」といった意味を持つ「Lean」とスタートアップを組み合わせた言葉のため、「無駄のないビジネスモデル」「無駄を省いたビジネスモデル」などと考えることもできます。
ルーツや提唱者
リーンスタートアップを提唱したのは、米国の起業家エリック・リース氏です。トヨタ生産方式としても知名度の高い「リーン生産方式」の考え方を、ITやスタートアップ企業の事業開発へ応用したものが始まりとされています。
デザイン思考やアジャイルとの違い
リーンスタートアップと混同されやすいビジネスワードとして、デザイン思考やアジャイルがあります。デザイン思考は、顧客課題を深く理解し、革新的なアイデアを創造するための手法です。「自社から何を生み出すべきか」といった問いに答えるための「探索」に強みがあり、主に設計段階で用いられます。
一方、アジャイルはソフトウェア開発で使われることの多い手法で、要件を細かく設定せずに進めるため、製品・サービスの仕様変更に対応しやすい特徴があります。また機能単位での開発によって、顧客への提供を迅速に行えるメリットもあります。
リーンスタートアップは、コストとリスクを最小限に抑えた上で顧客に製品・サービスを提供することです。最初から完璧を追究するのではなく、顧客のフィードバックを通じて改善を図り製品・サービスの方向性を定めていくため、デザイン思考やアジャイルとは目的に違いがあります。
なお、いずれも異なる手法ではあるものの、ビジネスにおいては併用が可能です。例えば、リーンスタートアップ構築時のアイデア出しでデザイン思考を用いる、MVPの開発・改善の際にアジャイルを用いるなどです。
MVP(Minimum Viable Product)の関係性
MVP(Minimum Viable Product)は最低限の機能を備えた製品・サービスの試作品を指し、リース氏の著書で提唱された用語です。
製品・サービスの開発では最初から利便性や親和性、快適性など、あらゆる要素を取り入れたモノづくりが行われがちですが、仮説に誤りがあった場合、これまでのコストがすべて無駄になってしまいます。
モノづくりをはじめるうえでは「後で改善する」ことを念頭に置き、仮説検証用としてMVPを制作することで、コストやリスクをさらに抑えた開発を実現できます。
リーンスタートアップの手法
リーンスタートアップにあたっては、下記のステップについて押さえておきましょう。
仮説構築
リーンスタートアップでは、リリースに必要なデータで構築された「リーンキャンバス」とMVPキャンバスのそれぞれを使い仮説構築を実施します。リーンキャンバスとはモノやサービスの開発に欠かせない情報を集めたシートのことで、モノ・サービスの方向性や利用予定のマーケティング手法、リリース後の成果見込みなどを記入します。
MVPは最小限の価値を備えた製品・サービスを指すことから、MVPキャンバスでは顧客から届いたアンケート結果やフィードバックをもとに試作品の作成を目指します。
計測・実験
次は実際に製品・サービスを作成し、リリース後の市場の反応を見て計測と実験を行います。ここでのポイントは、最初から完成度を追わず、MVPレベルでの提供を視野に入れることです。MVPである点を再認識することで、万が一うまくいかなかった場合のコストやリスクを最小限に抑えられます。
学習
計測と実験で収集したデータを参考に、次はMVPに改善を加えて製品・サービスの方向性を定めていきます。市場や顧客の反応が理想よりも遠い場合は、その理由を特定し、改善を図ります。マネジメント手法やPR方法が適切ではなかった可能性もあるため、多角的な視点で見つめ直すことを意識しましょう。
再構築・改善
軽微な改善点であれば前項の「学習」フェーズで対応できますが、状況や改善内容によっては製品・サービスの方向性や概要を大幅に変更する必要もあるでしょう。リーンスタートアップであれば仮説構築からやり直すことをおすすめします。
進展度や提供速度は落ちますが、MVPであればコストやリスクを最小限に抑えることができます。顧客体験の向上につなげるためにも、自社が提供すべき製品・サービスとはなにかについて改めて考えてみましょう。
リーンスタートアップとMVPによるメリット
製品やサービスの開発にあたっては、莫大な時間的リソースやコストがかかることが一般的であり、仮に開発が頓挫すればすべて無駄になるリスクが潜んでいます。しかしリーンスタートアップやMVPは、最小限のコスト・リスクにとどめながら、より早く最適な製品・サービスの完成に結びつけることができます。
時間・費用を抑えた計測が可能
完璧な製品・サービスを目指して開発した場合、膨大な時間やコストがかかるため、開発後のトラブルなどによっては多くの無駄を招くリスクがあります。しかしリーンスタートアップではMVPの作成を通じて製品・サービスの方向性を明確にする特徴があるため、時間やコスト、リスクを最小限に抑えながら市場に適した開発に結びつけることができます。
多くの機能を盛り込んだ製品やサービスは開発者にとっては魅力的に映るかもしれませんが、顧客によっては使いこなすことが難しく、多くの機能を不要とするケースも存在します。MVPではそうした可能性を多角的な視点から捉えることにつながり、最小限のコスト・リスクに留めながらより早く最適な製品・サービスの完成に結びつけることができます
市場競争において優位になる
MVPを市場にリリースすることで先行者利益が得られ、競争優位性の確立に期待できます。また、改善サイクルを自社なりに見つけ、着実に繰り返すことができれば素早く顧客ニーズへ対応することにもつながり、収益化における時間短縮も見込めるでしょう。
顧客ニーズを素早くキャッチアップできる
リーンスタートアップやMVPによって製品やサービスを早く市場にリリースできる分、顧客からの具体的なフィードバックも早く得ることにつながります。顧客ニーズを捉えた改善が従来よりも早く実現できるため、競争優位の確立だけでなく、顧客体験の向上にも期待できます。
素早い商材提供を実現できる
スタートアップ企業の場合、新たな製品・サービスをどれだけ早く市場にリリースするかがポイントです。仮に競合他社に先を越された場合、どれだけ優れた製品・サービスであっても価値は大きく低下してしまうでしょう。MVPは完璧を求めず素早い開発を実現できるため、競合他社に先駆けて市場に参入し、優位性の確立につなげられます。
リーンスタートアップは時代遅れ?懸念されるデメリット
一部の企業などからは、リーンスタートアップというビジネスモデルが「時代遅れ」と言われることもあるようです。ここからは、なぜそのようにいわれるのか、リーンスタートアップに潜むデメリットについて解説します。
必ずしも成功するわけではない
リーンスタートアップやMVPによってコストやリスクを最小限に抑えられたとしても、提供する製品・サービスが万人受けしないモノであれば失敗する可能性があります。
また、開発には各リソースとコストが必然的にかかり、仮に何度も仮説構築を繰り返す結果になれば最終的には大きな赤字を招くことにもなりかねません。素早い事業展開を視野にリーンスタートアップやMVPを検討するのであれば、事前に市場や顧客ニーズを丁寧に分析し、自社に何が求められているかを熟考することが大切です。
目的を見失いやすい
MVPの作成と検証を繰り返すあまり、当初の目的を見失ったり、ブレてしまったりする可能性もあります。自社あるいはチームが目指すべきゴールはどこなのか、そしてリーンスタートアップというビジネスモデルやMVPにどのような目的があるのかを念頭に置いた取り組みを心がけることが大切です。
業界によっては適さない
製造コストが高額な業界の場合、試作品の制作段階でも多額のコストがかかるため、リーンスタートアップやMVPに向いていません。また、トレンドの変化が激しい業界の場合も顧客ニーズの変化が頻繁に起きやすい傾向から、改善や仮説構築の繰り返しによっては製品・サービスの完成に時間やコストを要し、難しさを感じる場合があります。
再構築が難しい
MVPのリリース後、顧客から具体的なフィードバックが得られない場合や改善に多くの時間・コストを要する場合、再構築が難しくなる可能性があります。日々、業務に真摯に取り組んでいるうちに改善が目的にすり替わることも多く、この場合、当初の目標からかけ離れた製品・サービスを完成させてしまう場合もあります。
リーンスタートアップに関する事例
ここからは、リーンスタートアップに関する事例について解説します。どのような企業でどう進めているのかを押さえ、今後の参考にしましょう。
Yahoo!JAPAN
Yahoo!JAPANでは2015年末にオークションアプリ「ヤフオク!」の開発にリーンスタートアップを導入しています。開発時間の大幅短縮や手戻りの激減により、2018年には全社展開の拠点として「820Labs」を設立しています。現在では「Yahoo! JAPANアプリ」といった主力サービスにもリーンスタートアップを導入し、素早い開発につなげています。
参考:“手戻り”激減でヤフオク!アプリの開発期間を大幅に短縮
世界的にも多くのユーザー数を誇るInstagramは以前、位置情報を共有する「Burbn」というSNSでした。リリース後の注目度は予想を下回り、構築や計測、学習といった各プロセスを繰り返していました。サイクルを繰り返すうち、写真の共有機能に高い顧客ニーズを見出し、その後は写真投稿を中心とした現在のInstagramに方向転換しています。
YouTube
現在ではニュースやユニークな投稿から学習に有用な動画を閲覧できるYouTubeですが、YouTube社でもリーンスタートアップが取り入れられています。従来から動画投稿ツールではあったものの、ターゲットが限定的だったため、幅広いジャンルの動画をオンラインで共有できるよう方向転換しました。
その結果、さまざまな動画をオンラインで視聴できる大規模な動画視聴サービスへと進化を遂げています。
トヨタ自動車
トヨタ自動車で実施されている「かんばん方式」は、リーンスタートアップのルーツのひとつであり、「必要なものを、必要な時に、必要な分だけ作る」という無駄をなくすための考え方です。この取り組みによってチーム全体での情報共有がスムーズに進み、情報の一元管理を実現しています。
BASE FOOD
完全栄養食を開発するBASE FOODでは、創業者自らの食生活の乱れを機に誕生したサービスです。リーンスタートアップのなかでも構築・計測・学習のフィードバックループを積極的に活用し、「BASE PASTA」では発売後、4年のうちに18回も改善を重ね、現在の「BASE BREAD」を誕生させています。
参考:完全栄養食BASE FOODのイノベーションは『リーン・スタートアップ』と『コトラーのマーケティング4.0』の世界を体現していた。【みる兄さんが話題のプロダクトを考察する連載・第7回】
まとめ
リーンスタートアップは、社会や顧客ニーズの変化が激しい時代のなかで、最小限のコスト・リスクで事業を成長させるためのビジネスモデルです。本記事で解説したステップをひとつのサイクルと捉え、実践することで、顧客ニーズを迅速に捉えた製品・サービスの開発につなげられます。
Peaceful Morningでは、DX推進を加速させるプロ人材を紹介するサービス「DX Boost」を提供しています。グループ600万名を超える人材データベースから、貴社に最適なDX人材を即日ご提案できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。
最小限のコスト・リスクで事業展開を目指す上で、DX人材の不足がボトルネックに至った際は、この機会にお気軽にPeaceful Morningへお問い合わせください。

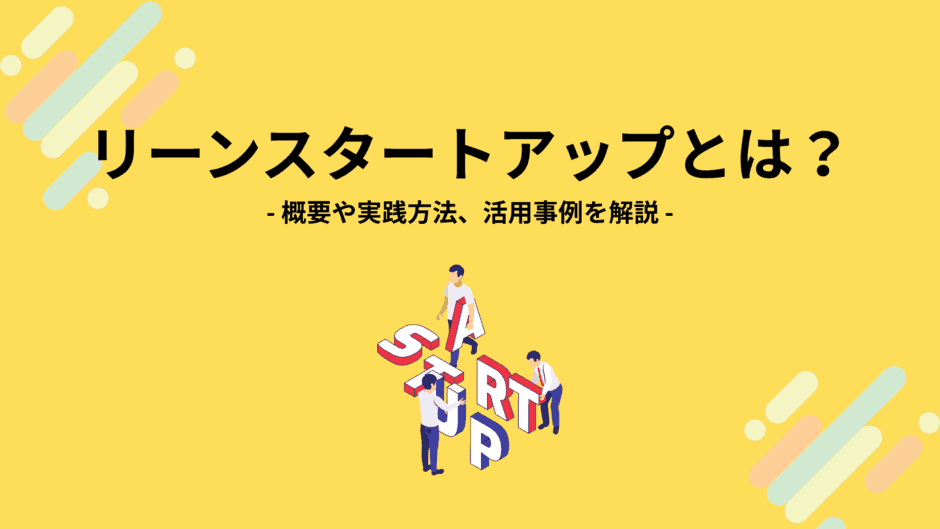



コメントを残す