今ではビジネスシーンに限らず、日常の疑問や悩みなどを質問・相談する人が増加し続けているChatGPTですが、利用規約に目を通した上で利用している方は少ないかもしれません。
生成AIが生み出すデータはさまざまな理由によりすべて正しいわけではないため、自身だけでなく身近な人や第三者に誤解や不安を与えないよう、ルールを把握しておくことが推奨されます。
この記事では、ChatGPTを利活用する上で把握しておきたいコンテンツポリシーを解説します。違反の対象となるケースや、違反行為に該当した場合の対応にも触れるので、多様なシーンで使用する方は正しい使い方への理解を深めましょう。
関連記事:ChatGPTは何ができる?できないことや活用のコツ、注意点を解説

\ DX・AI人材を600万名から選抜して提案 /
ChatGPTのコンテンツポリシーとは
ChatGPTのコンテンツポリシーとは、ChatGPTを提供するOpenAI社が定めた使用におけるルールのことです。今やビジネスシーンに限らず日常での利活用が増えるChatGPTですが、なかには性的、暴力的、差別的など、第三者が見ると不快に思う表現をChatGPTに生成させるユーザーが少なくありません。
そのためOpenAI社では、安全かつ責任あるAI利用の方針に基づき、下記のようなルールを挙げています。
- 悪意のあるユーザーによって有害なコンテンツ生成をしない
- 不法な行為を助長するような利用をしない
- プライバシーや著作権といった他社の権利を侵害しない
こうしたルールを明確に定め、ユーザーにルールを守ってもらいながら適切かつ持続的なサービス提供の実現を目指しています。
なお、ChatGPTではコンテンツポリシーについて質問すると、ルールに関するページを素早く閲覧できます。頻繁に利用しているもののまだ目を通したことがない方や、はじめてChatGPTを使用する方は質問を通じて確認してみるとよいでしょう。
また、コンテンツポリシーは一般利用ユーザー向けに設定されたポリシーに限らず、画像・動画作成におけるポリシーも設けられているため、画像・動画作成も行う方はそれぞれに目を通しておきましょう。
参考:Creating images and videos in line with our policies | OpenAI
ChatGPTのコンテンツポリシー違反例
多くのユーザーに安心・安全に利用してもらうべく、さまざまなページに多様なコンテンツポリシーを設定するChatGPTですが、それでもなお、ルールを守らず規約違反に至るユーザーもいます。
不適切コンテンツの生成リクエスト
不適切コンテンツの生成リクエストは、社会的に「それはよくない」と判断する行動や言動を推奨するようなコンテンツを指します。例えば性的、暴力的、差別的なコンテンツは不適切コンテンツに該当します。
これらはいずれも、自分を含め誰かを傷つけたり不快にさせたりする内容につながりやすいため、生成が発覚した場合ペナルティの対象になることがあります。
著作権侵害にあたるもの
すでに著作権で保護された作品を模したコンテンツ生成も、著作権侵害にあたりコンテンツポリシー違反となります。また「○○GPT」といった表現やOpenAIロゴの使用についても、コンテンツポリシーに記載された規定に準拠しなければなりません。
思わぬところで規約違反とならないよう、今一度コンテンツポリシーへの理解を深めておきましょう。
個人情報の取り扱いが不適切
個人や組織に関する機密度の高い情報や個人情報を不当に収集・共有・利用するためのリクエストも禁じられています。例えば、親しくしていた取引先担当者に退職の旨を伝えるために個人情報を取得しようとする行為も、悪意がなくても不適切とみなされます。
どのような目的があっても、企業や個人に関する機密度の高い情報を得るためにChatGPTを使用することは避けましょう。
虚偽の情報を拡散している
ChatGPTに限らず生成AIは、インターネット上で閲覧できる膨大な情報をもとにユーザーが提示したプロンプトに基づくデータを生成しています。そのためプロンプトの内容によっては誤った情報を参考にし、虚偽の情報を生成することがあります。そうとは知らずSNSなどに投稿した場合、虚偽の情報を拡散したことになり規約違反となる可能性があります。
なかでも医療や士業などの専門分野に関する情報は、科学的・専門的根拠のないデータを生成するケースが多く、誤解を招く場合があります。こうした情報を鵜呑みにし、第三者に共有した場合、虚偽の情報を拡散していると判断され、アカウントの利用が制限されることがあります。
生成データを犯罪行為に利用している
こちらもChatGPTに限りませんが、生成AIで生成された情報を詐欺や違法な取引などに使用する行為も禁じられています。
例えば、危険物の取引や詐欺、サイバー攻撃に関する情報を生成することは規約違反となります。プロンプトを提示する際は、知らないうちに犯罪行為につながる、あるいは助長しているとみなされないかについて確認した上で送信することをおすすめします。

\ DX・AI人材を600万名から選抜して提案 /
ポリシー違反とみなされた後のOpenAIによる対応
悪意の有無に限らず、ユーザーの行動がコンテンツポリシーに反していた場合、OpenAIはどのような対応を取るのでしょうか。具体的には、違反の強度や深刻さによって下記の対応がなされます。
メッセージなどによる警告
ユーザーの行動からポリシー違反が検出されたときは、まずOpenAIから警告文が届き、どのような行動が違反行為であったかを通知されます。警告文が届く、あるいは表示された際は違反の性質、度合いなどに応じて、ユーザーに是正措置を取るための機会提供がなされる場合があります。
アカウントの一時停止
ユーザーの行動がポリシー違反に該当し、かつ違反性が重度である、または繰り返す動作が見られた場合、OpenAIはこれ以上のトラブルを助長させないようユーザーアカウントを一時的に停止することがあります。
停止期間は明記されていないため、ChatGPTを頻繁に利活用する方は、警告を受け是正の機会が提供された時点で行動を改めることが推奨されます。
アカウントの凍結
メッセージでの警告や一時停止を受けてもなお是正が見られない場合、該当アカウントが永久停止される可能性があります。具体的な事例は公表されていませんが、犯罪を助長する行為や不適切なコンテンツ生成を繰り返す行為は凍結リスクが高いと考えられます。
法的措置
ユーザーの違反行為が法的な問題に発展する可能性がある場合は、OpenAIから法的措置が取られる可能性もあります。例えば著作権侵害や性的コンテンツを繰り返し生成し、不特定多数のユーザーに拡散した、といった違反行為は法的措置の可能性が十分にあります。
法的措置に関する判断基準や詳細は明らかではありませんが、OpenAIのコンテンツポリシーに繰り返し違反し、犯罪を助長するデータを生成するアカウントは、法的観点から見ても問題視されるでしょう。
具体的な基準について明らかになっていないからこそ、ChatGPTを使用する際はユーザー自らが法的観点からみて問題のないプロンプトおよび生成データであるかを確認する姿勢が大切です。
ChatGPTを安全に使うためのポイント
近年では多様な業界・シーンで利活用されることの多いChatGPTですが、今まで以上に安全に使うためにはどのようなポイントに留意する必要があるのでしょうか。ここからはChatGPTの使用における安全に使うためのポイントについて解説します。
利用規約にはこまめに目を通す
ChatGPTを含むOpenAIのサービスは、新機能の追加や法規制の変更、ユーザーフィードバックに基づく改善に合わせて、不定期に利用規約が更新されます。
ユーザーや社会の変容、ニーズ変化に寄せた規約に更新する必要性を考慮するとともに、知らないうちに自身の行動が規約違反となることを防ぐためにも、利用規約は定期的に確認することをおすすめします。
日常的な使い方を見直す
ChatGPTの日常的な使い方をこの機会に見直す方法も効果的です。物事を調べるうちに疑問が次々と生まれ、探究心が強まるほど、意図せずポリシーに反する質問をしている可能性も少なくありません。
例えば子どもが恋愛というキーワードについて質問した場合です。興味が深まるにつれ「人はどのように生まれるのか」といった内容に進む可能性があります。このような過程には、親が知らないところで性的コンテンツが生成されるリスクが潜んでいます。
こうしたケースは子どもに限らず、大人やビジネスの場でも、探究心や質問の積み重ねによって起こり得ます。利用規約はユーザーのニーズや安全・保護を目的に日々更新されています。どの程度の質問なら許容範囲かを把握するため、コンテンツポリシーに目を通し理解しておくことが、安全な利用に欠かせないポイントです。
活用範囲を見直す
ChatGPTに限らず、現在主流の生成AIは万能ツールではありません。専門的な知識が求められる医療や士業などをはじめ、正確性が欠かせない業務においては、参考情報を素早く抽出できるツールという認識に留めることも大切です。生成情報は参考資料の1つと位置づけ、最終的な判断と責任は人間が担うことを明確にしましょう。
データマネジメントの向上を図る
ChatGPTを使用する場合は、どのようなデータを入力するか、生成されたデータをどのように扱うかといった明確なルールを定めておくことも大切です。特にビジネスでの利活用では、機密性の高い企業・個人情報や取り扱い注意のデータは、入力自体を禁止するなどの措置が求められます。
日常生活においても、どの程度の質問、どの程度の情報提示であればポリシーに反していないかを日頃から意識することで、意図しないポリシー違反を防ぐことにつながります。
例えば日常利用では「気になる情報の質問に留める」「抽出データに誤りがあり得ると理解し、第三者に安易に共有しない」など、ユーザー自ら留意点を設定することで、誤情報の拡散や意図しないポリシー違反を防げます。
企業で使う場合はルール・マニュアルを作成・共有する
仮にビジネスシーン、特に業務用としてChatGPTを使用する場合は、社内ルールの策定や活用マニュアルを作成し、全社に共有する方法が効果的です。
ビジネスシーンで使用するにあたっては、機密情報の漏洩や従業員による意図しない誤情報の生成・拡散、倫理的に不適切なデータの抽出といったさまざまなリスクが潜んでいます。特に、各部門でChatGPTをはじめとした生成AIの利用を承認した場合、あらかじめ組織的な活用マニュアルがなければ企業の危機管理体制の統括が行えません。
ChatGPTなどの生成AIを業務で使用する場合には、全社共通のルールを策定後、マニュアルを作成し、共有することをおすすめします。このほか、下記の方法を検討することも推奨されます。
AIリテラシーの向上を図る
ChatGPTをはじめとする生成AIを活用する場合は、全従業員のAIに対する理解を深めるための研修を実施することをおすすめします。企業によってはMicrosoft製品・サービスを大規模契約しているために、生成AIはCopilotを使用するよう定められているケースもあるでしょう。
ChatGPTやCopilotなどを業務で使用する場合は、AIにできること・できないことや利用時の注意点を理解するAIリテラシーを身につける対策が推奨されます。
AIリテラシーの身につけ方はWebサイトの閲覧でも学べますが、機密情報の漏洩や意図しないポリシー違反を避けるため、AI技術に精通したプロによる研修が望ましいです。
Peaceful Morningでは、DX推進を加速させるプロ人材を紹介するサービス「DX Boost」を提供しています。グループ600万名を超える人材データベースから、貴社に最適なDX人材を即日ご提案できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。AIリテラシーを高めるための人材リソースが不足している際は、お気軽にPeaceful Morningへご相談ください。

\ DX・AI人材を600万名から選抜して提案 /
関連記事:AIリテラシーの概要や注目される理由とは?向上するためのポイントやおすすめの資格も解説
法人向けプランの検討も有効
ChatGPTをできる限り安全に利活用したい場合には、EnterpriseやTeamsといった法人向けプランに加入する方法も有効です。いずれもビジネス利用を想定したプランのため、ビジネスパーソンやシーンを想定した機能を利用できます。
例えば1日のリクエスト上限を引き上げるサービスや機密情報を安全に取り扱うためのセキュリティ強化機能、業界特有の用語や表現を学習させることができるカスタマイズ機能などです。
通常プランとは異なり企業利用に有効な機能が付随するため、安心・安全な利活用を組織的に統括したい場合は、法人プランの検討をおすすめします。
まとめ
ChatGPTのコンテンツポリシーは、生成AIを安心・安全に利用するために制定されたOpenAI社のルールです。ChatGPTを使用する上では利用シーンを問わず、ユーザー1人ひとりがポリシーを遵守する姿勢を持つことが大切です。
企業での使用を承認する際は、AIリテラシーの向上を図りつつ、意図しない情報漏洩の予防を目的に、法人プランの契約を視野に入れて検討することをおすすめします。
ChatGPTを社内導入する際や生成AI活用に有効なデジタル人材の育成を検討する際は、お気軽にPeaceful Morningへご相談ください。

\ DX・AI人材を600万名から選抜して提案 /

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中


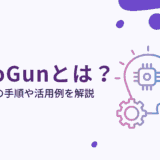
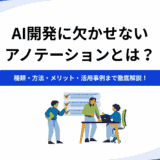
コメントを残す