生成AIは業務効率化に役立つ一方で、セキュリティ面に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実際に、情報漏洩やデータ改ざんなどのリスクが潜んでいます。
本記事では、生成AIによる具体的なセキュリティリスクとその対策を紹介します。リスクを正しく理解し、効果的な対策を講じることで、安全に生成AIを活用できるので、セキュリティ対策を事前に知りたい方は、本記事をぜひ参考にしてください。
関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介
生成AIのセキュリティリスクとは?
生成AIを導入する際には、セキュリティ上のリスクを正しく把握する必要があります。特に外部からの攻撃や、内部の操作ミスによる情報漏洩が代表的です。
リスクを軽視すると、顧客情報や業務データが第三者に流出する恐れがあります。しかし、具体的な危険性を知り、正しい対策を行えば、リスク軽減は可能です。ここでは、生成AIにおける外部・内部の2つの代表的なリスクについて詳しく解説します。
関連記事:生成AI導入・活用時の課題と解決策|注意点と今後の展望を予想
外部からの情報漏洩によるリスク
生成AIには、外部からの不正アクセスによる情報漏洩リスクがあると言えます。例えばAIチャットボットは、攻撃者が狙いやすい対象の一つです。
セキュリティの穴を突かれた場合、保存された個人情報や業務データが盗まれる可能性があります。また、チャットボットが誤った返答をするよう操作される恐れもあります。これらを防ぐには、データ暗号化やアクセス制限、定期的なセキュリティチェックを実施することが重要です。
内部からの情報漏洩によるリスク
生成AIのリスクには、内部の操作による情報漏洩も含まれます。内部からの情報漏洩の例として、従業員がAIに機密情報を誤って入力すると、そのデータが学習されて他の利用者に漏れる危険があります。
AIが以前の会話をもとに回答を生成する場合、思わぬ情報が含まれることも考えられるでしょう。こうした問題を防ぐには、機密データの入力を制限し、AIの出力内容を管理・監視する体制が必要です。
生成AIによるセキュリティリスクの5つの事例
生成AIによるセキュリティリスクの事例を5つ紹介します。
- 事例①データ漏洩とプライバシー侵害
- 事例②プロンプトインジェクションによる情報操作
- 事例③AIが誤った情報(ハルシネーション)を生成
- 事例④権利侵害(著作権、商標権、意匠権など)
- 事例⑤ディープフェイクによるなりすまし被害
それぞれ解説します。
事例①データ漏洩とプライバシー侵害
生成AIが扱う情報には、個人データや社内機密が含まれるケースが多いです。セキュリティが不十分なまま運用すると、第三者による不正アクセスにより情報が流出する恐れがあります。
もし、情報漏洩が発生すれば、企業の信用は失われ、顧客離れにつながるリスクも考えられるでしょう。さらに、個人情報保護法に違反すれば、罰金や損害賠償を請求される可能性があります。AIの学習には、個人情報を使わない設定やアクセス制限などの措置が必要です。
事例②プロンプトインジェクションによる情報操作
プロンプトインジェクションは、生成AIに不正な命令文を与え、意図しない出力を引き出す攻撃手法です。この手法により、通常は非公開となっている内容や、危険性の高い情報が表に出る危険があります。
攻撃者がAIを操作し、結果を改ざんすることで、業務の信頼性が大きく損なわれることもあります。対策としては、入力内容を監視・フィルタリングする仕組みを導入し、異常検知の強化を図ることが有効でしょう。
事例③AIが誤った情報(ハルシネーション)を生成
生成AIは事実と異なる内容を、正確そうな文章で提示することがあります。この現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、ユーザーが誤情報を信じる原因になり得ます。
たとえ正しい情報で学習されていた場合でも、出力に誤りが含まれるケースは完全には避けられません。特にAIの回答が説得力を持っていると、信ぴょう性の判断が難しくなります。重要な場面ではAIの回答をそのまま使わず、人の目による最終確認が必須です。
事例④権利侵害(著作権、商標権、意匠権など)
生成AIの出力物には、著作権や商標権など、他人の権利を侵害するリスクが伴います。特定の作家の作品に酷似した文章や画像を生成した場合、著作権侵害と見なされるかもしれません。
また、出力結果が他人の商標と類似している場合は、商標権の問題が生じます。仮に著作権侵害が認められなくても、自動生成物に対して著作権が発生するとは限りません。商用利用の前には法的観点からの確認が不可欠です。
事例⑤ディープフェイクによるなりすまし被害
ディープフェイクとは、AIを活用して本人そっくりの映像や音声を合成する技術のことです。本物と区別がつかないレベルでなりすましが行われ、詐欺や誤情報の拡散といった問題につながります。
SNSなどで拡散されると、個人の名誉やプライバシーが大きく傷つくおそれもあります。さらに、知らずに拡散に関与してしまう可能性もあるため注意が必要です。情報の発信元を確認する習慣と検出技術の導入が重要となるでしょう。
生成AIによるセキュリティリスクの対策例5選
生成AIによるセキュリティリスクの対策例を5選紹介します。
- 対策①データの暗号化によるセキュリティ強化する
- 対策②プロンプトの安全性を事前にチェックする
- 対策③リアルタイム監視システムを導入する
- 対策④利用ログを記録して監視する
- 対策⑤外部とのデータ連携を最小限にする
それぞれ解説します。
対策①加工やデータの暗号化によるセキュリティ強化する
生成AIの活用には、大量のデータがインターネットを介して移動するため、通信中の情報が狙われる危険があります。特に、個人情報や企業の機密が含まれる場合は、加工や暗号化などによる保護が不可欠です。
匿名加工と仮名加工
加工には「匿名加工」「仮名加工」の2種類があり、それぞれの詳細は以下の通りです。
- 匿名加工:個人情報が特定されないように氏名や住所などの識別情報を完全に削除または置き換える処理です。これにより、誰のデータかを特定することが不可能な状態となり、第三者提供が可能になります。
- 仮名加工:個人を直接特定できないように氏名などを別の記号や番号に変換する処理です。元の情報との照合手段を保有者が保持しているため、内部利用を前提とした安全管理措置のひとつとされています。
注意点として、仮名加工は照合手段を保持している状態のため、引き続き個人情報として扱われます。
データの暗号化
以下は、データの暗号化する際のポイントです。
|
ポイント |
詳細 |
|
通信経路の暗号化 |
生成AIがクラウド上で動作する際、データがサーバー間を移動する過程で通信内容が第三者に傍受されるリスクがあります。 そのため、「SSL/TLS」などの暗号化技術を利用し、通信データを保護することが基本となります。 |
|
データストレージの暗号化 |
学習データなどを保存するストレージも暗号化しておく必要があります。 これにより、不正アクセスが発生しても、暗号化された状態のデータは読み取ることが難しくなり、安全性が高まります。 |
加えて、アクセスできる人物やシステムを制限し、必要最低限の操作だけを許可することも情報漏洩対策として欠かせません。以下のような管理方法が有効です。
|
ポイント |
詳細 |
|
認証と認可の徹底 |
誰がアクセスしているかを確認する「認証」と、適切な権限を持つ人のみ操作を許可する「認可」を設定することで、不正なユーザーのアクセスを防ぎます。 これにより、正しい利用者のみがAIやデータにアクセスできる環境を構築できます。 |
|
役割ベースアクセス制御(RBAC) |
利用者の役割ごとにアクセスできる範囲を細かく設定する方式です。 たとえば、管理者はすべての情報にアクセス可能にし、一般ユーザーは一部の情報のみ操作できるように制御することが可能です。 |
データを暗号化することで、仮に盗まれても内容を読み取られるリスクを大幅に抑えることができます。あわせて、定期的なセキュリティ監査を実施することで、脆弱性を早期に発見し対処できる体制を整えることが重要です。
対策②プロンプトの安全性を事前にチェックする
生成AIに不正な命令を与えるプロンプトインジェクションを防ぐには、入力内容を事前に検証する体制が必要です。不正なプロンプトをブロックすることで、AIの誤作動を未然に防げます。
また、AIモデルに対して定期的にセキュリティパッチを適用し、脆弱性を放置しないことも重要です。フィードバック体制や監視機能を取り入れることで、生成AIの安全性を保ちやすくなります。
対策③リアルタイム監視システムを導入する
生成AIの異常をすぐに発見するためには、リアルタイム監視が欠かせません。不正アクセスや想定外の出力が発生した場合に即座に対応できる体制を構築することで、被害の拡大を防げます。
具体的には、深夜の大量アクセスなど異常な動作を検知し、アラートを出す仕組みが有効です。さらに、不適切な生成結果を自動でブロック・修正できる機能を持たせれば、安全性は一層高まるでしょう。
対策④利用ログを記録して監視する
生成AIのセキュリティ対策として、利用状況を記録することも重要です。ユーザーの操作履歴やシステムの応答内容をログとして保存することで、後から問題の原因を特定しやすくなります。
万が一、情報漏洩や誤作動が起きた場合でも、ログを確認することで迅速に対応できます。また、ログを定期的に分析することで、不審な挙動を早期に発見し、対策を講じやすくなるでしょう。
対策⑤外部とのデータ連携を最小限にする
生成AIの活用では、外部サービスと連携する場面が多くなりますが、過剰な連携はセキュリティ上のリスクを高める原因となります。データが外部に送信される機会が増えるほど、情報漏洩の可能性も広がるため注意が必要です。
最小限のデータで処理を行う設計にすることで、機密情報の外部流出を防ぎやすくなります。不要な接続を避け、必要な場合にも十分な暗号化とアクセス制限を徹底しましょう。
生成AIを活用する際のポイント
生成AIにはセキュリティ上のリスクも潜んでいますが、いくつかのポイントを意識すれば、安全かつ効果的に活用することが可能です。ここでは、活用時に押さえておきたい3つの視点をご紹介します。
攻撃に備えて特定のパターンを学習させる
生成AIは、入力された内容に応じて柔軟に反応しますが、悪意ある攻撃に対しては脆弱な場合もあります。そのため、事前に攻撃の兆候となる入力パターンをAIに学習させ、異常を自動で検出できるようにしておくことが効果的です。
例えば、不正アクセスや不自然な質問内容を識別できるように訓練することで、AIの防御力が向上します。想定されるリスクに備えて、予防的な学習データを用意することが望ましいでしょう。
全て機械に頼らない
生成AIは便利なツールですが、すべての判断を機械に任せるのは危険です。AIは人間と異なり、文脈の誤解や倫理的判断の欠如といった課題を抱えています。
そのため、重要な意思決定や情報発信には、必ず人の目を通す体制を整える必要があります。AIを補助的に活用し、最終判断は人間が行うというバランスを保つことが、安全で信頼できる運用につながるでしょう。
社内でルールを決める
生成AIを業務で使用する場合、利用ルールを明確に定めておくことが重要です。入力してはいけない情報や、出力結果の取り扱い方法をルール化することで、情報漏洩や誤使用のリスクを減らせます。
また、誰がどのような目的でAIを使うのかを記録する仕組みも有効です。社内で統一されたガイドラインを設けることで、全員が同じ意識で生成AIを利用できる環境が整うでしょう。
まとめ
生成AIは業務効率化を実現する一方で、情報漏洩や誤作動といったセキュリティリスクを抱えています。特に、外部からの攻撃や内部の取り扱いミスによるトラブルには注意が必要です。
そのため、暗号化や監視体制の強化、社内ルールの整備といった対策を講じることが重要です。リスクと正しく向き合いながら、安全に生成AIを活用できる環境を整備していきましょう。
RPAやAIなどの自動化ツールを活用し、業務効率を向上させたいとお考えの方は、DX推進支援サービス「Robo Runner」をご活用ください。これまで500名以上の支援を行ってきたエンジニアやコンサルタントが、RPA・AIの導入から運用や社内の開発者育成を支援します。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

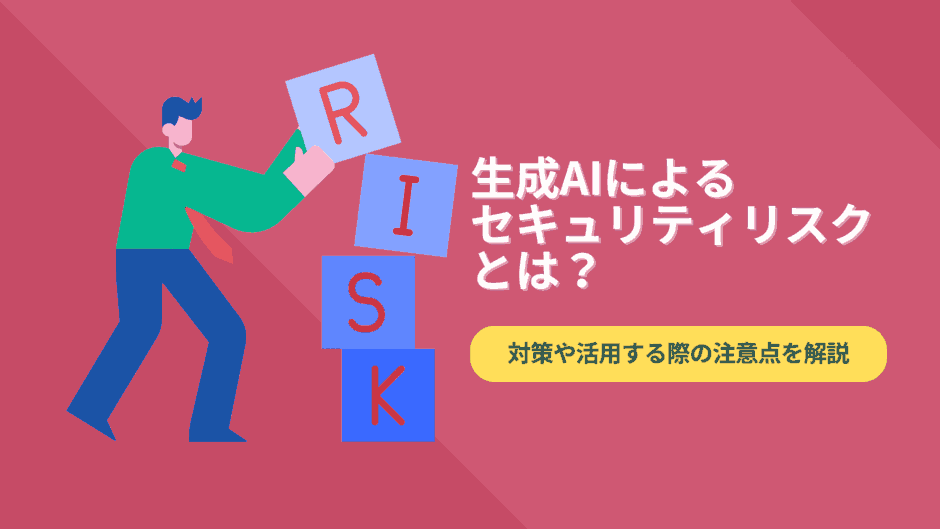

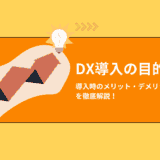
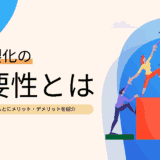
コメントを残す