クライアントや社内従業員、多くの顧客を抱える企業では、メール業務が大きな負担になりがちです。特に、取引先に送信する請求書や発注書、顧客に向けて送信されるキャンペーンメールなど内容がフォーマット化された定型業務は、従業員のモチベーション低下を招くことが少なくありません。
実は、進化を続けるテクノロジーの活用によって、メール業務を自動化できることをご存じでしょうか。この記事では、メール送信業務に潜む悩みを解決するべく、自動化できる業務の種類からツールの選び方まで解説します。現状のメール送信業務を振り返りながら、どのフローを自動化できるのかを押さえ、日常業務の効率化を目指しましょう。
関連記事:業務自動化とは?注目される理由や方法など基礎を解説!

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
目次
メール送信における業務上の悩み
まずは日常的に行われるメール送信業務のなかで、どのフローが悩みになりやすいかを解説します。これまでのメール送信業務を振り返りながらボトルネックになりやすい項目を押さえ、自動化すべき作業フローの特定につなげましょう。
取引先や従業員の数に応じて送信回数が増える
一般社団法人日本ビジネスメール協会がビジネスパーソンにアンケートを実施したところ、1日の平均メール送信数は12.33通、受信数は52.27通、送受信にかかる業務時間は約2時間30分でした。
取引先や従業員数がさらに増えればどの数字も増えることは想像に難くなく、場合によってはビジネスパーソンのなかには日々のメール送信業務に膨大な時間を費やしている可能性が考えられます。
また、メール業務と一口に言っても、送信から受信内容の確認、必要に応じた返信まで多岐にわたり、いずれも日常業務と並行しながら行われているのが現状です。特に、定型的な文章を送信するフローは単純作業になりやすいため、効率化を求める従業員が増えるのも無理はないといえるでしょう。
添付ファイルチェックに時間的コストが掛かる
受信メールに請求書や発注書などのファイルが添付されていた場合、解凍やフォルダ移動、内容に沿ったファイル作成など、付随作業が発生します。送信する側であっても、必要に応じてファイルを圧縮したりパスワードを設定したりなど細かな業務が伴うことから、メール業務そのものに従業員は一定の時間を費やしていると考えられます。
ルーティン業務であることが多い
定型作業が多いこともメール業務における悩みのひとつです。ビジネスメールには定型的な文章作成が多く、自社テンプレートに沿って記述や送信が行われることが珍しくありません。たとえ短文で済む文章でも、件名や宛名、挨拶文や署名は都度記載する場合も多く、テンプレートの流用が可能であっても数をこなすためには相当の時間と労力がかかります。
ツールを使って自動化できるメール業務の種類
テクノロジーのめざましい進化によって、メール業務はツールの活用を通じて自動化を実現できます。ここからは、メール業務のなかでも自動化できる項目について解説します。
メール送信
自動化できる業務のひとつとしてメール送信が挙げられます。送信可能な内容は以下の通りです。
- 請求書・発注書
- 出荷・納品データ
- リマインドメール
- 日報
こうした業務は一般的に所定の日時に送信する必要があり、担当者はスケジュール管理をしつつ日常業務と並行して対応しなければなりません。多くのツールは配信予約(スケジュール設定)機能を備えているため、従業員の負担軽減につなげながら適切な時期にメール送信を行うことができます。
本文からのデータ抽出
自動化ツールの利用によってメール本文から重要な情報を抽出できるようにもなり、業務効率化の実現につながります。例えば抽出した文章をCSVデータ化し、Excelや基幹システムと連携すれば、発注メールの自動作成・自動送信も可能です。人的リソースを最小限に削減できることに加え、クライアントへのメール返信の効率化に期待できます。
添付ファイルの詳細変更・保存
添付ファイルの名称変更や指定したフォルダへの移動も自動化できます。また、送信者名のフォルダが設けられていない場合には、自動的に作成することにも対応しています。
ファイル名を変更する作業や保存先フォルダを探す業務には一定の時間を要することから、取引先や従業員数が多い企業ほど、自動化を通じて仕分け作業の負担軽減に期待できるでしょう。
添付ファイルの圧縮・解凍
自動化ツールによっては添付ファイルの圧縮や解凍作業までを自動化することも可能です。パスワード付きのファイルに対応していることも多いため、圧縮して送信したり解凍して保存したりといった細かな作業にかかる労力を削減し、人的リソースが伴うメイン業務に注力することもできます。
メールの自動化を実現する主なツール
ここからは、メールの自動化を可能にするツールについて解説します。日常業務で使うことの多いツールがある場合は、どのように自動化できるのかを押さえておきましょう。
Gmail
Googleが提供するGmailとPython(またはApps Script)を併用すれば、定期配信や一斉配信などのメール自動化が可能です。比較的シンプルな自動メールではありますが、定期連絡の送信作業から離れられる特徴から、定型的な業務を効率化したい方にとっては有効な方法のひとつです。
送信業務の漏れといった人的ミスも防ぐことにつながり、日常的にGmailを利用する企業や部署であればPythonとの組み合わせを検討するとよいでしょう。
Outlook(Web版・デスクトップ版)
OutlookとOfficeアプリの自動化機能であるVBAを併用することで、多様な作業を自動化できます。例えば添付ファイル名をもとにメールの件名を自動作成したり、転送したいメールの宛先をワンアクションで操作したりなどです。
これらはほんの一例です。日常的にOutlookを使用する方はVBAと組み合わせ、Outlookにおける日常的な作業をワンアクションで効率化することをおすすめします。
メール送信専用ツール
大量のメールを効率的に送信する技術に特化したツールとしてメール送信専用ツールもあります。メールマガジンやキャンペーン、社内連絡など定型の一斉配信であれば、専用ツールの利用で効率化できます。
MA(マーケティングオートメーション)
MA(マーケティングオートメーション)は、日々の定期配信の自動化に限らず、顧客の行動履歴に基づいたメール配信や顧客データをベースとしたパーソナライズメールの送信にも対応しています。マーケティング分野に特化した機能を備えているため、高度なメールマーケティングを自動化したいときに有効です。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
メール自動送信ツールを導入するメリット
多くの従業員が悩みやすいメール送信業務ですが、自動化を可能にするツールを導入することでどのようなメリットがみられるのでしょうか。
業務効率化
これまで従業員が個別対応していたメール送信業務を自動化でき、業務効率化が実現します。メール作成における労力削減だけでなく、送信ミスや誤字・脱字といった人的ミスの防止にもなることから、組織全体の業務クオリティ向上にも期待できます。
セキュリティ対策の強化
多くの従業員が日々大量のメールを送信するなかで懸念されるものとして、情報漏洩が挙げられます。情報漏洩の原因は、ウイルス感染や不正アクセスに加え、誤表示・誤送信などの人的ミスも多いとされています。メール自動送信ツールの導入によって人的ミスでの漏洩リスクを最小限に抑えられるため、セキュリティ対策の強化にもつながります。
また、ツールによってはウイルス感染やスパムへの対策機能も搭載されているため、従来と比べて高いセキュリティ環境の構築にも期待できます。
参考:2024年上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 過去最多の189件
PDCA精度の向上
送信先のクリック率やメールの開封率をチェックできる機能が備わったツールであれば、データ収集の幅が広がることでPDCA精度の向上につながり、マーケティング施策においては多くの効果に期待できるでしょう。
例えば、開封率の高い件名やコンテンツを把握できる機能があれば、顧客ニーズに適しているかを数値で判断でき、顧客が求めるコンテンツや最適なアプローチ方法を検討しやすくなります。
さらに、顧客属性ごとでメール内容を変更した場合でも、ツールの独自機能によって過去と現状を客観的に比較できるため、精度の高いPDCAサイクルを回すことにつながります。
メール自動送信ツールの選び方
ここからはメール自動送信ツールの選び方について解説します。メール送信業務に悩みを抱えていた方は、重視したい項目を特定し、最適なツール選びにつなげましょう。
到達率
到達率は、送信したメールが受信者の受信トレイ(迷惑メールフォルダ回避を含む)に届く割合を示します。どれだけ試行錯誤して魅力的なメールを送信しても、受信者側が自社メールを迷惑メールフォルダに振り分けていれば目を通すことはないでしょう。このような可能性を踏まえ、大量のメールを送信する機会が多い企業は到達率の高いツールを選びましょう。
導入前に公式サイトで到達率の説明を確認し、無料トライアルで実配信テストを行うと、ツール特性とあわせて精度を検証できます。
既存システムとの相性
自社で利用するCRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)と連携できるかについても確認することをおすすめします。既存システムと連携できれば、顧客情報の自動同期やトリガーメール(行動ベース配信)など、より高度な自動化が可能です。
仮に連携機能がない、あるいは自社システムとは連携できないツールを選ぶと、手動によるデータのインポートやエクスポート作業が発生し、かえって業務効率を下げる恐れがあります。導入の際はAPI連携機能の有無や連携可能なシステムについて確認するよう意識しましょう。
対応メール数・高速配信
キャンペーンメールや業務連絡メールなど、短時間に大量のメールを送信しなければならない機会が多い場合は、ツールの対応メール数と高速配信能力についても確認しましょう。確認しないまま導入した場合、一斉送信が原因でシステムダウンを起こし、状況の長期化によっては機会損失を招く恐れがあります。
多くのツールではプランごとに送信数の上限が設けられているため、日常的に送信するメールの規模を考慮しながら最適なプランを選びましょう。
HTMLメールの作成難易度
画像やレイアウトを含むHTMLメールは、テキストメールより開封率・クリック率の向上に期待できます。しかし、HTMLに関する専門知識や技術がない場合、作成が思うように進みません。
こうした課題は、初心者でも容易にHTMLメールの作成が実現するよう、テンプレート搭載やドラッグ&ドロップエディター対応のツールを選ぶと良いでしょう。
特に、新たなアプローチ方法を取り入れた上で既存客の囲い込みや見込み客の誘導につなげたいときは、誰でもハイクオリティなHTMLメールを作成できる機能や環境があるかについても確認することをおすすめします。
セキュリティの内容・充実度
メール自動送信ツールではメールアドレスをはじめとした顧客情報を取り扱うため、セキュリティ環境を万全に整えておくことが推奨されます。ウイルスや不正アクセスの次に誤表示・誤送信といった人的ミスでの情報漏洩が多い点を踏まえ、SSLやTLSによる通信の暗号化や二段階認証、IPアドレス制限などセキュリティ対策に有効な機能の有無について確認することも大切です。
また、ツールを運営する企業がプライバシーマークやISO27001など国際的な情報セキュリティ認証を取得しているかを確認することも信頼性を判断する目安になります。個人情報を守る企業の姿勢は顧客からの信頼獲得につながるため、安心して利用できるツールであるかを必ず確認しましょう。
参考:2024年上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 過去最多の189件
メールの自動送信における注意点
メールの自動送信においてはいくつかの注意点について理解を深めておくことが大切です。ここからは使用時の注意点について解説するので、自動化によるトラブルを防ぐためにも各項目に目を通しておきましょう。
受信者による同意を得る
日本では「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」において、同意を得ていない宛先に対する営業・広告メールの送信は禁じられています。同意を得ていないのにもかかわらず一方的にメールを送り続けた場合、迷惑メールとして報告されたり法律違反による罰則対象になったりするなどトラブルに発展するリスクがあります。
配信リストの作成ではオプトイン(送信許諾)を取得しているかを確認し、記録を保管した上で送信することをおすすめします。
参考:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | e-Gov 法令検索
内容の見直し
メールの自動送信環境に慣れてしまうと、内容を確認する機会が減りがちです。確認を怠ると顧客である読者のニーズとメール本文に不自然さが生じ、開封率の低下を招く可能性があります。特に限定的な製品・サービスや季節・トレンドに影響を受けやすい内容ほど、定期的に見直して修正することが大切です。
自動送信をはじめた後も配信日時や内容はこまめに見直し、常に最新の情報を提供できるよう努めましょう。
オプトアウトの徹底
受信者がいつでも配信停止できるよう、オプトアウト(配信解除)の導線は分かりやすく設けましょう。文末などに「配信停止はこちら」といった一文とともにリンクを置くことで、受信者側に配慮したメール送信につながります。
配信停止までのプロセスが複雑化していると、受信者は不満を抱きスパムとして報告する可能性があります。例えば配信停止を促すリンクをクリックしても、容易な操作で配信停止ができないページ構造だった場合、顧客は強いストレスを抱くでしょう。
顧客のニーズが変化すれば次第に自社のメールが不要になる可能性は大いにあります。メール送信が一方的なものにならないよう、受信者の視点に立った内容を心がけるよう留意しましょう。
配信時間の配慮
メールを自動送信する場合であっても、時間帯には配慮しましょう。特に企業から届くいわゆる広告メールなどは、送信する時間帯によって開封率やクリック率が大きく異なります。例えば深夜・早朝にビジネスメールを送ると、受信者の一部は「非常識」と感じる恐れがあります。
メールを送信する場合は、顧客や取引先担当者などのライフスタイルやメールの目的に応じて最適な配信時間を考慮するよう努めましょう。多くのツールは予約配信に対応しているため、受信者側がネガティブな気分にならないよう最適な時間帯を設定することをおすすめします。
メール自動送信の具体例
メールの自動送信は業務効率化に留まらず、顧客との関係構築やビジネスの成長機会などとしても用いられています。ここからはメール自動送信における4つの具体例について解説します。
1.バースデーメール
バースデーメールは、顧客の誕生日に自動送信するお祝いメールです。普段のクーポンが5%オフであれば、10%オフに割引率を引き上げた自社製品・サービス専用クーポンを添付することで、お祝いの気持ちを届けることと合わせて購買意欲を高める効果に期待できます。
顧客満足度や顧客体験の向上につながれば、企業ブランドに対する親近感の向上にも期待できるため、これまでバースデーメールを使用したことがない方は、この機会に利用してみるとよいでしょう。
2.リマインドメール
リマインドメールは、会議や納期、支払期日などを知らせる自動通知です。1つひとつを手作業で行っていた場合、日常業務との並行によって送信漏れが起こる恐れがありますが、メール送信の自動化を通じて業務の抜け漏れ対策につながります。
従業員や顧客にとっても重要度の高い予定や期限を改めて認識するきっかけになるため、信頼関係の構築に期待できるでしょう。
3.ステップメール
ステップメールは、新規顧客に対して製品・サービスの利用方法や有効な情報を段階的に配信するメールです。例えば顧客がサービスを契約してから1日目には使い方を、3日目には活用事例を、7日目にはサービスに関連する情報を送信する、といった使い方があります。
事前に設定した配信シナリオに沿って段階的に届けることで、疑問や不安を解消し、理解を深める機会になります。
4.メールマガジン
メールを通じて自社製品・サービスに関する新着情報やメディアコンテンツなどを定期的に顧客に届けるアプローチ方法です。顧客ニーズに関する情報の収集・分析データを有効活用することで、顧客に有益なコンテンツ・情報を提供するツールとしても役立てられます。
読者の行動データを使いコンテンツの内容改善に有効なポイントを特定できれば、マーケティング施策の精度向上にも期待できます。
RPAならメール配信の前後の業務も自動化できる
RPAを活用すれば、メール送信にとどまらず、送信前の準備や送信後の処理まで一括自動化できます。これにより、人的ミスを防ぎながら業務効率を大幅に向上させることが可能です。以下に、代表的な活用事例を紹介します。
- 配信リストの自動作成
- 添付ファイルの自動生成
- メール配信後のデータ集計
- 受信メールの自動分類・保存
- 二重配信やエラーの自動チェック
- 報告書の自動作成
なお、メール自動化の後は、開封率・クリック率・到達率などをExcelやGoogleスプレッドシートに自動集計することをおすすめします。各項目をまとめておくことで、市場・顧客ニーズ調査やアプローチ方法の正確性についてデータを基に分析できるようになります。
これらの作業もRPAで自動化できるため、日次・週次で行われていた集計・報告業務をなくし、分析や戦略立案といった人間でなければ進められない業務に注力できます。
関連記事:RPAとは?仕組みや期待できる効果をわかりやすく事例とともに解説
RPAのことならRobo Runnerにお任せ
RPAの導入や開発者の育成を検討されている方は、Peaceful Morningの「Robo Runner」をおすすめします。Robo Runnerは、RPAやAIなどの開発経験豊かなプロが、社内の開発を月額10万円からサポートするサービスです。
これまで研修・サポートした人数は500名以上となっており、RPAプラットフォーム・UiPath製品に関するトレーニング提供において、トレーニング受講者数などの観点から最も貢献したパートナーに与えられる「Training Associate of the Year」を2年連続で受賞し、多くのお客様の業務における問題を解決した実績があります。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
まとめ
メールの自動送信は、日々の定型業務からの解放に加え、生産性向上・品質安定化に有効な方法のひとつです。導入検討においては自社に点在する課題や目的を明確にし、最適なツール選びにつなげましょう。
メール送信そのものだけでなく、配信リスト作成や添付ファイル生成、送信後の集計・チェックまで含めて効率化したい場合は、RPAやAIの活用も有効な選択肢です。定型業務を一連のフローとして自動化することで、作業負担や人的ミスを大幅に削減できます。RPAやAI活用をご検討の際は、導入から運用まで伴走支援を行う「Robo Runner」にぜひお任せください。



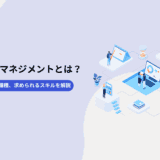
コメントを残す