AIの普及が急速に進むなか、意思決定を伴う業務もAIに一任できるようになれば、人間は人間の能力を必要とする業務に注力でき、業務改善に多く役立つでしょう。
そのような理想を実現させられるものがマルチエージェントAIです。この記事では、マルチエージェントAIの概要と仕組み、代表的なシステムや活用例について解説します。
目次
マルチエージェントAIとは
マルチエージェントAIとは、自律的に判断できるAIが複数連携し、さまざまなタスクを遂行できるAIのことです。マルチエージェントシステムとも呼ばれ、単体のAIでは難しい人間の判断を要する意思決定も適切に行うことができます。
各エージェントAIは独立した行動も可能ですが、フィードバックやコミュニケーションを通じてそれぞれが相互的に作用します。そうすることで、従来のAIと比べて広範囲の処理を実現できる仕組みです。詳細な仕組みについては後述します。
関連記事:自律型AIとは?仕組みや活用例、メリットや注意点をまとめて解説
シングルエージェントシステムとの相違点
マルチエージェントを含むエージェントシステムには、マルチ型のほかにシングル型もあります。マルチ型は複数の自律型AIがタスクを遂行する一方、シングル型はひとつの自律型AIが単独でタスクを遂行する違いがあります。
またマルチ型はそれぞれのAIがフィードバックを行いながら遂行力を向上させるのに対し、シングル型は相互的変化がなく、環境的な変化に順応することが難しいという違いもあります。
固定的なタスク遂行には向いている点や画像や文章生成といった軽微なタスク遂行を希望する場合はシングル型が向いているため、活用シーンに応じて使い分ける方法が有効といえるでしょう。
MoAとの相違点
マルチエージェントシステムは「MAS(Multi Agent System)」と略されますが、このMASと類似する言葉として「MoA(Mixture of Agents)」もあります。MoAはマルチエージェントシステムの概念のうち、大規模言語モデル(LLM)の連携を主軸とするアーキテクチャです。LLMエージェントが各々の得意分野を活かしながら情報処理・問題解決を目指します。
MoAの目的は、データ出力において単一のLLMでは困難とされる高度な推論や多角的な情報の収集・統合、高精度な説明を可能にすることです。それぞれの目的は類似しているものの、得意分野とする部分に違いがあるため、こちらもビジネスシーンに応じた使い分けが推奨されます。
マルチエージェントAIの仕組み
マルチエージェントAIはどのような仕組みで目標達成を目指すのでしょうか。ここからは仕組みについて解説します。
1.プロンプトの提示
まずはユーザー側がプロンプトを提示します。この部分がマルチエージェントAI全体で「これからどのように動くべきか」を考える主体になります。
2.作業分解・各タスクに分解
次にメインとなるエージェントAIがユーザーによるプロンプトの内容を把握し、複数のエージェントAIに分けます。この部分がタスク分解と呼ばれる構造です。
3.各AIが役割分担し目標を達成させる
次にメインエージェントAIが各エージェントAIにタスクを割り当て、目標達成を目指します。各エージェントAIはそれぞれの専門分野のなかでも最適な手段を選択しながらタスクを遂行します。データ解析に特化したもの、LLMに特化したものなどが独自にタスク遂行を目指し、プロンプトに対する最適解へと導く構造が基本的な仕組みです。
代表的なマルチエージェントAIシステム
ここからは、代表的なマルチエージェントAIシステムについて解説します。なお、2025年7月時点の情報であるため、記事公開時に変更されている場合があります。
AutoGen
「AutoGen」はMicrosoftが開発したオープンソースでの利用が可能なマルチエージェントAIシステムです。ソフトウェア開発に関するコードの自動生成からテスト、データ分析、技術文書の作成支援など総合的なサポートが受けられます。エージェントAIに留まらず人間との協調にも対応しており、信頼性の高いエージェントAIシステムのひとつです。
CrewAI
「CrewAI」はJoão Moura氏が開発したオープンソース型マルチエージェント構築フレームワークです。ビジネスユース向けなので、ビジネスシーンに活用できるエージェントAIをコストを掛けずに独自開発したい方におすすめです。Pythonをベースにしているため、Pythonに精通した方であればスムーズな開発が実現できるでしょう。
Semantic Kernel
「Semantic Kernel」はMicrosoftが提供するオープンソース型ソフトウェア開発フレームワークです。ソースコードは一般公開されているため、プログラミング経験がある方であればLLMをデータに素早く接続・統合できます。文章や音声データからその内容を理解する特徴があり、現在では検索エンジンやAIチャットボット、音声アシスタントといった多様なシーンで活用されています。
セマンティック カーネルの概要 | Microsoft Learn
The AI Scientist
「The AI Scientist」は元Google研究者らが立ち上げたSakana AIが開発したエージェントAIです。研究開発プロセスの自動化を可能にする特徴から、研究アイデアの提案から査読までのサポートが受けられます。生成コストも論文1本あたり$15以下なので、コストを抑えながら研究にまつわる作業を自動化したい方におすすめです。
新手法「TAID」を用いた小規模日本語言語モデル「TinySwallow-1.5B」の公開
マルチエージェントAIのメリット
ここからはマルチエージェントAI活用でみられるメリットについて解説します。
迅速かつ高度な意思決定の実現
マルチエージェントAIは自律型AIが複数連携し、それぞれの専門性を活かしながらタスクの完遂を目指します。そのため、人間では膨大な時間と労力が掛かるタスクが素早く終わらせられるだけでなく、重要な意思決定も実現できるメリットがあります。
それぞれの適性を活かしつつそれぞれがフィードバックを行い協調的にタスク達成を目指すので、人間による意思決定までのステップを大幅に短縮できるのは大きなメリットです。
容易なシステム拡張
マルチエージェントAIは専門分野ごとにエージェントAIが分かれているため、新たに機能を追加したり既存機能を強化したりする際に、システム全体を大きく変更する必要がありません。必要なエージェントを追加または修正するのみで済むので、システム拡張が容易な点もメリットです。
安定的な稼働
システムの構造が複数のエージェントAIに分散された仕組みであるため、一部のエージェントAIにトラブルが発生しても、他エージェントAIが補完あるいはタスクの引き継ぎが行われます。システム全体のダウンタイムが減少することから、社内の業務停止が比較的軽微で済む点もメリットのひとつです。
マルチエージェントAIの活用例
ここからはマルチエージェントAIがどのように活用できるのかをより深く理解できるよう、活用例について解説します。どのような業務に応用可能かを把握し、自社ビジネスの効率化・自動化を図りましょう。
社内用AIチャットボット
社内用AIチャットボットにマルチエージェントAIを導入することで、全従業員からの業務やシステムに関する問い合わせ対応業務を効率化・自動化できます。比較的届くことの多い問い合わせ内容やFAQなどの提示によって複数のエージェントAIが連携・タスク分担をし、必要な情報を必要なときに収集できるようになります。
翻訳
マルチエージェントAIの社内導入によって翻訳業務を素早く終わらせることも可能です。メールやチャットツール、必要情報などの翻訳に時間が掛かることも多いですが、この作業を一任することで素早い対応が可能になります。
グローバル化を目指す企業であれば多国語を網羅的に把握する必要がありますが、各国の言語を学ばなくても素早い意思決定を実現できます。
情報収集・分析・レポート作成
マルチエージェントAIは多様な話題の情報収集から分析、それらを統合しユーザーの求めるレポート作成も可能です。ビジネスシーンでは多くの情報を取り扱いながら自社競争力を高めていく必要がありますが、その際に必要となるものが根拠となる情報であり、収集には多くの時間と労力が伴うことが多いです。
この業務を一任できれば、従業員は人間の手・能力を求める業務に配置できるようになるため、従業員配置の最適化や生産性の向上、従業員1人ひとりのスキルアップなど多様なメリットにつなげられます。
マルチエージェントAIの課題と対策
これまでのAIよりも利便性が高く高性能が見込まれるマルチエージェントAIですが、導入・使用にあたってはどのような課題があるのでしょうか。ここからは主な課題と対策法について解説します。
複雑な設計
複数のエージェントAIが相互作用を生み出し、自律的な行動・判断をアップデートする特徴から、システム全体の設計が複雑という課題があります。一任する業務によってはさまざまなエージェントAIを確立させる必要もあり、コミュニケーション方法や協調メカニズム、競合解決方法などは慎重に構築することが求められます。
仮にマルチエージェントを設計する場合には、スモールスタートで始め、効果などをみながら段階的に設計を進める、既存のフレームワークを活用するといった工夫によって対処できるでしょう。
コスト
複数のエージェントAIを構築しなければならない点から、保守運用にあたってはそれぞれの開発にコストが掛かることにも注意しなければならないでしょう。また、構築にあたっての通信コストや初期費用などが高額になる可能性もあります。
開発する場合であれば、メッセージサイズの最適化を図る、通信プロトコルを効率的なものに切り替えるといった方法によってコストは抑えられるでしょう。事前に投資収益率の可視化を行い、費用対効果を明らかにすることも大切です。
セキュリティ
膨大なデータをエージェントAIそれぞれでやり取りすることから、データの漏洩やサイバー攻撃などに対するセキュリティ強化も実施する必要があります。仮にサイバー攻撃を受けてしまえば、自律的なエージェントAIが悪用される、あるいは意図しない結果を生み、企業損失につながる恐れがあります。
特にオープンソースタイプのマルチエージェントAIを活用する場合は、堅牢なセキュリティを自社システムに組み込むことが先決です。また、使用する従業員をごく一部に限定し、従業員による情報漏洩を防ぐガバナンス強化なども実施する必要があります。
関連記事:AIにおけるリスクとは?利用者、提供者などへのリスクや対策方法を解説
人材確保
マルチエージェントAIを活用するにあたっては、まず自社業務に適切なツール・システムを判断するべく、既存業務に潜む非効率な部分を洗い出すことが大切です。社内に点在するあらゆる業務を1つひとつ洗い出すためには、従業員へのヒアリングやアンケートなどを用いることで具体化できます。
速やかに非効率な業務を特定したい場合は、社内リソースのみに頼らず、外部の専門リソースを活用することを推奨します。業務分析に特化した外部パートナーに依頼することで、より客観的かつ効率的な分析が可能になります。
Peaceful Morningが提供するBUSINESS INSIGHTでは、プロの視点から業務を可視化するコンサルティングサービスを提供しています。現場への丁寧なヒアリングや業務データの分析を通じて、属人化や非効率の要因を明らかにし、次のアクションへとつなげます。
関連記事:AIリテラシーの概要や注目される理由とは?向上するためのポイントやおすすめの資格も解説
まとめ
マルチエージェントAIは、従来のAIとは異なり、複数の自律的AIが連携し、1つのタスクを完遂する技術です。プロンプトにある内容を細かく分けたあと、エージェントAIの専門分野ごとにタスクを振り分け最適解を導くことから、人間の判断を必要とする重要な意思決定にも活用することが可能です。
社内導入によって多くの業務・作業を効率化・自動化できるメリットがある一方、運用にあたってはコストや労力が掛かることから、事前にDX推進部門などを設置し、スモールスタートで進めることが望ましいです。
Peaceful Morningでは、専任のエージェントがヒアリングを通じて貴社のAI活用推進に必要な人材を即日ご提案するサービス「DX Boost」を提供しています。社内リソースでは開発や導入が難しいと判断される際は、ぜひお気軽にご相談ください。

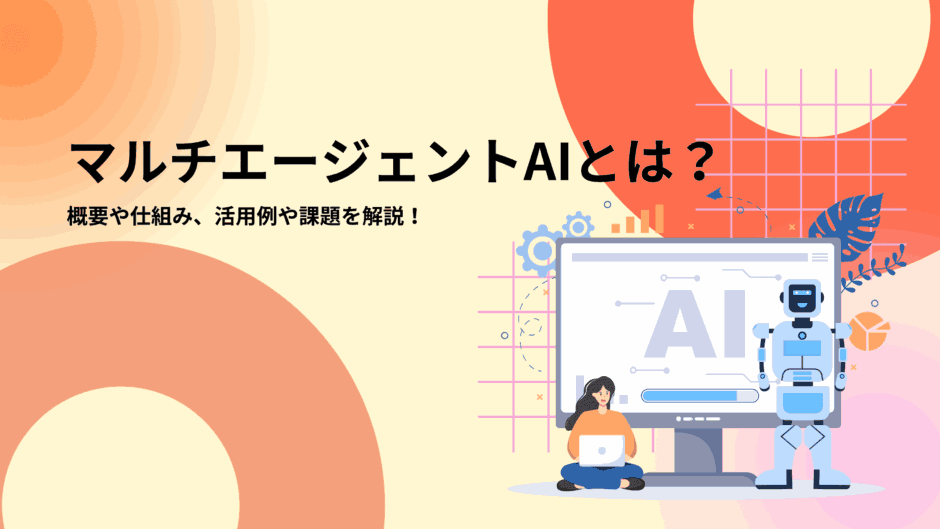


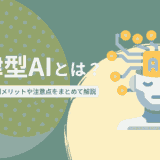
コメントを残す