ChatGPTをはじめとした生成AIを活用する際は、使用における留意事項を把握することが重要です。生成されたデータは主にインターネット上で閲覧・表示できるテキストデータを学習データとして使用しているため、そのまま使用すれば思いがけないトラブルを招く可能性があります。
このようなときに押さえておきたいのがリスキリングであり、生成AIを多用する上で必要な知識を学ぶことができるため、重要性が高まっています。この記事では、生成AIにおけるリスキリングの概要とメリット、ロードマップなどについて解説します。
生成AIのリスキリングとは
リスキリングとは、デジタル技術の急速な進化に対応するべく、個人・組織が必要な知識を新たに習得するプロセスです。そのなかで提唱された「リスキリング革命」では、IoTやAI、ビッグデータを搭載した技術革新の変化に対応したスキルを獲得するため、2030年までの間、およそ10億人に対して今以上によい教育とスキル、仕事を提供するとしています。
2022年10月には日本でも、岸田前首相が今後5年間で1兆円をリスキリング支援に投じると表明しています。
参考:AI導入で労働者の40%はリスキリングが必要–IBM調査 – CNET Japan
参考:リスキリング支援「5年で1兆円」 岸田首相が所信表明 – 日本経済新聞
なぜ生成AIに特化したリスキリングが必要なのか
生成AIにおけるリスキリングが注目される理由は大きく2つあります。1つめは日常業務で生成AIを使う機会が増えていること、2つめは業務の一部を生成AIで自動化できることが社会全体で浸透しつつある点です。
いずれにしても、業務と生成AIを掛け合わせるためには、生成AIに潜む課題やデメリット、注意事項に留意し、その上で正しく利用することが求められます。そのため、リスキリングによる学習の機会を設けることが重要視されています。
生成AIにおけるリスキリングのメリット
今や企業レベルで導入が進む生成AIですが、リスキリングによってどのようなメリットに期待できるのでしょうか。ここからは6つのメリットについて解説します。
業務効率化への期待
リスキリングを通じて生成AIに対応できる人材が確保できれば、業務効率化につながります。例えば定型的・反復的な業務を自動化したり、情報収集・分析を迅速にしたりするなど、多様なビジネスシーンでの効率化が期待できます。
セキュリティリスクへの対策
リスキリングによって情報漏洩や誤情報の拡散リスクを低減できます。生成AIには誤情報であるにも関わらずあたかも真実のようにデータを生成してしまうハルシネーションがあります。生成AIのなかでも大きな課題のひとつであることから、リスキリングによってどの部分に注意すべきかを理解し、使用上の安全性を確保できるでしょう。
新たなアイデアの創造
生成AIはインターネット上で検索・閲覧できるテキストデータを資料として学習しています。そのため、既存のデータや知識に基づきながらも新たなコンテンツやアイデアを生み出すことを可能にします。
人材採用の削減
既存従業員が生成AIスキルを身につけることで、デジタル人材の採用コスト削減にもつながります。生成AIに特化したリスキリングによって従業員のスキルアップも見込まれ、労働意欲の向上やそれによる生産性の向上にも期待できます。
DX推進の加速
リスキリングによって生成AIに対する従業員のスキルの底上げができることから、生成AIの導入を機に社内DXが加速します。生成AIをはじめ、近年はデジタル技術そのものが急速に進化しています。どのようなことに気を付けるべきかを把握しているため、DXを今以上に推進することも可能です。
AIリテラシーの向上
生成AIにおけるリスキリングによって従業員全体のAIリテラシーが向上します。その結果、どのようなデジタル技術を導入するとしてもその環境に順応でき、企業の競争力強化にもつながります。
関連記事:AIリテラシーの概要や注目される理由とは?向上するためのポイントやおすすめの資格も解説
生成AI活用に有効なロードマップ
生成AIの活用を企業レベルで成功させるためには、適切に進めるための計画が欠かせません。ここからは個人レベルと企業・組織レベルの観点でみた場合に有効なロードマップについて解説します。
個人レベル
個人レベルでは、組織に従事する従業員が安全かつ適切に生成AIを使用できるようになることを目指すことが先決です。例えば、企業側が推奨する生成AIツールや環境について明示する、プロンプト作成スキルの向上を図るなどです。
企業側が生成AIツールを推奨し、それと同時に使用環境も整えておけば、従業員が独自でツールを導入する可能性が減り、情報漏洩リスクを下げることができます。また、プロンプトの書き方や社内に有効なプロンプトも共有できる環境が整えば、生成AIの活用促進につながります。
企業・組織レベル
企業・組織レベルでは生成AI活用に関するアイデアやスキルの共有、高度化を目指すことが大切です。生成AIはさまざまな機能を搭載しているために、活用範囲が広い特徴があります。そのため「いつ」「どのようなシーンで」「どのように活用すべきか」などの活用内容がイメージしやすくなるよう、社内の活用事例を蓄積し全社に共有する方法が有効です。
使用シーンや活用事例を一目で閲覧できる生成AIマニュアルを作成・共有すれば、細かなミーティングをせずとも認識のすり合わせが実現します。高品質なデータを抽出できたプロンプトは、随時マニュアルにまとめることで再利用可能なプロンプトとして残り続け、組織資産となるでしょう。このような取り組みによって業務プロセスの変革も実現可能です。
生成AIのリスキリング|国内企業の導入事例
ここからは、生成AI活用に向けて実際にリスキリングに取り組んだ国内企業の事例について解説します。
キヤノン株式会社
キヤノン株式会社では、DXを担う人材育成を目的にDXリテラシー教育とキャリアマッチング制度における研修プログラムの改定を実施しました。AIとクラウド技術を初学者に身につけてもらい、デジタル技術を使ったことのない未経験者を再配置しDX人材の増強を目指しています。
参考:キヤノンがDX人材を2方面から増強、現場の底上げとリスキリングで | 日経クロステック(xTECH)
ソニー株式会社
ソニー株式会社では事務職・技術職を含む多種多様な従業員を対象に技術レベルの底上げを目的としたAIリテラシー研修を実施しています。AI概論から活用アイデアをはじめとした全6テーマで構成された研修を通じて従業員全体のAI理解を図り、製品・サービスの向上を目指しています。
参考:ITmedia NEWS|ソニー、社員に独自のAI研修 講師も社員 事務職含む4万人対象
ダイキン工業株式会社
ダイキン工業株式会社ではDX推進の一環としてAI関連の知識保有従業員の育成に力を入れるためのリスキリングを実施しています。AI活用によって業務効率化に留まらず新たな顧客価値の創造を目指すべく、AI活用に向けた研修や実践機会を提供しました。生成AIを活用し、従業員による製造現場でのデータ分析を可能にするための教育も取り入れています。
参考:東洋経済オンライン|AIの本格実装に見いだす日本の製造業の勝ち筋 ダイキンのDX人材が示すAI活用の可能性
富士通株式会社
富士通株式会社では将来的なビジネス成長に必要な人材を確保するため、AIやIoTといった新たなデジタル技術を中心に従業員へリスキリングを実施しました。社内スキルを習得できるようオンライン教材や学習プラットフォームの提供を行ったことで従業員が自発的にスキル習得を行えるようになり、社内従業員の開発を成功に導いています。
参考:リクナビNEXTジャーナル|リスキリングとは?富士通の事例に見るリスキリング推進の理由とビジネスパーソンのメリット
株式会社divx
株式会社divxでは独自のAIリスキリングアプローチにより、社内のAI導入率を100%に導いています。このノウハウを組織資産とし、生活AI普及協会が推奨するプロジェクトにも参加しました。また、将来的にさらなる需要が予測される生成AI人材が適正に評価されるよう、同社では雇用環境構築にも取り組んでいます。
参考:PR Times|AI×雇用のトレンドを牽引!DIVXが実現する「AIリスキリング」で雇用変革
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントでは生成AI活用の推進を目的に「生成AI徹底理解リスキリング」を開始しました。全執行役員を含む従業員が講義動画の視聴を完了させ、Webテストに合格しています。同プログラムはCAリスキリングパートナーズによって外部企業への提供もスタートさせ、各企業の競争力強化にも役立てています。
参考:CyberAgent Way|サイバーエージェントの99.6%にあたる社員・全役員が受講した「生成AI徹底理解リスキリング」とは?
LINEヤフー株式会社
LINEヤフー株式会社は企業内大学「Zアカデミア」でリスキリングに力を入れています。文系従業員向けの講座も充実しており、さまざまなプログラムを通じて生成AIの業務活用法などを習得できます。
Zアカデミアはイノベーションを生み出すための「ベースキャンプ」という目的も担っており、絶えず変化するビジネス社会において同社からの新たなイノベーション創出が期待されています。
参考:ITmedia ビジネスオンライン|Zホールディングスで人気の「Z文系AI塾」とは? 社内外の人材交流も促進:人的資本の施策ともリンク
生成AIのリスキリングを成功へ導く4つのコツ
生成AIに関するリスキリングは必要スキルの習得だけでなく、身につけた知識がどのように活かせるのかを理解するための実践機会が欠かせません。この点を重点に、ここからは生成AIのリスキリングにおけるコツについて解説します。
1.習得すべきスキルの洗い出し
生成AIは多くの種類があることから、活用シーンや対応範囲が多岐にわたります。企業によっても求められるスキルが異なることから、まずはどのようなスキルを習得するべきかを明らかにしておきましょう。
- 生成AIの概念や仕組み
- 著作権・倫理といったリスクとルールへの理解
- 画像・動画・文章など各生成AIの操作スキル
- AIを活用したプログラミングスキル
- AIを活用したデータの収集・分析・予測スキル
- 真新しいビジネスモデルを創出するスキル
上記の項目は、業界によって優先順位が異なることがあるため、企業戦略と照らし合わせた上で洗い出すことをおすすめします。
2.従業員レベルに適した研修制度の導入
次に、従業員レベルに適した研修制度の導入です。例えば生成AIの初学者と中級者であれば、下表のようにコンテンツ内容をグループ分けすると無理なく習得できるでしょう。
| 初級 | 中級以上 |
| ・生成AIの概念、仕組み ・基礎知識・種類 ・専門用語 ・活用事例 |
・分野別でみる活用方法、事例 ・実践 ・最新の動向研究、ツール共有 |
適切かつスムーズなリスキリング実現に向けて、まずは従業員のAIスキルレベルを洗い出しましょう。
3.実践機会の提供
リスキリングの効果を向上させるため、次は実践機会を提供しましょう。リスキリングは学んで終わりではなく、日々の業務に役立て、成果を生むことです。実際の業務課題をテーマにして生成AIを使用する、自身の業務でツールを操作してみるなどの方法が効果的です。
4.継続的な人材育成環境を検討・構築する
生成AIの進化に順応するべく、常に最新情報を取り込みながら従業員スキルのアップデートを図りましょう。生成AIは急速に進化しており、モデルや機能、対応範囲などが大きく変化しやすいです。1度のリスキリングで終わらせてしまえば、めまぐるしく成長を続ける生成AIに順応できず、競合に後れを取る場合もあります。
社内リソースでは限界がある場合は、外部リソースを頼りながらデジタル人材の育成・確保を実現させるとよいでしょう。
まとめ
生成AIは日々の進化によって対応可能な業務・作業が広がり続けています。適切な使用にあたっては、生成AIの進化に順応するためのリスキリングが必要であり、学習・コンテンツ内容にもアップデートを伴う場合があります。
生成AIのリスキリングや業務効率化の取り組みを社内で推進したい場合は、Peaceful Morningの「Robo Runner」をご活用ください。RPA・AIなどの開発経験豊富なプロが、月額10万円から生成AI活用の導入・開発・運用まで伴走型でサポートします。
Robo Runnerでは単なる座学ではなく、実際の業務課題を題材にしながら実践を通じて生成AIスキルを習得できるため、学んだ知識をすぐに現場で活用できます。
無制限のチャットサポートやWebミーティング、豊富なeラーニングコンテンツに加え、プロのサポートによる実践的な学習環境を提供し、企業の生成AIにおけるリスキリングとDX推進を全面的に支援します。




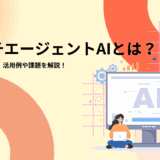
コメントを残す