デジタル技術の進化により世界的にDX化が進むなか、AIを使い業務の効率化・自動化を図る企業が増えています。AIの使用にあたっては、特性について正しく理解し適切に運用していく姿勢が欠かせません。仮にAIに潜むリスクや注意点を知らずに利用していた場合、企業に損害を与える可能性があるためです。
AIを正しく使うために身につけておきたいものとして挙げられるのが「AIリテラシー」です。本記事ではAIリテラシーの概要をはじめ、向上するためのポイント、おすすめの資格について解説します。従業員を中心に組織全体のAIに対する理解度や活用スキルの底上げを検討する企業担当者の方はぜひ参考にしてください。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
目次
AIリテラシーとは
AIリテラシーとは、AIの特性や機能、注意点などについて理解したうえで正しく使用できる能力のことです。本来、リテラシーとは「読み書きする能力」を指しており、近年よく見聞きする「ネットリテラシー」や「ITリテラシー」「DXリテラシー」などは、リテラシーの前に付随する言葉+正しく使いこなせる能力といった意味があります。
本記事で解説するAIリテラシーは、次の3つに分類できます。
- AIに関する知識
- AIを説明できる能力
- AIを活用する能力
ここからはAIリテラシーに求められる3項目について解説します。
AIに関する知識
AIができることにはさまざまな事柄がありますが、具体的には議事録の自動生成やアイデア出し、アンケート結果の分析などが挙げられます。このように、AIにできること、できないことについて一定の知識を身につけることが求められます。さらにAIの基礎として、特性や機能、深層学習(ディープラーニング)などについての知識も必要です。
AIを説明できる能力
AIリテラシーを学ぶうえでは、AIについて説明できる能力も欠かせません。
- どのようなことができるのか
- どのような注意が必要なのか
- 使用にあたってどのようなリスクがあるのか
このような項目について説明できれば、誰に対しても説得力のある説明ができます。AIの持つ特性と限界について適切に説明できるようになれば、組織が抱く誤解や不安を取り除きながらAI技術の活用、さらにはDX推進に結びつけることも可能です。
AIを活用する能力
AIを実際に使いこなす能力も必要です。例えばOpenAIの「ChatGPT」などをはじめとする生成AIにどのようなプロンプトを提示するべきかを理解している、またはAIを適切に組み込める方法を把握しているなどが該当します。
AIを正しく活用するスキルがあれば、導入前の段階から社内への使い方の周知や教育が可能となり、スムーズな展開が実現します。あらかじめ利活用に向けた環境構築が行えるため、AIに潜むリスクを最小限に抑えた利活用が実現するでしょう。
AIリテラシーが注目される理由
AIリテラシーが注目される理由は使うシーンや状況によってさまざまですが、一般的には以下4つの理由が挙げられます。
AIの活用シーンが増えている
AI技術の進化によって活用するシーンが増えているからこそ、正しく使用するための知識としてAIリテラシーが注目されています。業務や作業をAIで代替する企業が増加していますが、使い方を誤ると情報漏洩や著作権の侵害といったリスクに晒される危険があります。
日常的にも利活用する機会が増えたAIだからこそ、ビジネスパーソンに限らず、最近では自分ごととして捉える方がAIリテラシーを身につけるケースも増えています。
AIの活用によって業務の効率化に期待できる
AI技術を活かし業務を効率化する際にもAIリテラシーは欠かせません。例えばAIチャットボットを導入すると社内の問い合わせ数が減り、本来の業務が遂行しやすくなる一方で、使用方法や注意点について把握している人材がいなければ適切に運用することはできないでしょう。
効率化に限らず、本来の業務・作業をAIで代替・自動化させる場合において、AIの知識が何かと求められやすい点も理由のひとつです。
トラブルが起きる可能性がある
AIのリスクマネジメントを目的とするケースも理由のひとつです。例えば生成AIに画像生成を依頼すると既視感を覚える画像が生成されることがありますが、これはAIの特性のひとつで、インターネット上で収集した誰かが過去に作成した作品を模していることが理由です。
そのため、AIが生成するモノが誰かのモノから影響を受けているという特性を知らないまま抽出されたデータを使用した場合、著作権侵害につながる可能性があります。
AIは意図せず酷似したコンテンツや表現を生成することがまだまだ多いことから、気付かぬうちにトラブルを生まないためにAIリテラシーを身につけておくことも求められています。
誤情報・偽情報に騙される危険性がある
AIはインターネット上にある資料などをもとにデータを生成しますが、誤った情報を収集した場合、誤ったデータを生成する場合があります。AIリテラシーを身につけていると、AIの特性を理解し、事実かどうかを自身で調べトラブルを避けることができます。
しかしAIリテラシーが低いと、AIの特性について理解が浅いために、誤情報とは知らず他者に共有し、大きな誤解を与える危険性があります。一例として、AIが生成した誤情報をそのまま信じて拡散してしまったケースではありませんが、2016年の熊本地震時にSNS上で拡散された「ライオンが逃げた」というデマのように、情報を見極める力の重要性は高まっています。AIが生成する情報の正確性を常に疑い、確認する姿勢がAIリテラシーには不可欠です。
AIリテラシーは今やAI技術を使う企業だけでなく、情報を取得するユーザーそのものに求められる能力と考えられます。
参考:「ライオン逃げた」熊本地震のデマ情報を拡散した疑い 20歳男を逮捕 | ハフポスト NEWS
関連記事:AIにおけるリスクとは?利用者、提供者などへのリスクや対策方法を解説

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
文部科学省が掲げるAIに関する目標とは
AI技術はその利便性の高さにより、ビジネスシーンに留まらず日常生活でも広く利活用されています。国民がAIを活用する機会が増えたことを受け、文部科学省ではAI教育プログラム認定制度の創設や学校でのAI教育を進め、全ての国民がAI技術を正しく利用できることを目指しています。
AIリテラシーは、その技術の高さによってAIを利活用する全ての人が身につける必要のある知識・能力です。だからこそ、日常業務でAI技術を活用するビジネスパーソンほどリスクと隣り合わせであることを理解し、早急に身につけるべき能力といえるでしょう。
参考:数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度:文部科学省
AI時代を生き抜く!AIリテラシー習得5ステップ
AI技術が多くのシーンで利活用される時代だからこそ、ビジネスシーンで活用する方ほど早急に身につけることが求められます。ここからは、AIリテラシーを習得するための5ステップについて解説します。
1.AIを正しく理解するための基礎知識を身につける
まずはAIについて正しく理解するため、基礎知識を身につけましょう。ディープラーニングや機械学習、ニューラルネットワークといった基本用語を押さえておくとAI技術の導入に際して説得力のある説明が行えます。書籍だけでなく、AI技術の発展によって今ではオンライン講座なども設けられているので、自身のペースで取り組めるものを活用してみましょう。
2.AIの実用事例から業務への活用可能性を考える
次にAIの実用事例に目を通し、自身の業務あるいは組織全体の業務にどう活用できるかを考えましょう。自身が携わる業界やAI技術を活用した企業の成功事例などをリサーチすることで、AI技術やツールについて知識を深められることに加えて、日常業務のどのシーンで利用できるのかがイメージしやすくなります。
3.AIツールに触れてみる
AIができることについてある程度把握していても、どの程度までできるのか、どのような質問だと誤情報が生じやすいのかなど、詳細について把握している方は少ないでしょう。これらのことから、AIリテラシーを深めるためには、積極的にAIツールに触れてみることをおすすめします。OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」であれば無料で利用できます。
また、Microsoft Officeソフトを利用している方であれば「Copilot」が内蔵されているので、さまざまなツールを使いどのようなことができるのかについて調べてみましょう。
4.AI活用に伴う倫理的・社会的な課題と向き合う
AI技術の進化に応じるため、活用を視野に入れる場合は倫理的・社会的な課題について理解を深めることも大切です。AIはインターネット上にあるさまざまなデータを収集したうえで新たなデータを抽出します。そのため、AIに提示するプロンプトによっては、誤った情報や誤解を与えかねない情報、誰かを傷つける情報が抽出される場合があります。
AIにはできることが多くある一方で、完全ではありません。AIによって生成されたデータには誤りや著作権侵害に発展しかねない情報、多くの人を誤解させる恐れのある情報があると理解することもAIリテラシーを身につけるうえで大切な項目です。
5.進化するAI技術を継続的にキャッチアップする
AI技術はめまぐるしく発展し続けています。そのため、AI技術についてキャッチアップする姿勢を持つことも大切です。AI技術の進化内容については、SNSやWebサイトなどでも閲覧できます。
しかし、いずれも正しい情報がある一方、誤情報が投稿されている場合もあります。AIに関する情報を得る際は、AIリテラシーの向上を視野に入れ、情報の正当性を自身で調べるクセを付けることをおすすめします。
AIリテラシー向上におけるポイント
AIリテラシーを向上させる際は、以下のポイントを意識してみましょう。
AIについて理解を深める
前提として、AIはできることが複数あったとしても、完璧な存在ではないことを理解しましょう。文書や画像、動画の生成のほかプログラミングコードの生成なども実現可能なAIですが、インターネット上の資料・データをもとにデータを生成するために、すでに存在するデザインを模したり、見たことのあるような映像を生成したりする場合があります。
AIに任せれば問題ない、AIの導入によって業務全てが効率化するといった考えは、自身の意図せぬところで大きなトラブルを招く可能性があります。AIリテラシーの向上を図る上では、AIが生成したデータは必ずファクトチェックを行う、正しい情報を覚えさせるなどの工夫を心がけることが大切です。
AIに精通した人物に相談する
AIツールの利活用において少しでも不安が残るときは、AIに精通した人物に相談することをおすすめします。自社内にいないときは、外部パートナーに相談するのも方法のひとつです。
AIに関する知識を十分に身につけたとしても、完璧に運用できるとは限りません。仮に企業にAIツールを導入したとしても、正しい知識・技術を身につけた人材がいなければ、正しい利活用にはつながらないためです。
AIツールを含むDX導入に向けた取り組みに対して経済産業省は必要に応じて外部パートナーの利用を推奨しています。自社従業員だけではAIリテラシー教育が難しいときなどは、この機会に外部パートナーとの連携を検討するとよいでしょう。
参考:経済産業省|デジタル トランスフォーメーション DX銘柄2024

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中
AIツールを活用する
AIツールによって特性は大きく異なります。できることとできないことはある程度同じですが、生成するデータの精度などは異なる場合が多いです。AIリテラシーの向上を目指す方はさまざまなAIツールを使用し、どの作業にはどのAIツールが適しているかなどを自身で調べてみましょう。
AIリテラシーを高められる資格
ここからは、AIリテラシー向上に有効な資格を4つ解説します。
生成AIパスポート
「生成AIパスポート」は生成AI活用普及協会(GUGA)が主催する日本最大級の生成AI資格試験です。同協会には日本を牽引するAI有識者が50名以上所属しており、AIに関する経験などに基づき、豊富な知識を身につけることができます。
生成AIの基礎知識や活用方法について正しく理解したい方や、生成AI活用レベルを社内外にアピールしていきたいと考える方におすすめです。年代や業種を問わず全国の10代から70代以上の方が合格しており、有資格者は年々増加傾向にあります。同資格の詳細については同協会公式ホームページをご確認ください。
参考:生成AIパスポート(一般個人向け)|生成AIリスクを予防する資格試験
G検定(ジェネラリスト検定)
「G検定」は一般社団法人日本ディープラーニング協会が主催する検定のひとつで、AIやディープラーニングの活用リテラシーを習得することを目的とした検定試験です。AI・ディープラーニングを体系的に学習することで、AIにはなにができてどのようなことを不得意とするのか、どのようなシーンでAIは活用できるのかについての理解を深められます。
同検定の取得によってデータを活用した新たな課題の特定やアイデアの創出につなげられるほか、デジタル施策の推進に対する自信が持てるなど、ビジネスキャリアの幅が広がります。G検定の詳細については、一般社団法人日本ディープラーニング協会公式ホームページをご確認ください。
参考:G検定とは – 一般社団法人日本ディープラーニング協会【公式】
E資格
「E資格」は前項で解説した一般社団法人日本ディープラーニング協会による検定資格のひとつで、主にAIエンジニアに求められるディープラーニングに関する実装能力や知識を認定するものです。資格名の「E」は「エンジニア」を意味しており、ディープラーニングの理論について理解しており、適切な手法を用いて実装できるかが試されます。
取得によってAIエンジニアとしての知識・技術が向上し、企業に最適なAIツール開発に向けた会議でも、専門用語を用いながら正しい知識をもとに説明できます。今後の社会はますますAIツールの導入が進み、運用に際して専門知識を有する人材が欠かせないことから、将来性のある資格です。
参考:E資格とは – 一般社団法人日本ディープラーニング協会【公式】
AI実装検定
「AI実装検定」は、AIの基礎理論をはじめ、実践的な技術までを網羅した資格です。資格取得によってAIに関する技術的能力があることが証明できることから、AIツールの開発・導入・運用においては高い需要が見込まれる資格です。
同資格は「B級」「A級」「S級」と3つの認定レベルに分かれており、AI難関資格でもある「G検定」や「E資格」の実装レベルを想定した認定となっています。AIに関する資格を網羅的に取得したい方はチャレンジしてみるとよいでしょう。
参考:AI実装検定
人工知能プロジェクトマネージャー試験
「人工知能プロジェクトマネージャー試験」は(一社)新技術応用推進基盤による、AI技術を通して企業にビジネス的価値を提供できる人材かが問われる試験です。AI導入前に自身でビジネス目標を設計し、技術的道筋を立てて実務をやりきる能力が試験で試されることから、受験にあたってはAIに関する知識・技術を応用する能力を身につけておく必要があります。
試験は月1回受けられるほか、さらに高い点数で合格したいといった場合も翌月以降に再度受験することができます。
参考:人工知能プロジェクトマネージャー試験 – (一社)新技術応用推進基盤公式
なお、AI技術に留まらずデジタル人材育成も検討中の方は、DXに有効な資格について解説しているので併せてご覧ください。
関連記事:デジタル人材育成に有効な資格16選!概要やメリット、注意点を解説
まとめ
AI技術の発展はめまぐるしい一方で、まだまだ不完全な部分も多く、プロンプトの内容によっては既視感を覚える画像・動画・文書が生成されることも珍しくなく、抽出されたデータをそのまま使用すれば、ユーザーの意図せぬ場所で誰かを傷つけたり、著作権を侵害したりする恐れがあります。
このようなトラブルを最小限に抑えるためには、自身のAIを利活用する能力、AIリテラシーを身につけることが大切です。とはいえ、自社従業員のリソースではAIリテラシー教育が行える人材がおらず向上が難しいといった場合もあるでしょう。そのようなときは経済産業省が推奨するように、外部パートナーと連携し、AIリテラシーの向上を図ることをおすすめします。
Peaceful Morningでは、AI活用をプロがサポートする「Robo Runner」がおすすめです。eラーニングコンテンツやチャットサポートを通じ、AIに関するスキルを身につけながら活用できます。自社チームや組織全体のAIリテラシーを向上させたい企業担当者様は、この機会にお気軽にPeaceful Morningへご相談ください。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /
無料トライアル実施中



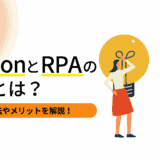
コメントを残す